飛跡を利用した放射線検出器はどれか。
- CR-39
- GM計数管
- 比例計数管
- 蛍光ガラス線量計
- NaI (Tl)シンチレーション検出器
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
1.CR-39
解説
✔ 飛跡検出器とは?:「傷跡」を数える検出器
飛跡検出器は、その名の通り、放射線が物質の中を通過した際にできる「飛跡(ひせき)」、つまり「傷跡」を利用する検出器です。
原理をスケートに例えてみましょう。
- 飛跡の形成
- 荷電粒子(α線など)がスケート選手のように、CR-39というプラスチックの氷の上を滑ります。すると、目には見えない微小な傷(分子結合の破壊)が、滑ったルートに沿って残ります。これが潜伏飛跡です。
- エッチング
- この氷に、水酸化ナトリウムなどの薬品をかけます(化学エッチング)。すると、傷の部分だけが選択的に溶けて、傷が大きく広がります。
- 計数
- 大きくなった傷跡(エッチピット)を顕微鏡で観察し、その数を数えることで、どれだけの放射線が通過したかを評価します。
✔ 各選択肢について
1. CR-39
- ✅ 正解
- プラスチックに残った荷電粒子の「傷跡」を数える、典型的な飛跡検出器です。
2.GM計数管
- ❌ 誤り
- ガイガー・ミュラー管は気体電離を利用します。放射線がガスを電離させて生じる電気パルスを数えます。
3.比例計数管
- ❌ 誤り
- GM計数管と同様に気体電離を利用しますが、パルスの大きさが放射線のエネルギーに比例する領域で使います。
4.蛍光ガラス線量計
- ❌ 誤り
- 発光現象を利用します。
- 放射線を浴びたガラスに紫外線を当てると、浴びた線量に応じた量の蛍光を発します。その光の量を測定します。
5.NaI (Tl)シンチレーション検出器
- ❌ 誤り
- シンチレーション(蛍光)を利用します。
- 放射線が結晶に当たると、そのエネルギーに応じて結晶がピカッと光ります。その光を検出します。
出題者の“声”

この問題は、数ある放射線検出器について、その「測定原理」を正しく分類できているかを試しておる。 「放射線を測る」という目的は同じでも、そのアプローチは全く違うからのう。
- 「気体を電離させて、電気信号を測る」のが、GM管や比例計数管。
- 「光らせて、その光を測る」のが、蛍光ガラスやシンチレーション検出器。
- そして、「物理的な傷跡を残させて、その傷を数える」という、極めてアナログな手法が、この飛跡検出器じゃ。
それぞれの検出器の名前を聞いたときに、頭の中にその「測定原理の動画」が再生されるか。
そこが、知識の定着度を測る分かれ目じゃ。
臨床の“目”で読む

飛跡検出器であるCR-39は、他の電子的な検出器にはないユニークな特徴を持ち、特定の分野で非常に重要な役割を果たしています。
ー主な活躍の場:「ラドン」と「中性子」の測定ー
CR-39の最も代表的な用途は、ラドン濃度の測定です。 ラドンは、崩壊する際にα線を放出します。家の中や作業環境にCR-39の小さなチップを数週間~数ヶ月間設置しておくと、その間のラドン(から放出されたα線)の総量が「飛跡」として記録されます。後でこれを分析することで、平均的なラドン濃度を評価できるのです。
また、中性子の個人被ばく線量計としても利用されます。中性子自体は電荷を持たないので直接は飛跡を作りませんが、CR-39内の水素原子(陽子)を弾き飛ばし、その陽子が飛跡を作ることを利用します。
ーなぜCR-39が使われるのか?ー
- 電源が不要(パッシブ型)
- 設置しておくだけで、長期間の積算測定が可能です。
- 小型・安価
- 取り扱いが容易で、多数の地点に設置できます。
- γ線の影響を受けにくい
- γ線に対する感度が非常に低いため、γ線が多く存在する環境でも、α線や中性子だけを選択的に測定できます。
このように、CR-39は特定の種類の放射線を、長期間にわたって静かに記録し続ける「無口な記録係」として、環境放射線モニタリングなどの分野で活躍しているのです。
今日のまとめ
- CR-39は、荷電粒子がプラスチックに残した「飛跡(傷跡)」を化学処理で拡大し、数えることで放射線を検出する飛跡検出器である。
- GM管や比例計数管は「気体電離」、蛍光ガラスやNaI(Tl)は「発光」を利用する原理の異なる検出器。
- CR-39は電源不要のパッシブ型検出器として、主にラドンや中性子の長期間にわたる積算線量測定に用いられる。

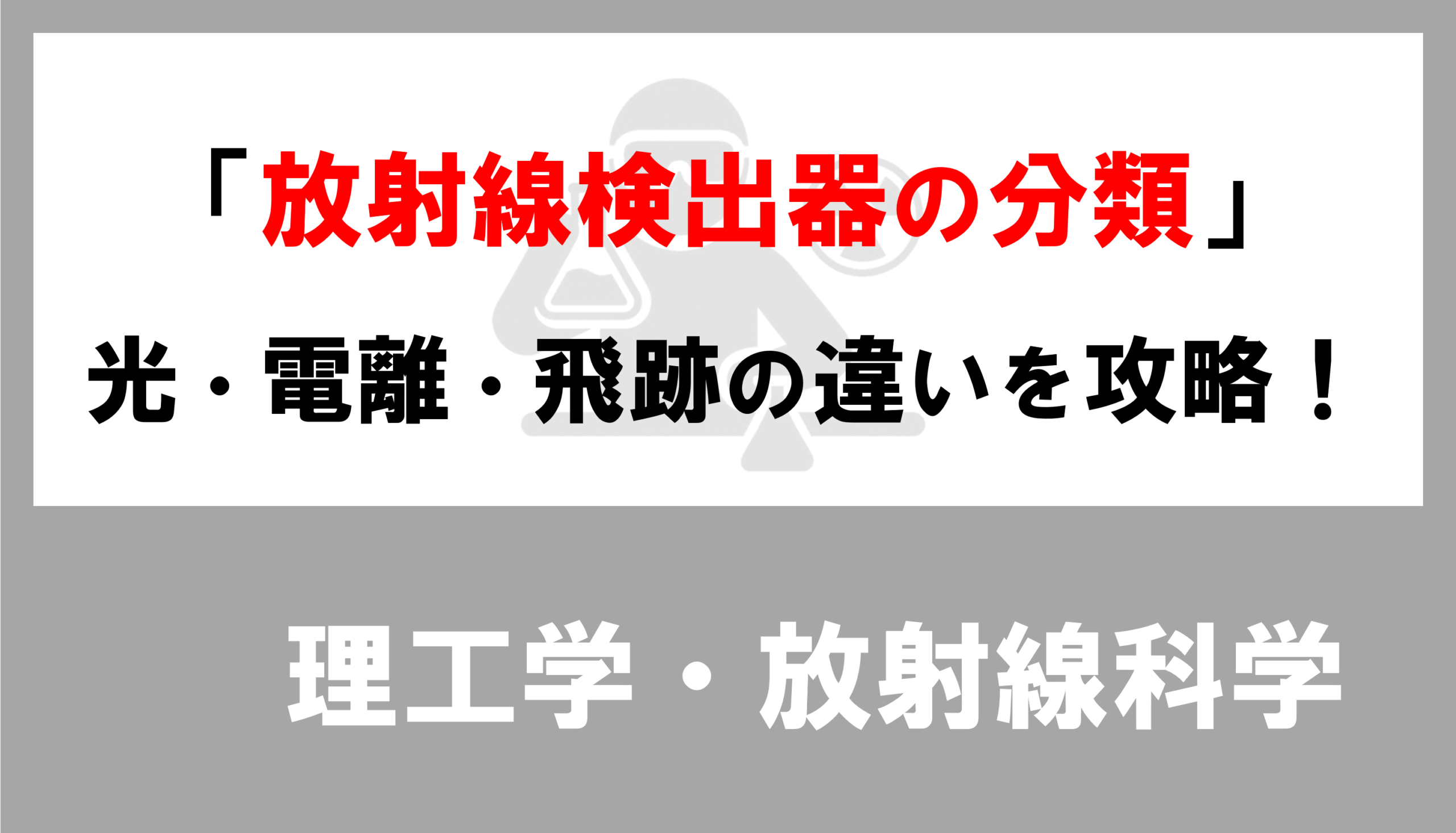
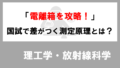

コメント