結合組織でないのはどれか。
- 腱
- 爪
- 筋膜
- 骨膜
- 靭帯
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
2.爪
解説
✔ そもそも「結合組織」とは? 🧬
結合組織とは、その名の通り、体内のさまざまな組織や器官のすき間を埋め、つなぎ合わせ、支える役割を持つ組織の総称です。体の構造的な「土台」や「枠組み」を形成していると考えると分かりやすいでしょう。
主な構成要素
- 細胞: 線維芽細胞、脂肪細胞など
- 線維: コラーゲン線維や弾性線維といった、組織に強度や弾力性を与えるタンパク質の線維
- 基質: 細胞と線維の間を埋める、水分やヒアルロン酸などを含むゲル状の物質
これらの構成バランスによって、非常に硬い「骨」から、流動性のある「血液」まで、多種多様な組織が結合組織に含まれます。
✔ 結合組織の分類と代表例
- 疎性結合組織
- 皮下組織など、線維がまばらで柔らかい組織
- 密性結合組織
- 腱、靭帯、筋膜、骨膜など、コラーゲン線維が密に詰まった強靭な組織
- 特殊結合組織
- 骨、軟骨、脂肪組織、血液
この分類からも分かる通り、選択肢にある腱、筋膜、骨膜、靭帯は、すべて密性結合組織に属します。
✔ では「爪」は何か?
爪は、結合組織ではなく、「上皮組織」に分類されます。 具体的には、皮膚の最も外側にある表皮が、硬いケラチンというタンパク質に変化(角化)してできたものです。皮膚は、外側から表皮(上皮組織)と真皮(結合組織)で構成されており、爪や毛は、この表皮から派生した「皮膚付属器」と呼ばれます。
✔ 各選択肢について
1. 腱
- ❌ 誤り
- 結合組織です。筋肉の力を骨に伝える、コラーゲン線維が豊富な強靭な組織です。
2.爪
- ✅ 正解
- 結合組織ではありません。皮膚の表皮(上皮組織)が硬く角質化したもので、発生の由来が異なります。
3.筋膜
- ❌ 誤り
- 結合組織です。筋肉一本一本や、筋肉のグループを包み込む線維性の膜です。
4.骨膜
- ❌ 誤り
- 結合組織です。骨の表面を覆い、骨に栄養を供給したり、骨折の治癒を助けたりする重要な膜です。
5.靭帯
- ❌ 誤り
- 結合組織です。骨と骨とをつなぎ、関節を安定させる強靭な線維の束です。
出題者の“声”

この問題の狙いは、「結合組織」という広い概念を正しく理解し、異なる由来を持つ「上皮組織」由来の構造物とを、明確に区別できるかを問うことにある。
「腱」「靭帯」「膜」…これらはすべて、体を“つなぎ・支える”という結合組織の役割を、その名前から連想しやすい。 一方で「爪」は、見た目が硬いため、つい骨や腱の仲間だと勘違いしがちじゃ。しかし、その“出身”は皮膚の表皮、つまり上皮組織じゃ。
- 結合組織 = 体の「内側」で支える、つなぐ
- 上皮組織 = 体の「表面」を覆う、守る
この、役割と由来による対比を頭に入れておけば、爪が仲間外れであることは一目瞭然のはずじゃ。
臨床の“目”で読む

ー結合組織の理解は画像診断の基本ー
放射線技師にとって、結合組織の知識は、CTやMRIの画像上で、なぜ組織がそのように見えるのかを理解するための基礎となります。
- CT画像で腱や靭帯が白く(高吸収に)見える理由
- コラーゲン線維が密に詰まっており、水分が少ないため、X線が透過しにくいからです。
- MRI(T1強調像やT2強調像)で筋膜や腱が黒く(低信号に)見える理由
- 水分含有量が極端に少なく、信号を発するプロトンが少ないためです。
- 骨膜反応
- 骨折や骨の腫瘍、炎症などが起こると、骨膜が刺激されて新しい骨を作り始めます。これはX線写真やCTで観察できる重要な診断所見です。
このように、各組織が「何でできているか(=組織学)」を理解していると、「画像でどう見えるか」という知識と結びつき、より深い画像解釈が可能になるのです。
今日のまとめ
- 結合組織は、体を支え、つなぐ役割を持つ組織で、腱、靭帯、筋膜、骨膜、骨、軟骨、血液などが含まれる。
- 爪は、皮膚の表皮が硬く変化した上皮組織由来の構造物であり、結合組織ではない。
- 「内側で支える=結合組織」「表面を覆う=上皮組織」という役割で区別すると分かりやすい。
- 結合組織の性質を理解することは、CTやMRIで組織がなぜそのように見えるのかを理解する上で重要である。

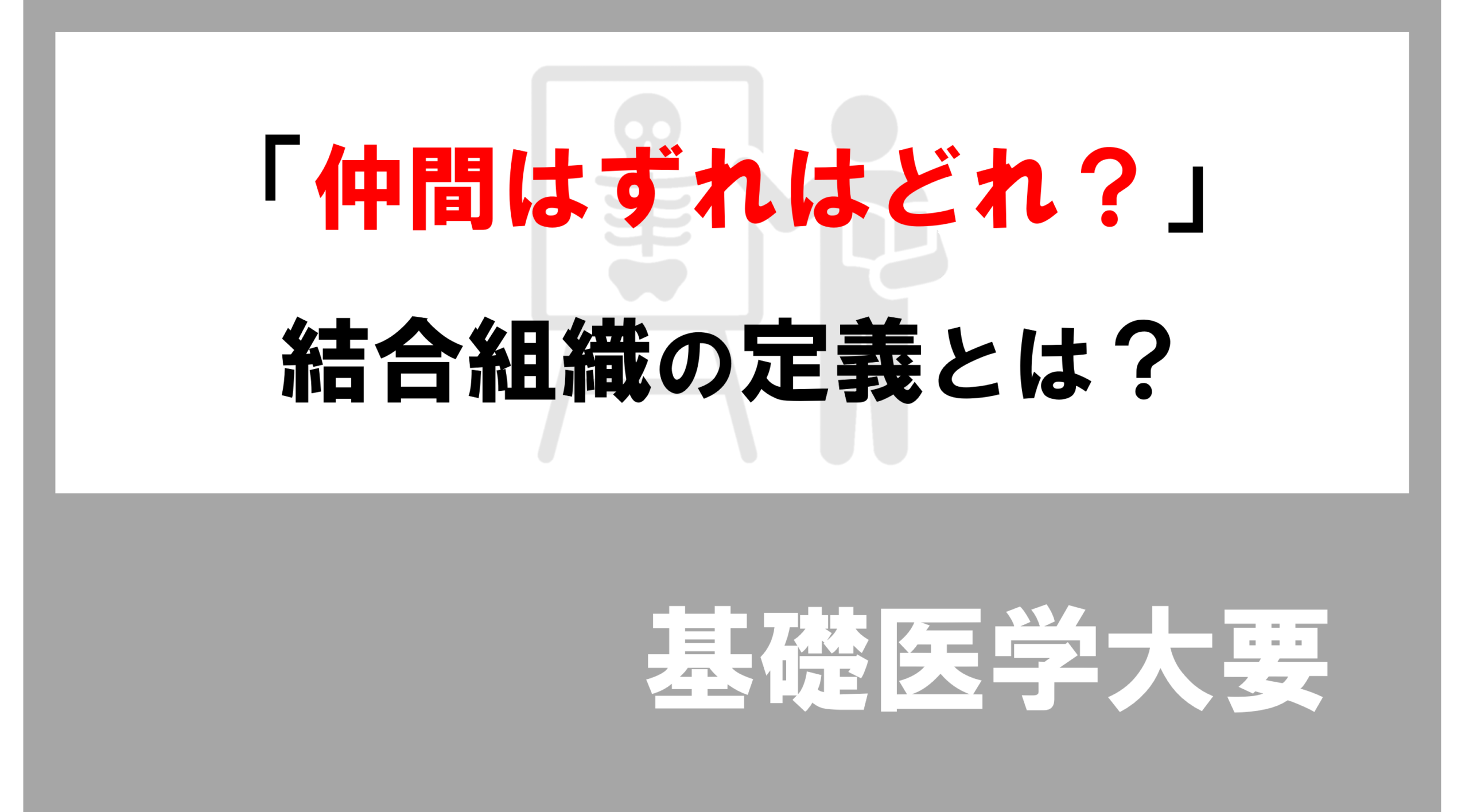


コメント