X 線 CT を用いた SPECT 減弱補正で、CT 値から線減弱係数への変換テーブル作成に関係するのはどれか。2つ選べ。
- 収集時間
- CT 管電圧
- 被検者の体格
- 放射性医薬品の投与量
- 放射性核種のエネルギー
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
2.CT管電圧
5.放射性核種のエネルギー
解説
✔ SPECT減弱補正とは?
- SPECT検査では、体の中から出てくるγ線をカメラでとらえて画像にします。
でも、そのγ線は体の中を通るときに骨や臓器に吸収されて、減弱するため、画像が暗くなったりゆがんだりしてしまいます。
それを直すために、CTで得られる「CT値」を使って、減弱の程度を計算する補正が必要になります。
✔ CT値 → 線減弱係数への変換テーブルとは?
- CT画像の明るさ(CT値)は、120kVpぐらいのX線エネルギーで測られたものです。でも、SPECTで使う放射性医薬品(たとえば⁹⁹ᵐTc)は、違うエネルギー(たとえば140 keV)のγ線を出しています。なので、「CTのX線エネルギーに対するCT値」を「SPECTのγ線エネルギーでの減弱係数(μ)」に換算してくれる変換テーブルが必要になります。
1. 収集時間
- ❌ 誤り
- 長く撮れば画像がなめらか(画像ノイズ低減)になりますが、CT値とμの関係とは無関係。
2. CT管電圧
- ✅ 正解
- X線のエネルギーが変わるとCT値のスケールも変わるため、それに合わせた専用の変換テーブルが必要になります。
3.被検者の体格
- ❌ 誤り
- 体格の違いはノイズやビームハードニングには影響しますが、変換テーブルそのものには関係ありません。
4.放射性医薬品の投与量
- ❌ 誤り
- 画像のカウントには関係しますが、線減弱係数(μ)という物理定数には関係しません。
5.放射性核種のエネルギー
- ✅ 正解
- γ線のエネルギーによって物質に吸収されやすさ(μ)が変わるため、使用する核種ごとに変換テーブルが必要になります。
出題者の“声”

この問題では、「CTとSPECTの融合」がどう技術的に成り立っておるかを確認したかったのじゃ。
特に注意してほしいのが、「CTのX線」と「SPECTのγ線」は別のエネルギーのものという点じゃ。
CTで測った値をそのままSPECTに使えると思っておると、減弱補正がズレて画像が正確に作れなくなるのじゃ。
そして、この問題の引っかけポイントは、「体格」や「投与量」といった、SPECT画像の“見え方”に関係しそうなキーワードをわざと混ぜておるところじゃ。
しかし、それらは変換テーブルの“作成”には無関係。
そこをちゃんと切り分けて判断できるかが、試験を読み解く力なんじゃぞ!
臨床の“目”で読む

CTベースの減弱補正は、SPECT-CT装置を使う最大のメリットのひとつで、
特に肝臓や膵臓、横隔膜下の病変など、深部の臓器で診断精度が大きく変わります。
実際の臨床現場では、「CT管電圧が変わると変換テーブルも変わる」なんてあまり意識しないかもしれません。
でも、装置の導入時やQC(品質管理)では、「減弱係数はエネルギー依存」という原理を理解しておくことが非常に重要です。
また、放射性核種によってγ線のエネルギーが違うので、
たとえば⁹⁹ᵐTc(140 keV)と²⁰¹Tl(70 keV)では別の変換テーブルが必要になります。
もしそれを誤れば、定量評価や病変の検出が大きくズレることになりかねません。
こうした原理をおさえておくことで、「なぜ今この画像が正しいのか?」を自信をもって説明できる技師になれるはずです。
キーワード
- SPECT-CT
- 減弱補正
- CT値
- 線減弱係数
- 変換テーブル

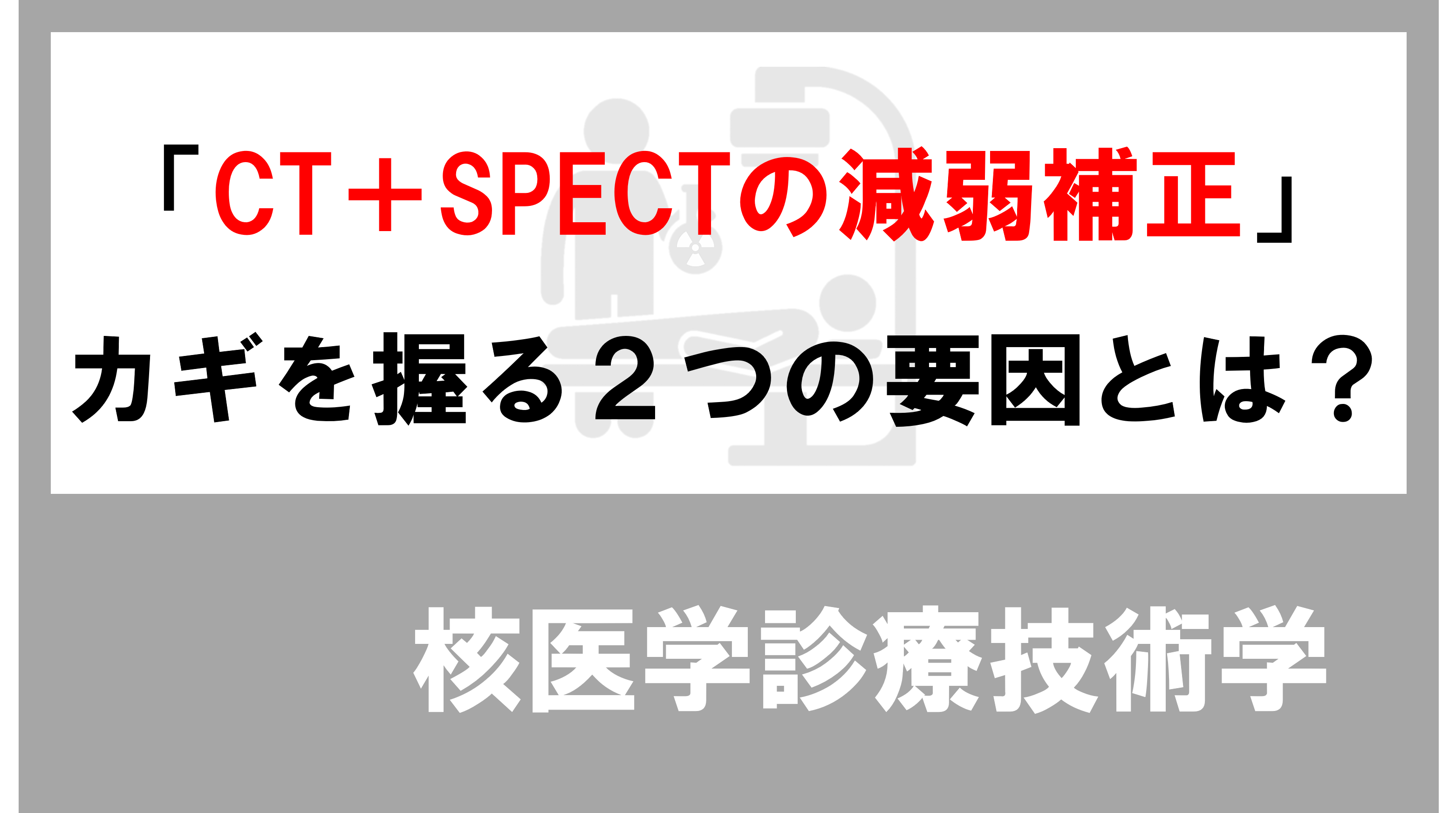
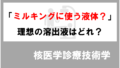
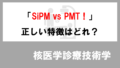
コメント