MRI と関連事項の組合せで正しいのはどれか。
- 拡散強調像 ― TOF法
- 脂肪抑制法 ― b値
- 非造影灌流MRI ― ASL〈arterial spin labeling〉
- MR hydrography ― BOLD効果
- functional MRI ― 化学シフト
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
3.非造影灌流MRI ― ASL〈arterial spin labeling〉
解説
✔ MRI用語の「正しい相棒」探し
この問題は、バラバラにされたカップルを正しいペアに戻してあげる「神経衰弱」のような問題です。 一つずつ、本来のパートナーを探していきましょう。
✔ 各選択肢について
1. 拡散強調像 ─ TOF法
- ❌ 誤り
- 拡散強調像(DWI)の相棒は「b値」です。
- 水分子の拡散(動き)を強調する強さを決めるのがb値です。
- TOF法(Time of Flight)は、MRA(血管撮影)の用語です。「血流の流入効果」を利用します。
2.脂肪抑制法 ─ b値
- ❌ 誤り
- 前述の通り、b値の相棒は「拡散強調像(DWI)」です。
- 脂肪抑制法の相棒になり得るのは、「化学シフト(CHESS法)」や「反転回復法(STIR法)」です。
3.非造影灌流MRI ─ ASL
- ✅ 正解
- ASL(Arterial Spin Labeling):首元の動脈血にRFパルス(電波)を当てて「目印(ラベル)」をつけます。その血液が脳に到達したところを撮像することで、造影剤を使わずに脳血流量(灌流)をマップ化できる技術です。
- 「ASL = 非造影パーフュージョン」。これは必須知識です!
4.MR hydrography ─ BOLD効果
- ❌ 誤り
- MR hydrography(MRCPなど)の原理は、「重T2強調画像」です。水を白く、それ以外を黒くして、水だけを浮き上がらせます。
- BOLD効果の相棒は、選択肢5にある「functional MRI(fMRI)」です。
5.functional MRI ─ 化学シフト
- ❌ 誤り
- functional MRI(fMRI)の相棒はBOLD効果です。脳が活動して酸素を使うと、局所の磁場が変わる(T2が変化する)現象を利用します。
- 化学シフトは、水と脂肪の周波数差のこと。これを利用するのは「脂肪抑制(CHESS)」や「MRS(MRスペクトロスコピー)」です。
出題者の“声”

この問題は、MRIの「略語」と「原理」をセットで記憶できているかを試しておる。
ただ単語を覚えるだけではダメじゃ。 「DWIといったらb値」「fMRIといったらBOLD」「脂肪抑制といったら化学シフト」。 このように、関連ワードを芋づる式に引き出せる回路を作っておくのじゃ。
特に正解となった「ASL」。 これは近年のトレンドじゃ。「造影剤を使わずに血流が見られる」という画期的な技術じゃから、国試でも頻出ワードになってきておるぞ。
MRIは、名前だけ覚えても意味がない。それぞれの原理や評価指標が、どのように画像として現れるかを理解して整理することが大切なのじゃ。
臨床の“目”で読む

ASLって、造影剤を使いにくい患者さん――たとえば小児や腎機能が低下している方――には本当に重宝します。造影剤なしで脳の血流を評価できるので、リスクを避けつつ、ルーチン検査にも組み込みやすい便利な技術なんです。
実際、認知症やTIA(一過性脳虚血発作)の精査では、ASLはよく使われます。
最近では、3D ASLや高分解能タイプも登場していて、臨床応用の幅もかなり広がってきています。
ASLの何が良いかって、やっぱり「静脈穿刺なしで完結」できるところですね。
DWI+ASLを撮れば、急性期脳梗塞の「拡散-灌流ミスマッチ」も評価できて、検査時間は10分強。安全・非侵襲・短時間という、三拍子そろった優れた検査法です。
今日のまとめ
- DWI のキーワード ➡ b値、拡散、ブラウン運動
- fMRI のキーワード ➡ BOLD効果、脳機能マッピング
- 脂肪抑制 のキーワード ➡ 化学シフト、STIR、Dixon
- ASL のキーワード ➡ 非造影、灌流画像(Perfusion)、スピンラベリング

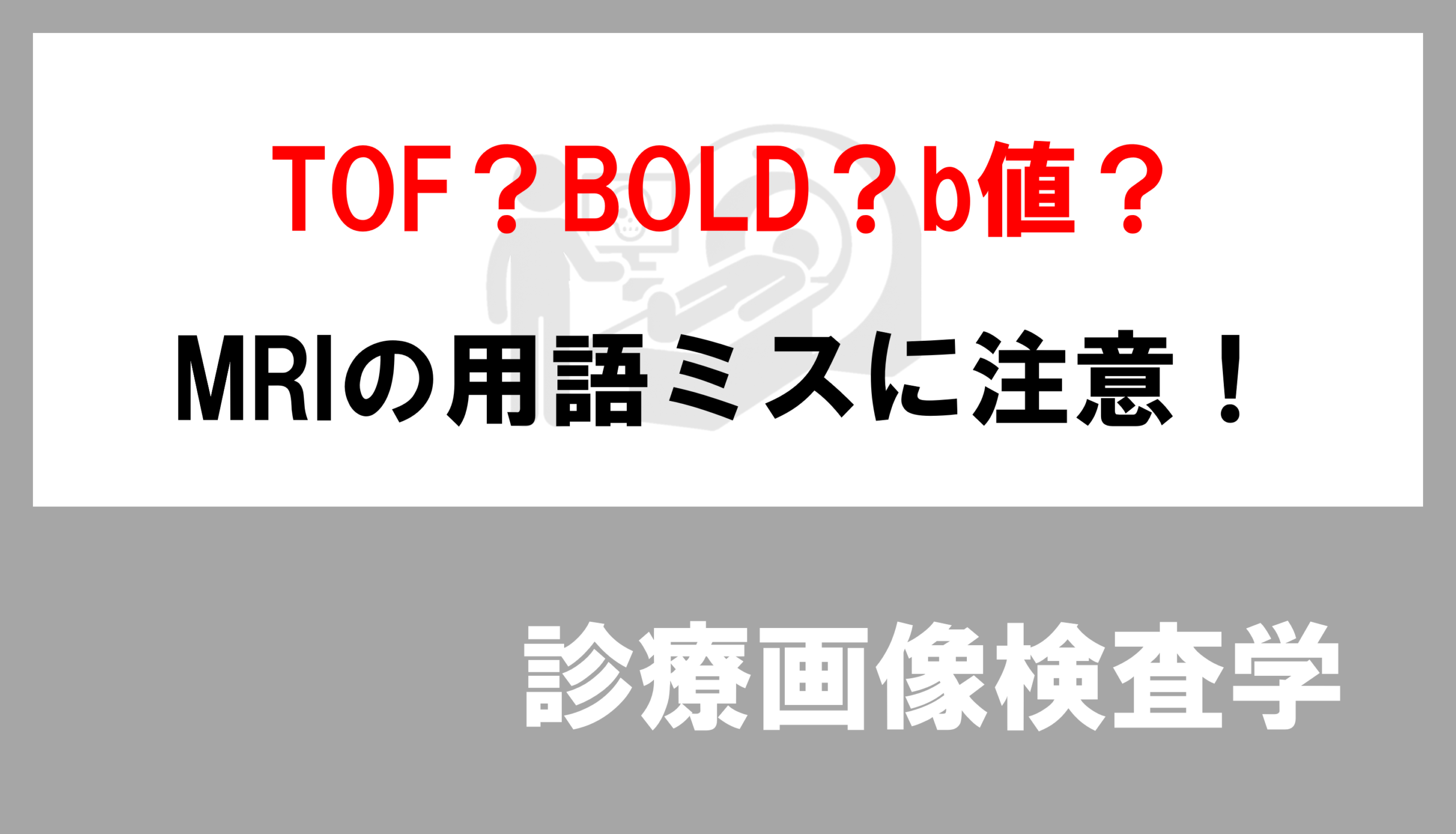

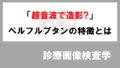
コメント