放射線治療装置の受入試験で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 納入業者のみで実施する。
- 計算値を実測値で検証する。
- コミッショニング後に実施する。
- 仕様書を満たすことを確認する。
- 定期的品質管理の基本データを得る。
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
4.仕様書を満たすことを確認する。
5.定期的品質管理の基本データを得る。
解説
✔ 放射線治療装置の正しい導入プロセス
- 装置の納入・設置
- 受入試験 (Acceptance Test) ← 今回のテーマ
- コミッショニング (Commissioning)
- 臨床使用開始
✔ 受入試験(Acceptance Test)とは?
装置が設置された後、臨床使用を開始する前に行う品質保証の最初のステップです。その目的は、主に以下の2つです。
- 仕様の検証:装置が、契約時にメーカーから提示された仕様書(スペック)通りの機械的・物理的性能を満たしているかを確認します。
- ベースラインデータの取得:今後の定期的品質管理(QA/QC)で「正常値」として参照するための、初期状態の基準データ(ベースライン)を測定・記録します。
この試験は、納入業者と医療機関側が共同で実施しますが、最終的な合否の判断と責任は医療機関側にあります。
✔ 各選択肢について
1.納入業者のみで実施する。
- ❌ 誤り
- 医療機関が主体となり、業者の協力のもとで実施します。
- 装置の性能に最終的な責任を負うのは使用者である医療機関です。
2.計算値を実測値で検証する。
- ❌ 誤り
- これは、治療計画装置(TPS)にビームデータを入力し、その計算精度を検証する「コミッショニング」の作業です。
3.コミッショニング後に実施する。
- ❌ 誤り
- 受入試験はコミッショニングの前段階。
- まず装置の物理性能を受け入れてから、TPS モデル化や線量計算法の検証(コミッショニング)へと進みます。
4.仕様書を満たすことを確認する。
- ✅ 正解
- これが受入試験の最も本質的な目的です。
- 出力の安定性、機械的な精度、安全機能などが仕様を満たしているかを厳密にチェックします。
5.定期的品質管理の基本データを得る。
- ✅ 正解
- 測定結果はベースラインとなり、以後の 定期 QA/QC で経時変化を判定する基準データになります。
出題者の“声”

この問題では、放射線治療装置を導入する際の「受入試験」の立ち位置と目的を、正確に理解しているかを確認したかったのじゃ。
「受入試験」「コミッショニング」「品質管理(QA)」…似たような言葉が並ぶが、それぞれ役割も実施する順番も全く違う。この区別がついていないと、引っかかってしまうぞ。
特に「受入試験 → コミッショニング」という順序は絶対じゃ。まだ性能が保証されていない装置のデータで治療計画の準備(コミッショニング)を始めるなど、土台がぐらついたまま家を建てるようなものじゃからのぅ。
また、「メーカーがやってくれる」という受け身の姿勢も禁物じゃ。最終的に装置を使い、患者さんの治療に責任を持つのは医療機関じゃ。
自分たちで性能を確かめ、「この装置は安全に使える」とハンコを押す。受入試験とは、そのための最初で最も重要な儀式なのじゃ!
臨床の“目”で読む

放射線治療装置の受入試験は、“臨床責任の起点”ともいえる作業です。
この段階で測定された全てのデータは、装置がその役目を終えるまでの十数年間、すべての品質管理の礎となります。
- 受入試験は「装置の性能保証」:メーカーが約束したスペックが、本当に達成されているかを確認します。ここで基準を満たさなければ、医療機関は改善を要求したり、最悪の場合は受け入れを拒否したりする権利があります。
- コミッショニングは「治療計画の準備」:受入試験に合格した装置のビーム特性(PDD、プロファイルなど)を詳細に測定し、そのデータを治療計画装置(TPS)に入力して、正確な線量計算ができるようにモデルを構築する作業です。
このように、両者は目的も内容も異なります。放射線技師としては、「この測定値は仕様を満たしているか?」「将来のQAで比較できるよう、再現性の高い方法で記録しているか?」といった視点が不可欠です。
受入試験を単なる「納品チェック」と捉えず、これから始まる高精度治療の安全性を自分たちの手で築き上げる第一歩として、主体的に取り組む姿勢が求められます。
キーワード
- 受入試験(Acceptance Test)
- コミッショニング
- 仕様書確認
- QA(品質保証)

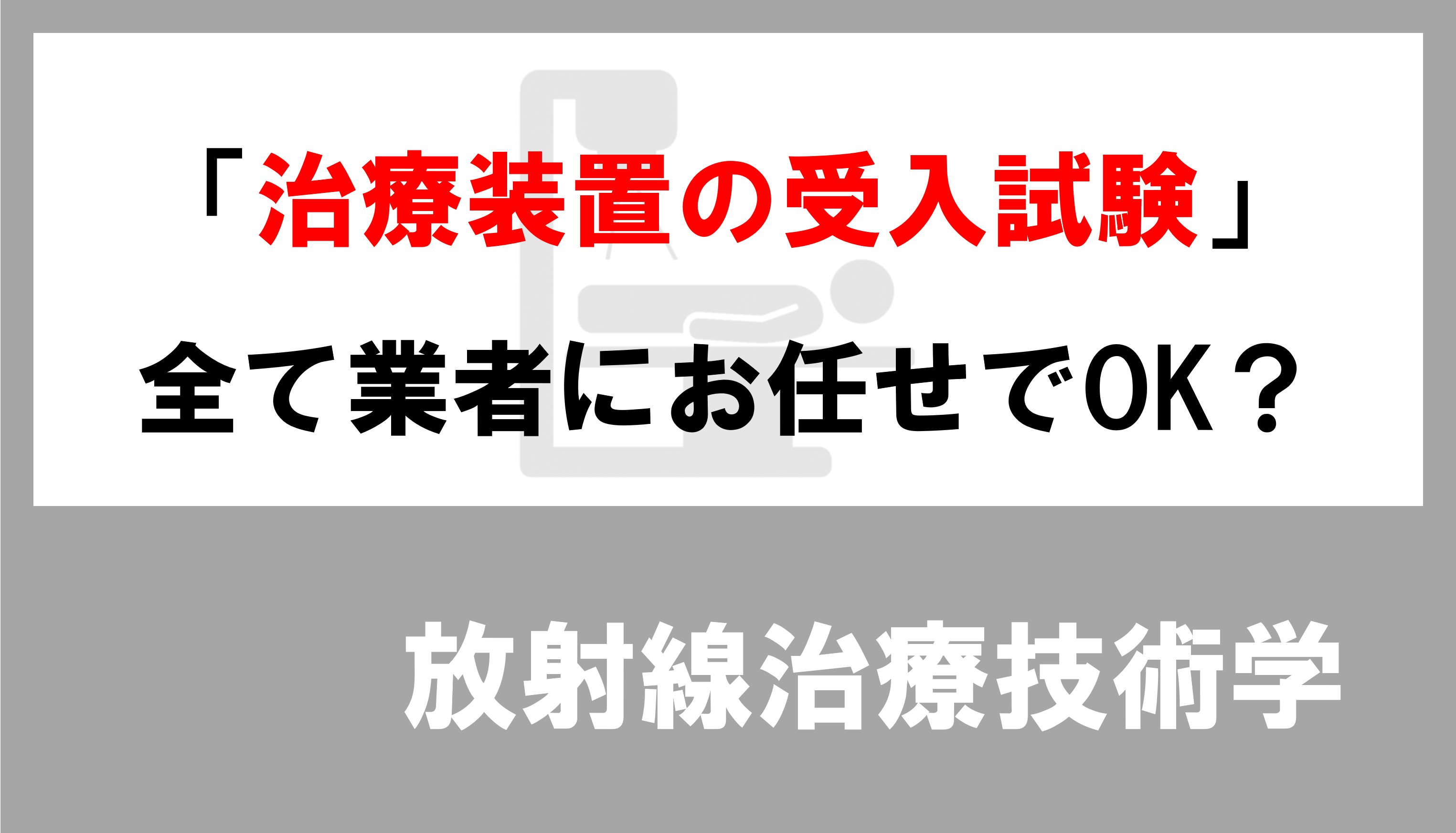


コメント