骨粗鬆症性椎体骨折が多いのはどれか。
- 上部頚椎
- 下部頚椎~上部胸椎
- 中部胸椎
- 下部胸椎~上部腰椎
- 下部腰椎
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
4.下部胸椎~上部腰椎
解説
✔ 骨粗鬆症性椎体骨折とは?
- 骨密度の低下(骨粗鬆症)により骨がもろくなり、咳やくしゃみ、前屈みになるといった日常生活の些細な動作でも、背骨(椎体)が圧迫されて潰れてしまう骨折です。
- 特に閉経後の女性に多く見られます。
✔ なぜ「下部胸椎~上部腰椎」で多いのか?
この部位、特に胸腰椎移行部(T12-L1あたり)に骨折が集中するのには、明確な力学的理由があります。
- 構造上の弱点:ヒトの背骨は、S字カーブを描いています。胸椎は肋骨に支えられて動きが少ない後弯カーブ、一方、腰椎は可動性が大きく負荷がかかる前弯カーブです。下部胸椎~上部腰椎は、この「動きの少ない部分」と「よく動く部分」の境目にあたり、物理的なストレスが最も集中するのです。
- 力学的な負荷:ちょうどテコの支点のように、上半身の重さがこの移行部に集中するため、骨がもろくなっていると、特に椎体の前方が潰れやすくなります(楔状骨折)。
✔ 各選択肢について
1. 上部頚椎
- ❌ 誤り
- 可動性は大きいですが、頭部を支える荷重は比較的小さいため、骨粗鬆症性の圧迫骨折は稀です。
2.下部頚椎~上部胸椎
- ❌ 誤り
- この部位もカーブの移行部ではありますが、胸腰椎移行部ほど大きなストレスはかかりません。
3.中部胸椎
- ❌ 誤り
- 肋骨に囲まれた「胸郭」によって支持されており、比較的安定しているため、骨折の頻度は高くありません。
4.下部胸椎~上部腰椎
- ✅ 正解
- 胸椎の後弯と腰椎の前弯が切り替わる胸腰椎移行部(T12-L1が中心)は、力学的なストレスが最大となるため、最も骨折しやすい部位です。
5.下部腰椎
- ❌ 誤り
- 荷重は大きいですが、椎体自体が大きく頑丈であるため、骨粗鬆症による骨折は胸腰椎移行部より少なくなります。
出題者の“声”

この問題の狙いは、骨粗鬆症性椎体骨折が「どこに起きやすいか」という知識だけでなく、「なぜ、そこに起きやすいのか」という解剖学・力学的な理由まで理解できているかを確認することじゃ。
背骨のS字カーブは、荷重を分散するための巧みな構造じゃが、そのカーブの「変わり目」は、どうしても構造上の弱点となる。
特に胸腰椎移行部は、肋骨で守られた固定域(胸椎)から、自由に動く可動域(腰椎)へと切り替わる、まさにストレスの集中地点なんじゃ。
CTやMRIを見ていると、T12やL1が楔形に変形しているのを頻繁に目にするじゃろう。それは偶然ではなく、力学的な必然なんじゃ。
臨床の“目”で読む

骨粗鬆症性椎体骨折は、診断から治療まで放射線技師が深く関わる疾患です。私たちの役割は多岐にわたります。
- 診断における役割
- 好発部位の意識:単純X線撮影やCT、MRIを撮る際、常に胸腰椎移行部を注意深く観察する癖をつけることが重要です。腹部CTの撮影範囲に、骨折した椎体が含まれていることも珍しくありません。
- 骨折の“新旧”の判断:患者さんの痛みの原因を特定するため、MRIのT2強調画像やSTIR法で椎体内の浮腫(高信号)の有無を確認し、骨折が「新しい(新鮮)」ものか「古い(陳旧性)」ものかを判断する材料を提供します。これは治療方針の決定に極めて重要です。
- 治療における役割
- 経過観察とケア:保存的治療では、コルセットを装着した患者さんのX線撮影を定期的に行います。撮影時に患者さんの負担を最小限にしつつ、安全にコルセットの着脱を補助することも、大切な技術の一つです。
- 外科的治療のサポート:経皮的椎体形成術(BKP)では、手術室でCアーム型X線透視装置を操作し、医師が椎体内にセメントを注入するのをリアルタイムでサポートします。ここでも技師の専門性が発揮されます。
このように、放射線技師は単に画像を撮影するだけでなく、解剖学的・力学的な知識を基に病態を理解し、診断から治療までチーム医療の一員として貢献することが求められています。
キーワード
- 骨粗鬆症性椎体骨折
- 圧迫骨折 / 楔状骨折
- 胸腰椎移行部 (T12/L1)
- 生理的弯曲
- 経皮的椎体形成術 (BKP)

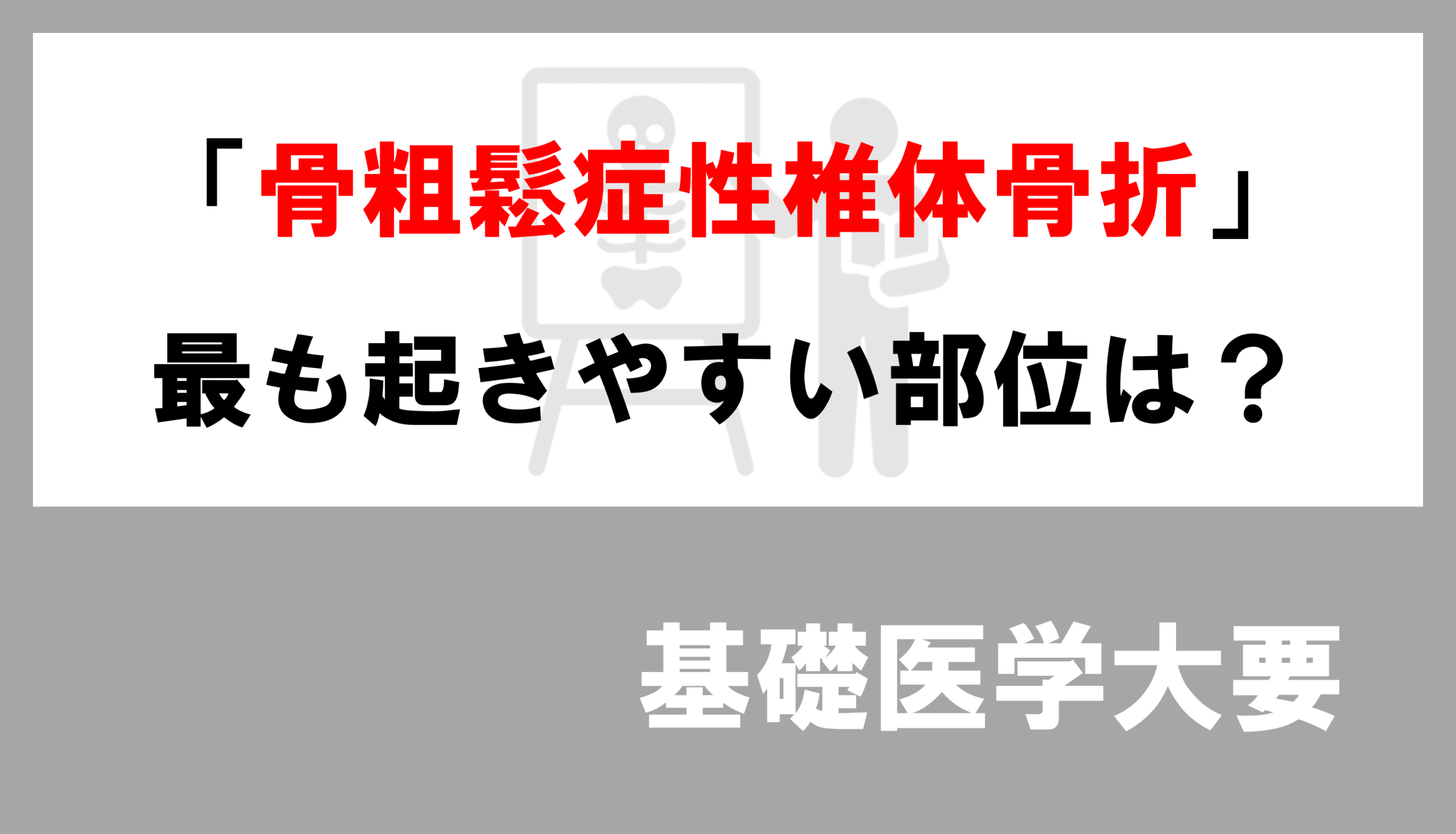

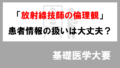
コメント