灰白質はどれか。
- 内包
- 脳梁
- 被殻
- 前交連
- 放線冠
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
3.被殻
解説
✔ 灰白質と白質の違いとは??
✅ 灰白質
- 構成要素:神経細胞の本体(細胞体)が密集している部分。
- 役割:情報の処理、計算、判断、命令などを行う「CPU・処理センター」。
- 主な部位:大脳皮質、視床、大脳基底核(被殻、尾状核など)。
- MRI所見:一般的にT1強調画像で白質より暗く(低信号)、T2強調画像で明るく(高信号)見える。
✅ 白質
- 構成要素:神経細胞から伸びる神経線維(軸索)の束。ミエリン(髄鞘)という脂肪組織で覆われているため白く見える。
- 役割:灰白質同士、あるいは灰白質と体の各部を結ぶ「通信ケーブル・配線」。
- 主な部位:内包、放線冠、脳梁、前交連など。
- MRI所見:一般的にT1強調画像で灰白質より明るく(高信号)、T2強調画像で暗く(低信号)見える。
✔ 各選択肢について
1. 内包
- ❌ 誤り
- 大脳皮質と脳幹・脊髄などを結ぶ神経線維が密集した、典型的な白質。
2.脳梁
- ❌ 誤り
- 左右の大脳半球をつなぐ最大の神経線維の束。
3.被殻
- ✅ 正解
- 大脳基底核を構成する主要な部分であり、神経細胞体が密集した灰白質。
- 運動の調節などに重要な役割を果たします。(※尾状核とともに線条体を、淡蒼球とともにレンズ核を形成)
4.前交連
- ❌ 誤り
- 左右の側頭葉などをつなぐ神経線維の束。
5.放線冠
- ❌ 誤り
- 内包と大脳皮質を放射状に結ぶ神経線維の束。
出題者の“声”

この問題の狙いは、脳の解剖構造について、「情報を処理する場所(灰白質)」と「情報を伝える道(白質)」を、明確に区別できているかを確認することじゃ。
灰白質は神経細胞の本体(司令部)が集まる場所、白質はその司令部同士を結ぶケーブル網。この機能的な役割の違いを理解していれば、それぞれの構造がどちらに分類されるか、おのずと見えてくるはずじゃ。
被殻は大脳基底核という、運動制御の中枢。まさに「処理する場所」じゃから灰白質。一方、内包や脳梁、放線冠などは、いかにも「何かを繋いでいそう」な名前の通り、神経線維の束、つまり白質なんじゃ。
解剖名をただ暗記するだけでなく、その構造が持つ「役割」とセットで理解すること。それが、画像から病態を読み解く力につながる、本当の解剖学の勉強なんじゃ。
臨床の“目”で読む

灰白質と白質の区別は、頭部CT・MRIを読影する上での“地図”そのものです。なぜなら、多くの神経疾患は、どちらを主座として発生するかによって、その種類や症状が大きく異なるからです。
- 脳血管障害(脳梗塞・脳出血)
- 被殻や視床といった深部灰白質は、細い穿通枝動脈に栄養されており、高血圧性のラクナ梗塞や脳出血の好発部位です。
- 内包や放線冠といった白質の障害は、運動野や感覚野からの神経線維路を直接破壊するため、重篤な運動麻痺や感覚障害を引き起こします。
- 脱髄疾患(例:多発性硬化症)
- 神経線維を覆うミエリンが破壊される病気のため、病変は白質に好発します。脳梁や脳室周囲の白質に特徴的な病変が見られるかどうかが、診断の鍵となります。
- てんかん・皮質形成異常
- 神経細胞の異常な興奮が原因となるため、病変の主座は大脳皮質(灰白質)にあります。
私たち放射線技師は、撮影時にこれらの構造を正確に識別できるだけでなく、「この疾患だから、白質(あるいは灰白質)のこの部分に注目しよう」と、病態生理に基づいて画像のチェックポイントを意識することが求められます
キーワード
- 灰白質 / 白質
- 神経細胞 / 神経線維(軸索)
- 大脳基底核 / 被殻
- 内包 / 脳梁 / 放線冠

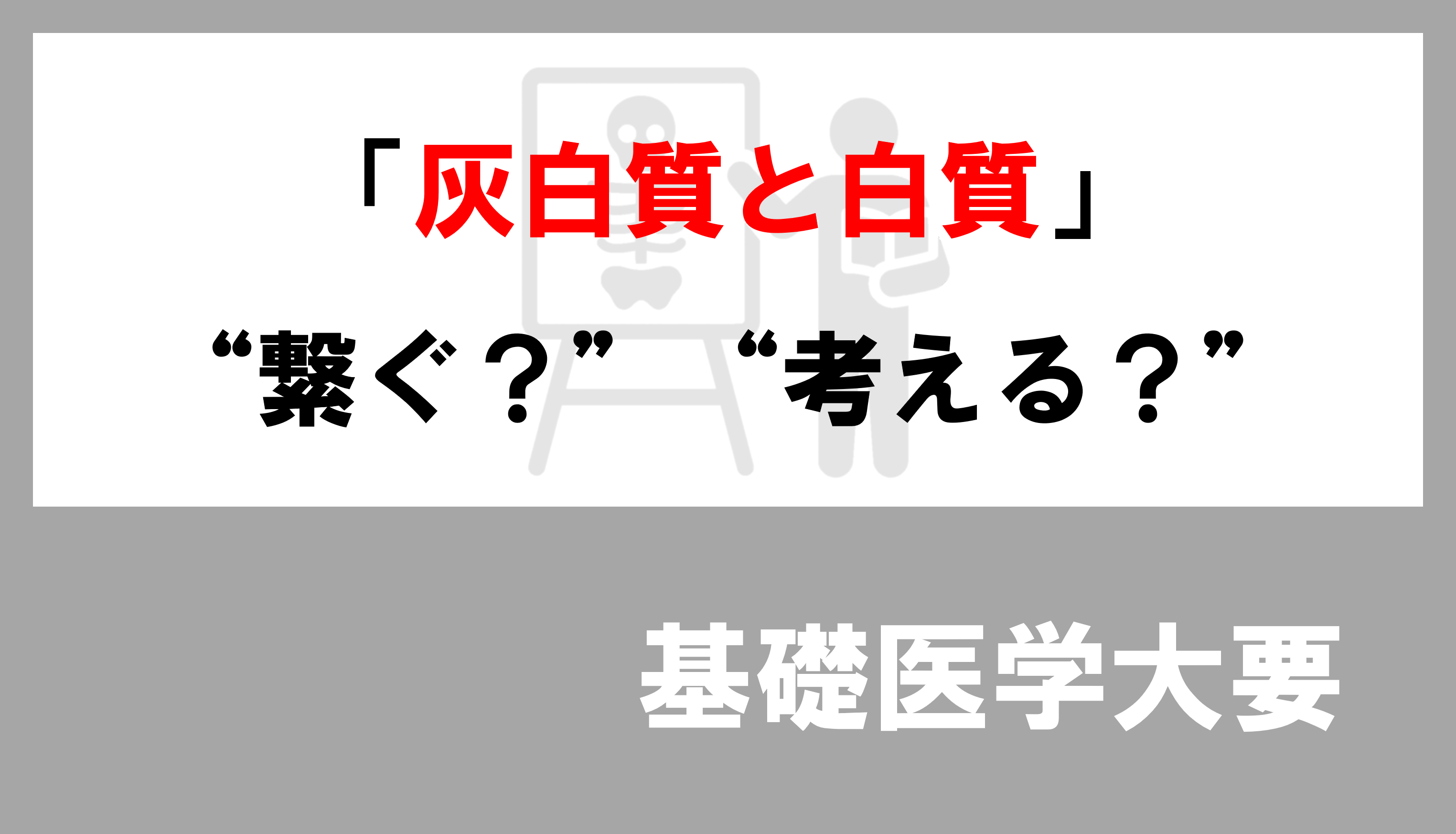


コメント