悪性腫瘍の発生数が最も少ないのはどれか。
- 食道
- 胃
- 小腸
- 結腸
- 直腸
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
3.小腸
解説
✔ 日本の消化管がん 罹患数(2019年データに基づく)
国立がん研究センターの統計によると、年間の罹患数(新たにがんと診断される人の数)には大きな差があります。
- 結腸・直腸がん(大腸がん):合わせて約155,500人 (男女計で第1位)
- 胃がん:約124,300人 (男女計で第3位)
- 食道がん:約26,300人
- 小腸がん:約3,300人
✔ なぜ小腸がんは少ないのか?
小腸は消化管全体の長さの約75%を占めるにもかかわらず、がんの発生は稀です。
その理由として、以下のように考えられています。
- 通過速度が速い:食物の通過が速いため、発がん性物質と粘膜が接触している時間が短い。
- 腸内環境:アルカリ性の消化液や、希薄な腸内細菌叢により、発がん性物質が作られにくい。
- 免疫機能:パイエル板などのリンパ組織が豊富で、免疫監視機構が活発に働いている。
結果として、がん化のチャンスが他部位に比べて低いと考えられています。
✔ 各選択肢について
1. 食道
- ❌ 誤り
- 年間2万人以上が罹患します。
- 特に男性の飲酒・喫煙が強いリスク因子です。
2.胃
- ❌ 誤り
- ヘリコバクター・ピロリ菌感染を主因とし、依然として日本で非常に多いがんです。
3.小腸
- ✅ 正解
- 消化管の中では圧倒的に発生数が少なく、全悪性腫瘍の1%未満とも言われる希少がんです。
4.結腸
- ❌ 誤り
- 直腸がんと合わせて「大腸がん」として集計され、男女計では日本で最も罹患数が多いがんです。
- 食生活の欧米化などが関与しているとされます。
5.直腸
- ❌ 誤り
- 結腸に次いで多く、大腸がんの一部を構成します。
出題者の“声”

この問題では、消化管における悪性腫瘍の発生頻度を正しく把握し、臨床現場での“常識”として身についているかを確認したかったのじゃ。
「胃がん」「大腸がん」はよく目にする定番の疾患じゃが、「小腸がんは極めてまれ」という疫学的事実は、意外と印象に残りにくい。
そこで今回はあえて、「発生数が最も少ないのはどれか?」」という逆方向の問い方で、知識の網の目に空きがないかを確かめたのじゃ。
この問題は、「がんの知識を持っているか?」というだけでなく、
- 消化管という構造を通して発生頻度を比較できるか
- 大腸=結腸+直腸という分類を正しく整理できているか
- “見かけない=発生が少ない”という実感が持てているか
といった、国家試験らしい“頻度感覚”と構造理解のバランスを確認するための一問じゃったのじゃ。
「見たことがない=レア」ではなく、「なぜあまり見ないのか?」という問いを持てるかどうかが、疫学を臨床に活かす力なのじゃ!
臨床の“目”で読む

がんの発生頻度は、「日常の画像診断で、どの臓器に、どれくらい注意を払うべきか」という、私たちの注意の配分に直結します。
- 高頻度のがん(大腸、胃、食道) これらの臓器は、CTや内視鏡、造影検査において常に「がんがないか」という視点で重点的に観察されます。特に大腸がんと胃がんは罹患数が非常に多く、画像上のわずかな壁肥厚や粘膜の不整も見逃せません。まさに「見逃し厳禁エリア」です。
- 低頻度のがん(小腸) 小腸は、その長さにもかかわらず腫瘍の発生が極めてまれです。そのため、画像検査で小腸を第一に疑って精査するケースは多くありません。むしろ、腸閉塞や虚血、消化管出血といった、腫瘍以外の病態で注目されることがほとんどです。小腸がんが疑われるのは、
- 原因不明の慢性的な消化管出血や貧血がある場合
- カプセル内視鏡やバルーン内視鏡で精査が必要になった場合 など、特殊なケースが中心となります。
私たち放射線技師が、こうした疫学的な背景知識を持つことで、「この検査の主目的は何か」「どの臓器にクリティカルな病変が隠れている可能性が高いか」を意識した撮影計画や画像処理が可能になります。それは結果的に、診断の質の向上と、見逃しの低減に貢献するのです。
キーワード
- がん罹患数
- 小腸がん
- 大腸がん(結腸・直腸がん)
- 胃がん
- 食道がん

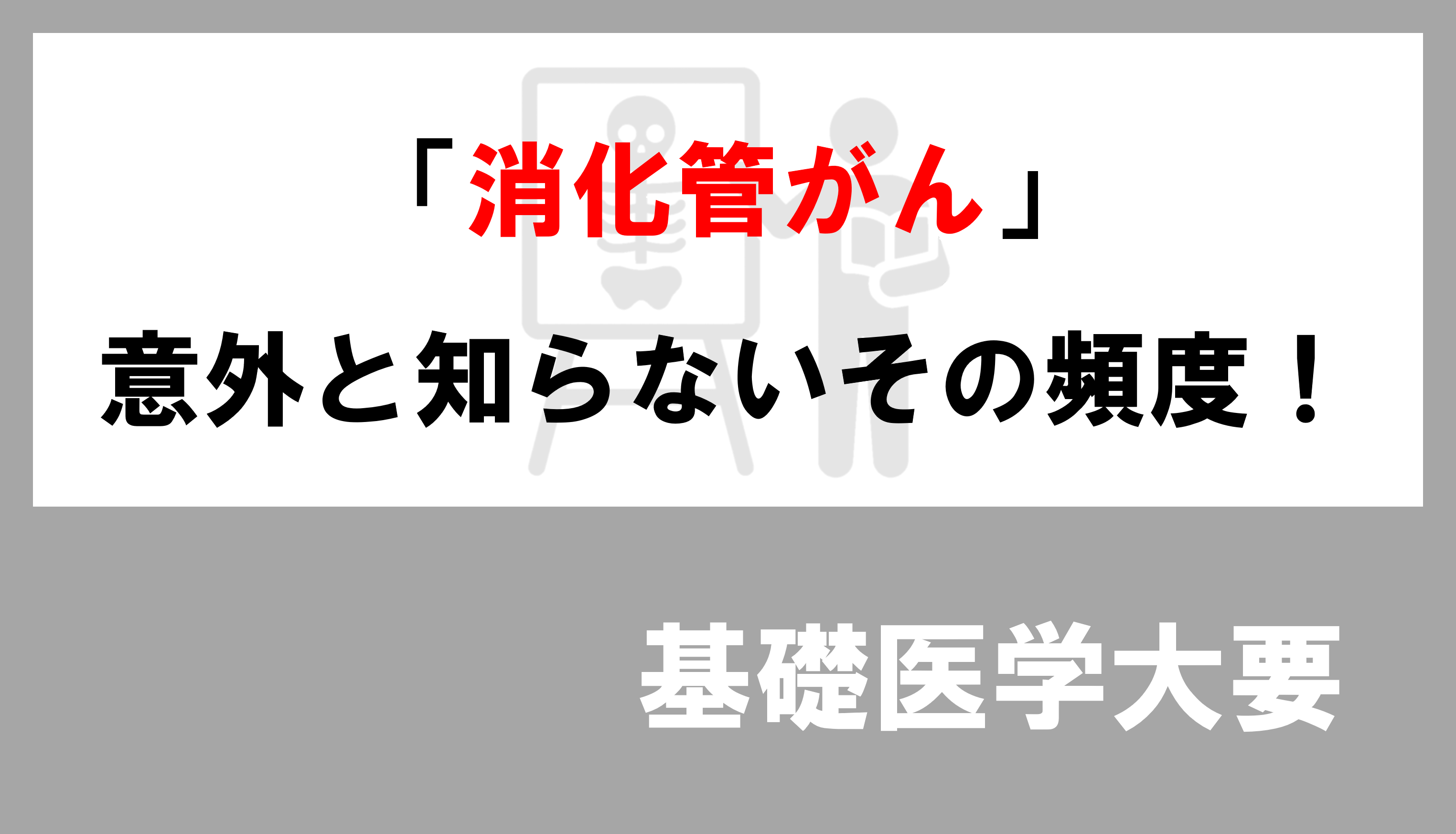


コメント