体温の恒常性で誤っているのはどれか。
- 体温中枢は視床下部にある。
- 運動によって体温は上昇する。
- 寒冷の環境では代謝が低下する。
- 体温には概日リズムが存在する。
- 年齢が高くなるにつれ体温は低下する。
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
3. 寒冷の環境では代謝が低下する。
解説
✔ 体温恒常性(ホメオスタシス)とは?
体温の恒常性とは、外部の環境が変化しても、体温を一定(約37℃)に保とうとする、生命維持に不可欠な仕組みです。
この司令塔は脳の視床下部にあり、主に以下の2つのメカニズムを調整しています。
- 熱産生(体内で熱をつくる)
- ふるえ産熱:筋肉を細かく震わせる(シバリング)。
- 非ふるえ産熱:褐色脂肪細胞の活動や、甲状腺ホルモンによる基礎代謝の亢進。
- 熱放散(体外へ熱をにがす)
- 血管拡張:皮膚の血流を増やして熱を逃がす。
- 発汗:汗が蒸発する際の気化熱で体温を下げる。
✔ 各選択肢について
1. 体温中枢は視床下部にある。
- ✅ 正しい
- 視床下部は、体温のセットポイントを設定し、上記の熱産生・熱放散のバランスを自律神経やホルモンを介してコントロールしています。
2.運動によって体温は上昇する。
- ✅ 正しい
- 運動による筋肉の活動は、大量の熱を産生するため、体温は上昇します。
- 運動後に汗をかくのは、上昇した体温を下げるための正常な熱放散の反応です。
3.寒冷の環境では代謝が低下する。
- ❌ 誤り
- 寒い環境では、体は体温を維持するために熱産生を高めようとします。
- そのために、ふるえ(シバリング)を起こしたり、甲状腺ホルモンを分泌して基礎代謝を亢進させたりします。
- したがって、代謝は「低下」ではなく「上昇」します。
4.体温には概日リズムが存在する。
- ✅ 正しい
- 体温は1日の中でも一定ではなく、早朝に最も低く、夕方にかけて最も高くなるという約0.5~1.0℃の周期的変動があります。
5.年齢が高くなるにつれ体温は低下する。
- ✅ 正しい
- 高齢者は、筋肉量の減少による基礎代謝の低下や、自律神経機能の低下により、若年者に比べて平均体温がやや低くなる傾向があります。
出題者の“声”

この問題の狙いは、体温調節という身近なテーマを通じて、生理学の基本原理を正確に理解できているかを確認することにある。
特に、今回のひっかけは3番じゃ。「寒いと、なんとなく活動が鈍って代謝も下がりそう」という直感的なイメージは、実は生理学的な事実とは真逆なんじゃな。
体は、寒いときには必死に熱を作ろうとして、むしろ代謝を「上げる」方向に働く。この「恒常性を維持するための体の健気な反応」を正しく理解できているかが、この問題の核心じゃ。
視床下部、概日リズム、加齢による変化といった他の選択肢も、すべて臨床で重要となる基本知識。一見すると当たり前に見える選択肢の中に、一つだけ巧妙なウソを混ぜておる。
見た目はシンプルでも、正解を導くには確かな論理と根拠が必要であり、暗記型ではなく理解型の学習ができているかを測る問題じゃ。
臨床の“目”で読む

体温は、患者さんの状態を把握するための最も基本的なバイタルサインですが、その解釈には生理学的な背景知識が不可欠です。
- 視床下部と体温
- 脳梗塞や脳腫瘍などで視床下部が損傷されると、体温調節が機能不全に陥り、異常な高体温(中枢性発熱)や低体温をきたすことがあります。
- 高齢者の体温
- 高齢者は平熱が低い傾向があるため、「37.5℃の発熱」は若者における38℃以上の発熱に相当すると考えるべき場合があります。また、感染症にかかっても体温が上がりにくく、「なんとなく元気がない」という状態が、重篤な感染症の唯一のサインであることも少なくありません。「熱がないから大丈夫」という判断は、高齢者においては特に危険です。
- 概日リズム
- 解熱剤の効果判定や、感染症の熱型(稽留熱、弛張熱など)を評価する際には、この日内変動を考慮に入れる必要があります。
私たち医療従事者は、体温計が示す「数字」だけを見るのではなく、その背景にある患者さんの年齢、時間帯、活動量、基礎疾患などを総合的に考慮して、その「数字の意味」を解釈する力が求められます
キーワード
- 恒常性 (ホメオスタシス)
- 視床下部
- 熱産生 / 熱放散
- 基礎代謝
- 概日リズム

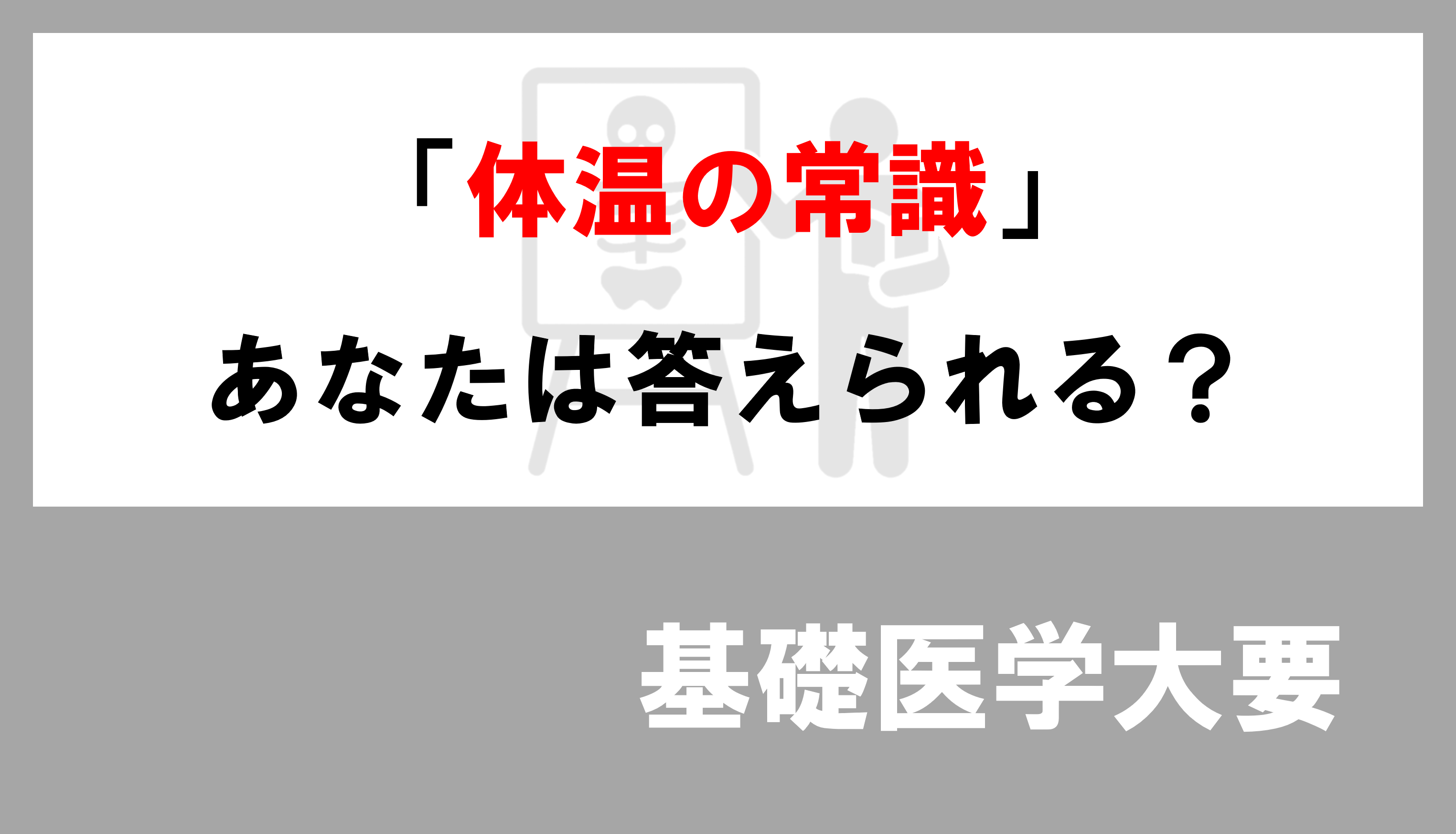


コメント