成人の正常組織で放射線感受性が最も低いのはどれか。
- 肝臓
- 小腸
- 心筋
- 皮膚
- 水晶体
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
3.心筋
解説
✔ 放射線感受性の原則(ベルゴニー・トリボンドーの法則)とは?
細胞分裂能が高く未分化な細胞ほど感受性が高く、分裂能が低く成熟した細胞ほど感受性が低いとされています。正常組織では、腸管や皮膚の基底層など増殖能の高い部位が早期反応(急性反応)を示し、筋肉や神経など分裂の少ない組織は反応が弱い・遅い(晩期反応)傾向があります。
✔ 各選択肢について
1. 肝臓
- ❌ 誤り
- 普段はあまり分裂しませんが、再生能力が高く、必要時には分裂できるため中程度の感受性に分類されます。
2.小腸
- ❌ 誤り
- 小腸の粘膜上皮は、数日という驚異的なスピードで細胞が入れ替わる、まさに高感受性組織の代表格です。
3.心筋
- ✅ 正解
- 心筋細胞は、一度分化・成熟すると基本的に再分裂しない「終末分化細胞」です。
- 細胞分裂がほとんどないため、放射線感受性は正常組織の中で最も低いグループに入ります。
4.皮膚
- ❌ 誤り
- 皮膚の表皮も、常に新しい細胞が作られ、垢となって剥がれ落ちています。
- 細胞分裂が活発なため、感受性は比較的高く、日焼けのように急性障害(紅斑など)が起こりやすい組織です。
5.水晶体
- ❌ 誤り
- 水晶体の細胞分裂の頻度は低いですが、放射線によって白内障が起こりやすいことが知られています。
- その発症しきい線量は比較的低いため、放射線防護や治療計画上は「臨床的に感受性が高い組織」として扱われます。
出題者の“声”

この問題は、ただの暗記では解けん。放射線感受性の「原則」と、臨床上の「例外」を、両方とも理解しているかを試しておるのじゃ。
多くの学生は「ベルゴニー・トリボンドーの法則」を覚える。そこでワシは、その法則の例外中の例外である「水晶体」をワナとして仕掛けた。 「分裂頻度が低いから感受性も低いはずだ」と早とちりした者は、このワナにまんまと引っかかる。
正解の「心筋」は、法則に忠実な「分裂しないから感受性が低い」組織の代表じゃ。 つまり、原則(心筋)と例外(水晶体)を正確に区別し、それぞれの理由を説明できるか。
答えにたどり着くには、見かけのイメージや臓器の大きさにまどわされず、細胞の性質から考える力が必要なんじゃよ。
基礎が身についておれば、これは確実に拾いたい問題じゃ!
臨床の“目”で読む

組織の放射線感受性の違いを理解することは、放射線治療計画の根幹そのものです。
治療計画とは、がんに高線量を集中させつつ、周囲の正常組織への線量をいかに低く抑えるかの戦いです。この時、特に守るべき正常組織を「リスク臓器」と呼びます。
- 例えば、腹部の腫瘍を治療する際は、隣接する高感受性の小腸に当たる線量を厳しく制限します。
- 頭頸部腫瘍の治療では、水晶体に線量が当たると白内障のリスクがあるため、細心の注意を払ってビームの向きなどを調整します。
私たち放射線技師は、この感受性の違いを理解しているからこそ、日々のミリ単位での正確な位置決め(ポジショニング)がいかに重要かを実感できます。正確な照射こそが、リスク臓臓器を守り、治療効果を最大化するのです。
「感受性が低い」の、もう一つの意味とは?
では、「心筋」や「神経」のように放射線感受性が低いことは、良いこと尽くめでしょうか? 少し視点を変えてみましょう。
救急医療の現場では、「心筋梗塞」や「脳梗塞」は一刻を争います。なぜなら、心筋細胞や神経細胞は一度ダメージを受けて壊死してしまうと、二度と再生しない(細胞分裂しない)からです。
これは、放射線感受性の低さの理由と全く同じです。 つまり、「感受性が低い」という性質は、「放射線という外的要因には強いが、一度失うと取り返しがつかない」という弱点でもあるのです。 この二面性を知っておくと、人体の理解がさらに深まりますよ。
今日のまとめ
- 放射線感受性の原則は「細胞分裂が活発なほど感受性が高い」(ベルゴニー・トリボンドーの法則)。
- この原則から、筋肉(心筋)や神経は感受性が最も低い組織となる。
- 水晶体は例外!分裂頻度は低いが、白内障を起こしやすいため臨床的には高感受性として扱う。

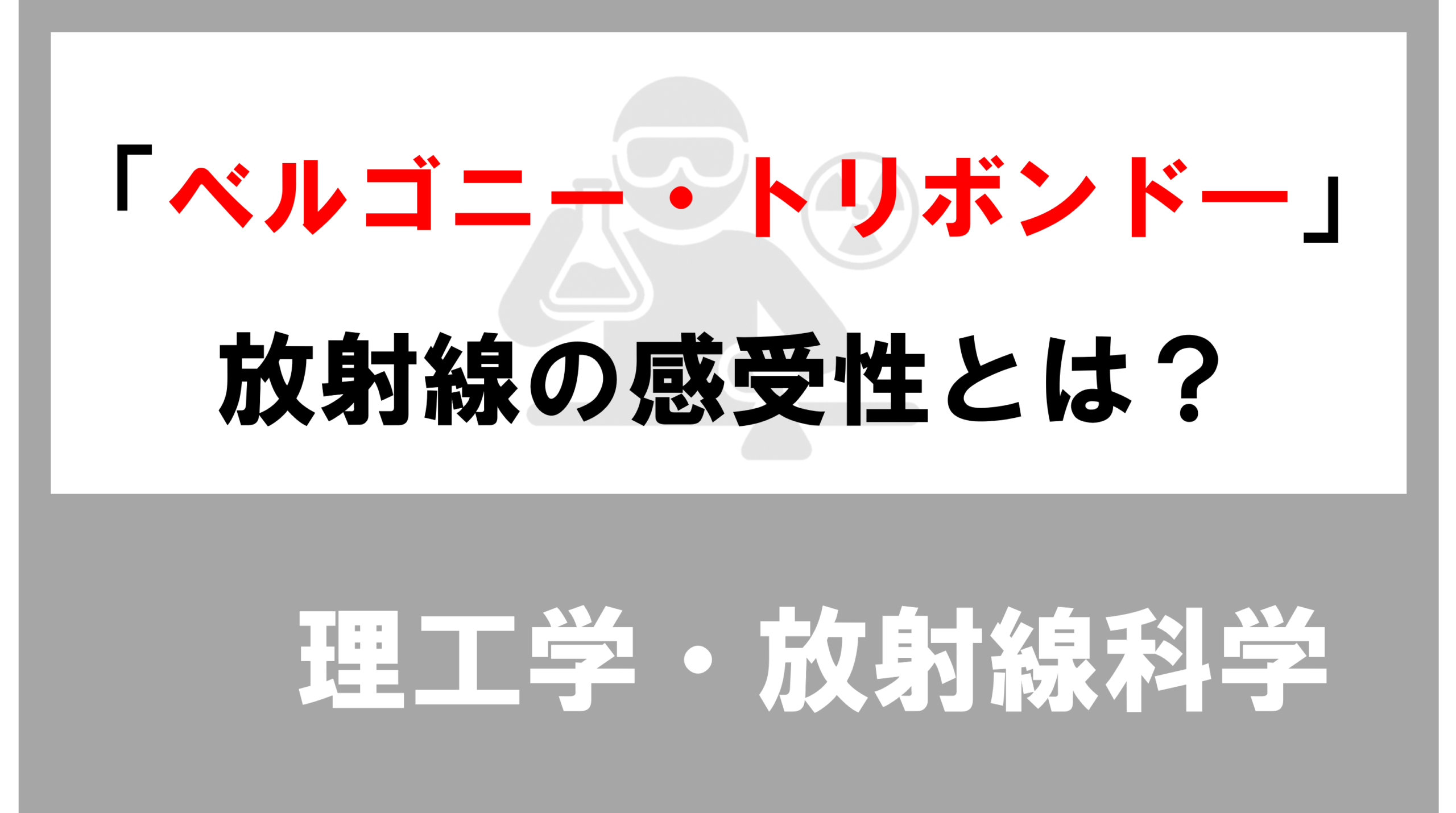


コメント