放射線誘発がんで正しいのはどれか。
- 前立腺癌の主な発がん形式である。
- 小児より成人の方が発がんリスクは高い。
- 発がんリスクは線量率によって変化しない。
- 放射線による肺癌の発生リスクと喫煙は関係ない。
- 同じ物理線量の場合、低LET放射線より高LET放射線の方が発がんリスクは高い
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
5.同じ物理線量の場合、低LET放射線より高LET放射線の方が発がんリスクは高い。
解説
✔ 放射線誘発がんの基本:「確率的影響」
まず大前提として、放射線誘発がんは「確率的影響」に分類されます。これは、
- しきい値はない(どんなに低い線量でも、リスクはゼロにはならないとされる)。
- 発生する確率は、被ばく線量が多いほど高くなる。
- 発症しても、がんの重篤度(悪性度)は線量の大小とは関係しない。
という特徴を持っています。そして、その発生確率は、被ばくした線量だけでなく、様々な要因に影響されます。
✔ LET(線エネルギー付与:Linear Energy Transfer)とは?
LETとは、放射線が体の中を進むときに、通り道にどれだけ密にエネルギーを落としていくかを示す指標です。イメージで言うと…
- 低LET放射線 (X線, γ線など)
- エネルギーをパラパラとまき散らしながら進む「散弾銃」のよう。DNAへの損傷もまばらで、修復される可能性も比較的高い。
- 高LET放射線 (α線, 中性子線, 重粒子線など)
- エネルギーを狭い範囲に集中させて突き進む「大砲の弾」のよう。DNAに複雑で修復困難な傷(二重鎖切断など)をつけやすくなります。
このため、同じ1Gyという物理的な線量でも、「大砲の弾」である高LET放射線の方が、生物学的な影響(発がんリスクなど)は格段に高くなります。
✔ 各選択肢について
1. 前立腺癌の主な発がん形式である。
- ❌ 誤り
- 放射線誘発がんとしてリスクが高いとされるのは、骨髄(白血病)、甲状腺、乳腺、肺、皮膚などです。
- 前立腺がんは、放射線誘発がんの代表例には含まれません。
2.小児より成人の方が発がんリスクは高い。
- ❌ 誤り
- 小児の方が、成人よりも発がんリスクは高いです。理由は、①細胞分裂が活発で放射線の影響を受けやすいこと、②被ばくしてからがんが発症するまでの期間(潜伏期間)を考えても、人生が長い分、発症する可能性が高まるためです。
3.発がんリスクは線量率によって変化しない。
- ❌ 誤り
- 同じ総線量でも、一度にドカンと被ばくするより、ゆっくり時間をかけて被ばくする方が、発がんリスクは低くなります。
- これは、低い線量率だと、被ばく中に体内のDNA修復機能が働く余裕が生まれるためで、「線量率効果」と呼ばれます。
4.放射線による肺癌の発生リスクと喫煙は関係ない。
- ❌ 誤り
- 放射線と喫煙は、それぞれが肺がんのリスク因子ですが、両方が重なるとリスクは単純な足し算(相加効果)ではなく、掛け算のように増大する「相乗効果」があることが知られています。
5.同じ物理線量の場合、低LET放射線より高LET放射線の方が発がんリスクは高い
- ✅ 正解
- 高LET放射線はDNAに致命的な損傷を与えやすいため、生物学的な影響(発がんリスクを含む)が大きくなります。
出題者の“声”

この問題は、「放射線誘発がんの性質」について、正しい知識と放射線生物学の理解があるかを見極める一問じゃ。
放射線ががんのリスクを高めることは知られておるが、その影響は年齢・線質・線量率・他の因子との相互作用など、さまざまな条件に左右される。
つまり、単純な知識ではなく、多面的に理解しておるかを確かめたいのじゃ。 そのために各選択肢が、独立した重要な知識になっておる。
- 感受性の高い臓器を知っておるか?
- 年齢によるリスクの違いを分かっておるか?
- 線量率効果という現象を知っておるか?
- 喫煙のような他の発がん因子との関係は?
- そして、放射線の「質」であるLETの影響は?
ただ「がんは確率的影響」と覚えているだけでは、これらのワナはかわせん。 線量、線量率、年齢、生活習慣、そして線質(LET)。
これら全ての要因が複雑に絡み合ってリスクが決まる、という本質を掴めておる者だけが、自信を持って正解できるのじゃ。
臨床の“目”で読む

放射線誘発がんの知識は、我々の日々の業務の根幹をなす、極めて重要なものです。
① 放射線防護の基本理念「ALARA」として
「しきい値はない」からこそ、私たちは「ALARA(As Low As Reasonably Achievable:合理的に達成可能な限り低く)」の原則に従い、患者さんと自身の被ばくを常に最小限に抑える努力をします。適切な撮影条件の設定、不要な検査の回避、確実な防護など、全ての業務がこのリスクを低減するためにあります。
② 放射線治療への理解として
一方で、「高LET放射線は生物効果が高い」という性質は、最先端のがん治療に応用されています。 それが、「粒子線治療(陽子線治療、重粒子線治療)」です。
- 重粒子線のような高LET放射線は、従来のX線(低LET)では治療が難しかった放射線抵抗性のがんに対しても、非常に高い殺細胞効果を発揮します。
- また、エネルギーをがん病巣に集中させ(ブラッグピーク)、その先にある正常組織にはほとんどダメージを与えないという特性も持っています。
このように、「発がんリスクが高い」という危険な性質は、裏を返せば「がんを殺す力が強い」という治療の武器にもなり得るのです。この二面性を理解していると、放射線医学の奥深さが見えてきます。
今日のまとめ
- 放射線誘発がんは確率的影響(しきい値なし、線量に応じて確率UP)。
- リスクは小児で高く、線量率が低いと低下し、喫煙で相乗的に増加する。
- 同じ線量なら、高LET放射線(α線, 重粒子線)の方が低LET放射線(X線)より発がんリスクが高い。
- この知識は、日常の放射線防護(ALARA)と、粒子線治療の原理を理解する土台となる。

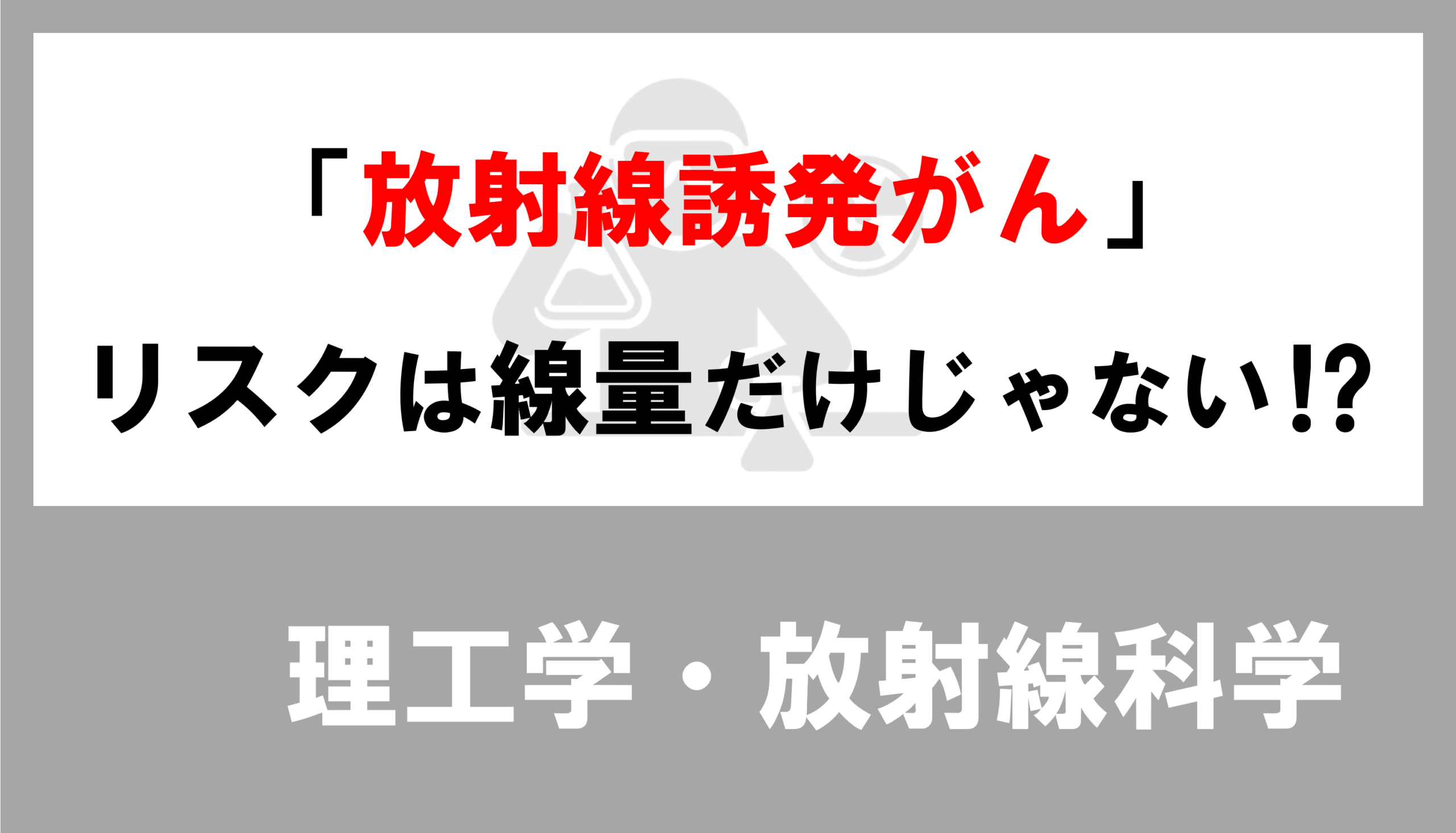

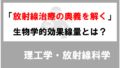
コメント