光子と物質の相互作用で正しいのはどれか。
- 特性X線は連続スペクトルを持つ。
- 光電効果は最外殻の電子で起こることが多い。
- 電子対生成の生じた位置で消滅放射線が発生する。
- コンプトン散乱において散乱光子の波長は入射光子の波長より長くなる。
- 光子エネルギーが1 MeVのとき鉛と光子の相互作用は電子対生成が主である。
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
4.コンプトン散乱において散乱光子の波長は入射光子の波長より長くなる。
解説
✔ 光子と物質の3大相互作用
X線やγ線などの光子が体内に入射した際、そのエネルギーを物質に与える主要なプロセスは以下の3つです。
それぞれの「主役」と「結末」を区別することが重要です。
- 光電効果
- 光子のエネルギーが低い領域(診断X線エネルギー域)で主役。光子は原子の内殻電子(K殻など)に全エネルギーを渡し、自身は消滅します。エネルギーをもらった電子は原子から飛び出します。
- 結末: 光子は消滅。画像コントラストの源。
- コンプトン散乱
- 幅広いエネルギー領域で起こり、特に人体組織では診断〜治療域で主役。光子は原子の外殻電子と衝突し、ビリヤードのようにエネルギーの一部を電子に与え、自身はエネルギーが低くなって別の方向へ散乱します。
- 結末: エネルギーの低い散乱光子が発生。画質低下(散乱線)の原因。
- 電子対生成
- 光子エネルギーが1.022MeVを超える高エネルギー領域(治療域)でのみ起こります。光子が原子核の近くを通過する際に消滅し、そのエネルギーが「電子」と「陽電子」のペアという物質に変換されます。
- 結末: 光子が消滅し、電子と陽電子のペアが誕生。
✔ 各選択肢について
1. 特性X線は連続スペクトルを持つ。
- ❌ 誤り
- 特性X線は、原子内の電子軌道間のエネルギー差(準位差)によって決まる、特定のエネルギー値だけを持つ線スペクトル。
- 連続スペクトルを持つのは制動放射線です。
2.光電効果は最外殻の電子で起こることが多い。
- ❌ 誤り
- 光電効果は、原子に強く束縛されている内殻の電子(K殻、L殻)と起こりやすい現象です。
3.電子対生成の生じた位置で消滅放射線が発生する。
- ❌ 誤り
- 電子対生成で生まれた「陽電子」は、すぐに消滅しません。まず周囲でエネルギーを失いながら少しだけ移動し、止まりかけたところで近くの電子と結合して消滅(対消滅)し、511keVの消滅放射線を2本放出します。
- 生成位置と消滅位置はわずかにズレます。これはPETの分解能限界の要因の一つです。
4.コンプトン散乱において散乱光子の波長は入射光子の波長より長くなる。
- ✅ 正解
- コンプトン散乱では、入射光子がエネルギーの一部を電子に渡します。
- 光子のエネルギーと波長は反比例の関係(E=hc/λ)にあるため、エネルギーが減少すると、波長は長くなります。
5.光子エネルギーが1 MeVのとき鉛と光子の相互作用は電子対生成が主である。
- ❌ 誤り
- 電子対生成が起こるための最低エネルギー(しきい値)は1.022MeVです。
- 1MeVの光子では電子対生成は起こり得ません。このエネルギー域の鉛では、コンプトン散乱が主となります。
出題者の“声”

この問題は、「光子と物質の相互作用」を正しく理解しておるかを見とる基本問題じゃ。
光電効果・コンプトン散乱・電子対生成……この三大相互作用の特徴をしっかり整理できておるか、そこを試しておる。
ただ名前を覚えているだけでは、ワシが仕掛けたワナにはまるぞ。
正解の選択肢は、物理の最も基本的な関係式を問うておる。
コンプトン散乱でエネルギーを失う。ならば、光子の性質はどう変わる? エネルギーが減れば、波長は長くなる。 この反比例の関係は、放射線物理の常識じゃ。 一つひとつの現象を、その背景にある物理法則と結びつけて理解できているかが、勝負の分かれ目じゃ。
これはまさに、基礎中の基礎。しっかり押さえておけば、サービス問題になる一問じゃ!
臨床の“目”で読む

これら3つの相互作用は、我々が日常的に扱う放射線画像の「すべて」を説明する、まさに土台となる知識です。
- 光電効果:診断のヒーロー
- 骨(原子番号が大きい)で光電効果がよく起こり、X線が吸収されるため、写真は白く写る。軟部組織とのコントラストを生み出す最大の功労者。
- コンプトン散乱:画質の悪役 & 被ばくの原因
- 患者さんの体内で散乱したX線は、検出器に到達して画像をボヤけさせる。これが散乱線。我々が使うグリッドは、この散乱線を除去するためのもの。また、術者や介助者の被ばくの主な原因でもある。
- 電子対生成(&対消滅):PET診断の主役
- PET検査で使う薬剤(FDGなど)から放出される陽電子が、体内で電子と対消滅する際に放出される2本のγ線を捉えることで、がんの位置を特定する。電子対生成は、この原理の逆反応にあたる。
このように、X線写真がなぜ白黒に見えるのか、なぜ防護エプロンが必要なのか、PET検査がなぜ可能なのか、その全ての答えが、この3つの相互作用の中に詰まっているのです。
今日のまとめ
- 光子の3大相互作用は「光電効果」「コンプトン散乱」「電子対生成」。
- コンプトン散乱では光子はエネルギーを失うため、反比例の関係にある波長は長くなる。
- 光電効果は内殻電子と起こり、X線写真のコントラストの源。
- 電子対生成は1.022MeV以上で起こり、その逆反応である対消滅はPETの基本原理。
- 診断画像の質や被ばくは、すべてこれらの物理現象によって決まる。

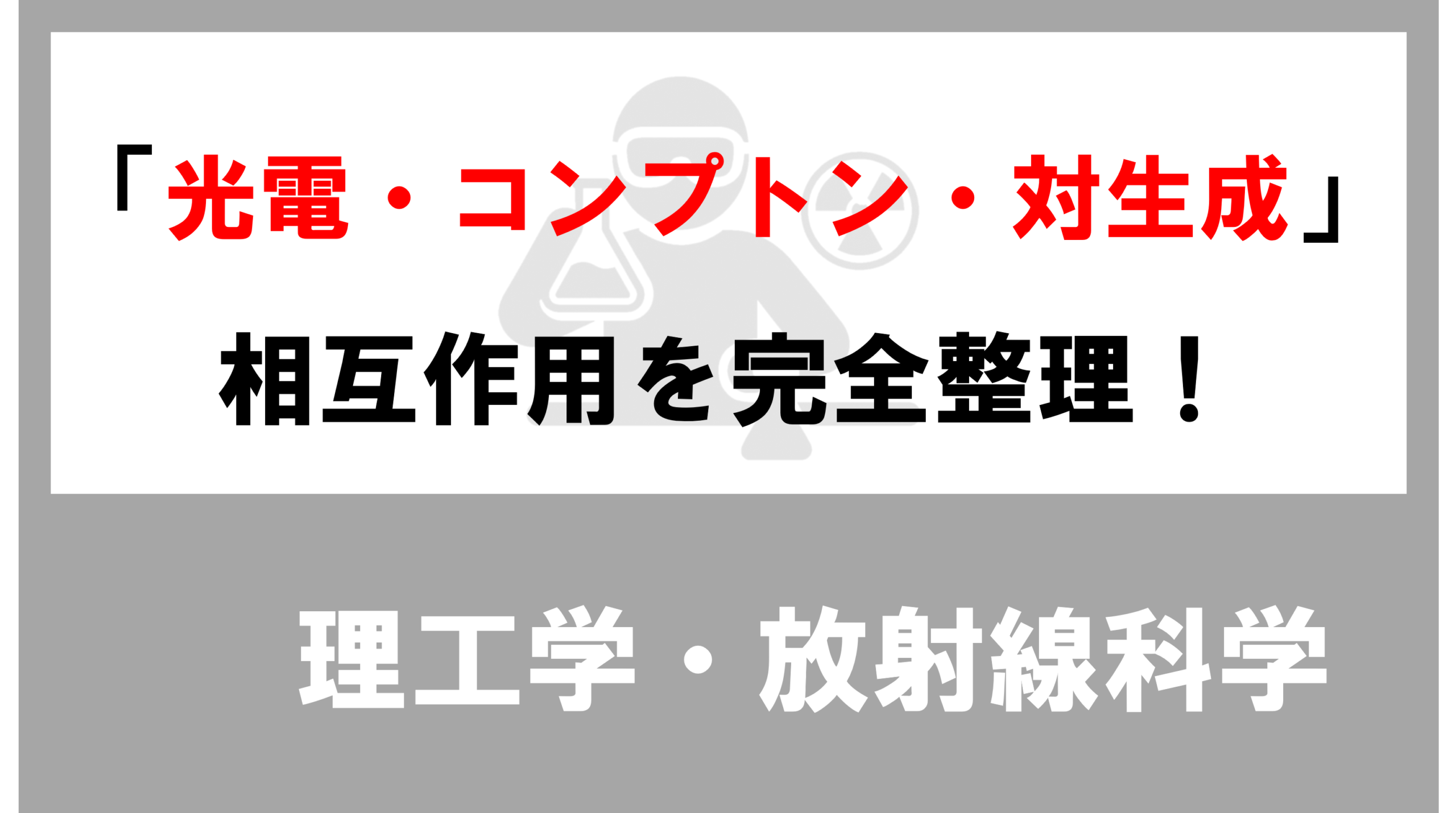

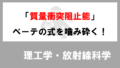
コメント