核磁気共鳴の緩和現象で正しいのはどれか。
- 縦緩和時間は磁場均一性に依存する。
- 縦緩和時間は物質の温度に依存する。
- 横緩和時間は縦緩和時間よりも長い。
- 横磁化は時間とともに直線的に減少する。
- 縦磁化は90度RFパルス印加中に増加する。
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
2.縦緩和時間は物質の温度に依存する。
解説
✔ MRIの緩和現象とは?:コマの動きでイメージしよう
MRIの緩和現象とは、RFパルスという電波のエネルギーをもらって励起した水素原子核(プロトン)が、元の安定した状態に戻っていく過程のことです。この戻り方には2種類あり、それぞれがMRI画像のコントラストを生み出します。
- 励起前:プロトンは、強力な磁石(静磁場)の向きに沿って整列し、全体として縦方向の磁化(縦磁化)を持っています。
- RFパルス印加:RFパルスを当てると、この縦磁化が真横に90度倒され、横方向の磁化(横磁化)に変わります。
- 緩和:RFパルスを切ると、倒された磁化が「起き上がりながら(縦緩和)」、「バラバラになっていく(横緩和)」という2つの現象が同時に起こります。
✔ T₁(縦緩和)とT₂(横緩和)の正体
- 縦緩和 (T₁) スピン-格子緩和
- 横に倒された磁化が、元の縦方向の状態に回復していく過程です。プロトンが周囲の分子(格子)にエネルギーを返すことで起こるため、「スピン-格子緩和」と呼ばれます。「起き上がる速さ」の指標です。
- 横緩和 (T₂) スピン-スピン緩和
- RFパルスで向きが揃えられたプロトンたちが、お互いの影響で足並みが乱れ(位相がずれ)、横方向の磁化が消えていく過程です。プロトン同士の相互作用で起こるため、「スピン-スピン緩和」と呼ばれます。「足並みが乱れる速さ」の指標です。
- 重要ルール
- 一般的に、足並みが乱れてバラバラになる方が、完全に起き上がるよりも速く終わります。
- そのため、常に T₂ ≦ T₁ の関係が成り立ちます。
✔ T₂*とは?:「見かけ上」の横緩和
ここで重要なのが、横緩和には2つの乱れの原因があるということです。
- プロトン同士の相互作用(これが「真のT₂」)
- 静磁場のわずかな「ムラ」(追加の乱れ要因)
MRI装置が実際に観測している信号は、この①と②が合わさった結果として、速くなった足並みの乱れを見ています。
この、磁場のムラの影響も全部コミコミで測定された、見かけ上の速い横緩和時間のことを「T₂*(ティーツースター)緩和時間」と呼びます。
T₂* = 「真のT₂」 + 「磁場のムラによる追加の乱れ」
この関係から、常に T₂* < T₂ ≦ T₁ となります。
✔ 各選択肢について
1. 縦緩和時間は磁場均一性に依存する。
- ❌ 誤り
- 磁場の不均一性が影響するのは、見かけ上の横緩和時間であるT₂*です。
- 縦緩和時間(T₁)は、周囲の分子運動(温度や粘性など)に依存します。
2.縦緩和時間は物質の温度に依存する。
- ✅ 正解
- 温度が変わると、分子の動きの速さが変わります。
- これにより、プロトンがエネルギーを周囲に返す効率が変わるため、T₁は温度に依存します。
3.横緩和時間は縦緩和時間よりも長い。
- ❌ 誤り
- 常に T₂ ≦ T₁ です。横緩和(足並みの乱れ)の方が、縦緩和(起き上がり)より速く進みます。
4.横磁化は時間とともに直線的に減少する。
- ❌ 誤り
- 縦緩和の回復も、横緩和の減衰も、どちらも指数関数的に変化します。
5.縦磁化は90度RFパルス印加中に増加する。
- ❌ 誤り
- 90度RFパルスは、縦磁化を横磁化に変換するのが仕事です。
- そのため、パルス印加によって縦磁化はゼロになります。
出題者の“声”

MRIの緩和現象は、物理のイメージが頭に描けておるかを試す格好のテーマじゃ。言葉の定義だけを覚えておる者と、スピンの動きを動画のように想像できる者とでは、雲泥の差がつく。
- 「90度パルス」とは何か? → 縦を横に倒すこと
- 「T₁緩和」とは何か? → 倒された磁化が起き上がること
- 「T₂緩和」とは何か? → 向きを揃えられた磁化がバラバラになること
この3つの動きをイメージできれば、各選択肢の正誤は自ずと見えてくるはずじゃ。
特に、「T₂はT₁より必ず短い」ことや、「磁場の不均一が影響するのはT₂*」といった基本中の基本は、絶対に落とせんぞ!
臨床の“目”で読む

T₁とT₂という物理現象は、我々が日常的に目にするMRI画像のコントラストそのものです。組織によってこの「起き上がる速さ(T₁) 」「足並みが乱れる速さ(T₂) 」が異なることを利用して、特定の組織を白く(高信号に)見せています。
- 脂肪はT₁が短く(起き上がりが速い)ため、T₁強調画像で白く見えます。
- 水はT₁もT₂も長く(起き上がりが遅く、足並みも乱れにくい)ため、T₂強調画像で白く見えます。病変の多くは水分量が増えるため、T₂強調画像は病気を見つけるのに非常に有用です。
さらに補足しておくと:
MRIの撮影法であるグラディエントエコー(GRE)法はT₂*信号を反映し、
スピンエコー(SE)法は180度パルスにより磁場のムラを打ち消し、真のT₂信号を取り出す技術です。
撮りたい組織や見つけたい病変に応じて、T₁とT₂のどちらを強調するかを考え、適切な撮影シーケンスを選択・実行しているのです。
今日のまとめ
- 緩和現象には、縦磁化が回復する縦緩和(T₁)と、横磁化が消失する横緩和(T₂)がある。
- 磁場の不均一性が加わった、見かけ上の横緩和時間をT₂*と呼び、常に T₂* < T₂ ≦ T₁ となる。
- T₁とT₂は温度などの分子的環境に依存し、磁場の不均一はT₂*に影響する。
- このT₁とT₂の組織による違いが、T₁強調画像とT₂強調画像のコントラストを生み出している。

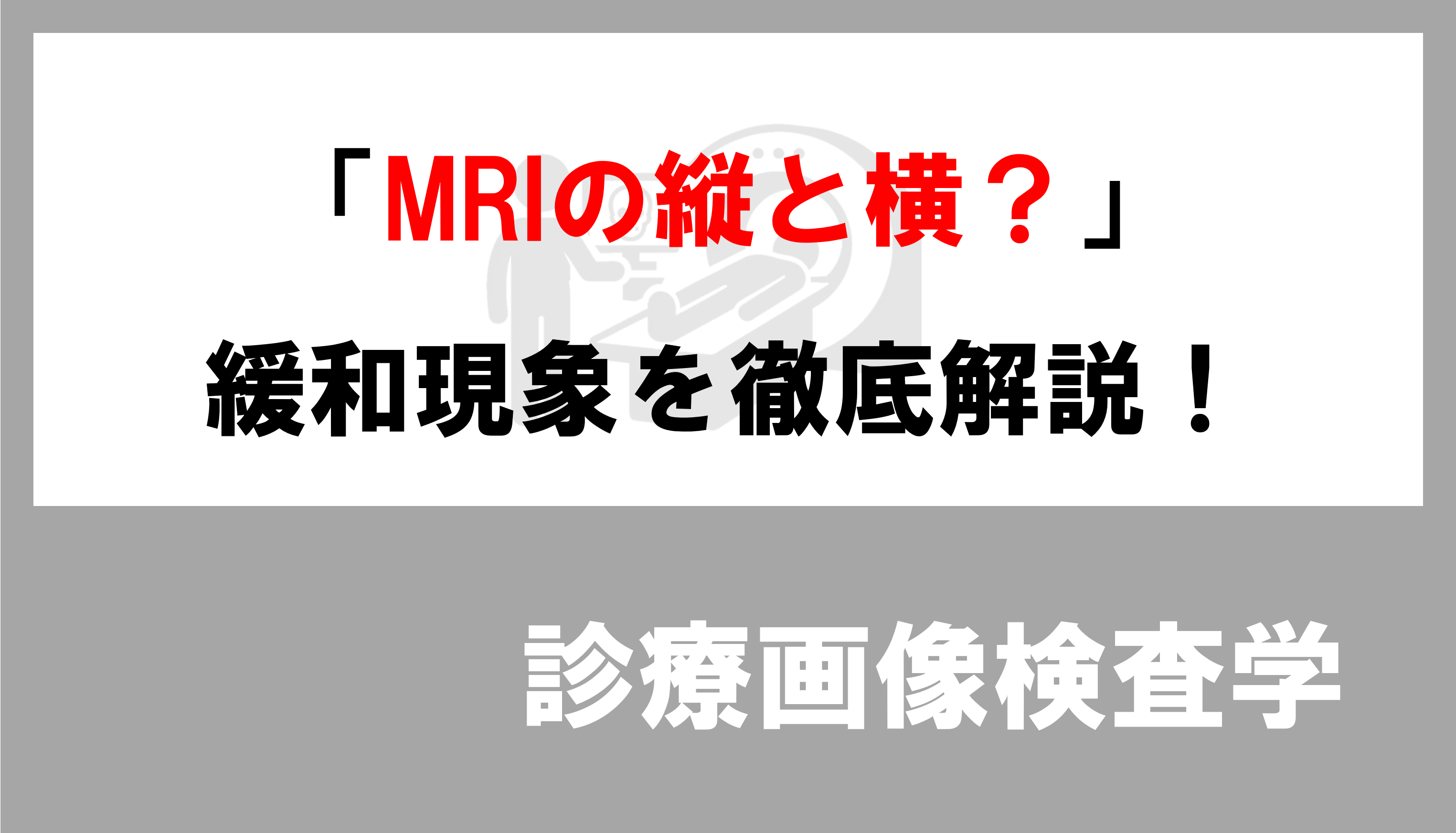

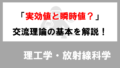
コメント