ガンマカメラで正しいのはどれか。2つ選べ。
- シンチレータが厚いほど空間分解能が高い。
- 位置計算には抵抗マトリクス方式が用いられる。
- NaI(Tl)シンチレータの厚さは2インチ程度である。
- エネルギー演算機構はZ信号加算回路と波高分析器からなる。
- 入射γ線エネルギーが高いほどシンチレータの光電吸収検出効率は高い。
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
2.位置計算には抵抗マトリクス方式が用いられる。
4.エネルギー演算機構はZ信号加算回路と波高分析器からなる。
解説
✔ ガンマカメラ:体内からの微弱な放射線を捉える超高感度カメラ 📸
ガンマカメラは、体内に投与した放射性医薬品から放出される微弱なガンマ(γ)線を検出し、その体内分布を画像化する装置です。γ線が検出器に到達してから、1枚の画像ができるまでのプロセスを理解することが重要です。
① シンチレータでの検出:厚さと性能のトレードオフ
体から飛んできたγ線は、まずNaI(Tl)シンチレータという結晶に当たり、そのエネルギーが微弱な光(シンチレーション光)に変換されます。このシンチレータの厚さは、画質を決定づける重要な要素です。
- 厚いシンチレータの場合
- 利点: ガンマ線が結晶を通り抜ける確率が減り、捕まえやすくなるため、検出効率は高くなります。
- 欠点: 結晶内で発生した光が、光電子増倍管に到達するまでの距離が長くなります。その間に光が大きく広がってしまうため、発生した正確な位置が分かりにくくなり、空間分解能は低くなります。
- 薄いシンチレータの場合
- 利点: 発生した光がすぐに光電子増倍管に到達し、光の広がりが少ないため、発生位置を正確に特定でき、空間分解能は高くなります。
- 欠点: ガンマ線が結晶を通り抜けてしまう確率が高くなり、検出できる数が減るため、検出効率は低くなります。
このように、シンチレータの厚さにおいて、検出効率と空間分解能はトレードオフの関係にあります。
② 信号処理:位置とエネルギーを見分ける
シンチレータで発生した光は、光電子増倍管(PMT)で電気信号に変換・増幅された後、2つの回路で処理されます。
- 位置演算回路
- 複数のPMTが受け取った光の強さのバランスから、「光がどこで発生したか」という位置(X,Y座標)を計算します。この計算に抵抗マトリクス方式が用いられます。
- エネルギー演算回路
- 全てのPMTからの信号を合計し(Z信号)、そのγ線が持っていたエネルギーの大きさを計算します。その後、波高分析器(PHA)で、散乱線などの不要なエネルギーを持つ信号を除去し、目的のγ線だけを選び出します。
✔ 各選択肢について
1. シンチレータが厚いほど空間分解能が高い。
- ❌ 誤り
- 上記の通り、シンチレータが厚いと光が結晶内で広がるため、空間分解能は低下します(検出効率は向上します)。
2.位置計算には抵抗マトリクス方式が用いられる。
- ✅ 正解
- PMT群からの信号の加重平均をとって発生位置を計算するために、抵抗マトリクスを用いた回路が一般的に使われます。
3.NaI(Tl)シンチレータの厚さは2インチ程度である。
- ❌ 誤り
- SPECTで一般的に用いられるNaI(Tl)結晶の厚さは3/8インチ(約9.5mm)が標準です。
- 2インチ(約5cm)もの厚い結晶は、より高エネルギーのγ線を扱うPET装置などで用いられます。
4.エネルギー演算機構はZ信号加算回路と波高分析器からなる。
- ✅ 正解
- 全PMTの信号を足し合わせたZ信号でエネルギーの大きさを求め、波高分析器でエネルギーの選別(ウィンドウ設定)を行います。
5.入射γ線エネルギーが高いほどシンチレータの光電吸収検出効率は高い。
- ❌ 誤り
- 光電吸収は、γ線のエネルギーが低いほど起こりやすい現象です。エネルギーが高くなるほどコンプトン散乱が優位になり、光電吸収の割合は低下します。
出題者の“声”

この問題は、ガンマカメラの画質を決める「物理特性」と「信号処理の基本原理」を、セットで正しく理解しておるかを試しておる。
学生がよく間違えるのは、1番と3番じゃな。
- 「厚い方がたくさん検出できるから、性能が良いに違いない」と思い込み、1番を選んでしまう。→ 効率と分解能のトレードオフを理解しておらん証拠じゃ。
- 「NaI(Tl)結晶」という言葉のイメージだけで、「分厚いもの」と勘違いし、3番の「2インチ」に飛びついてしまう。→ SPECTとPETでの結晶の厚みの違いを知らん証拠じゃ。
これらは、単なる丸暗記ではなく、なぜその厚さなのか、厚くするとどうなるのか、という原理から理解していないと、見事にひっかかってしまうぞ。
臨床の“目”で読む

ガンマカメラの基本原理の理解は、日々の品質管理(QC)やトラブルシューティング、そして画質の最適化に直結します。
ー装置特性の理解が画質を左右するー
- 分解能と感度のバランス
- 例えば、高エネルギーのガリウムシンチグラフィでは、分解能を少し犠牲にしても、感度の高い厚めのシンチレータや高エネルギー用コリメータを選択します。このトレードオフを理解していると、検査目的に応じた最適な画質設定の意図が分かります。
- エネルギーウィンドウ設定
- エネルギー演算の仕組みを理解していれば、散乱線の影響をどう除去するか、なぜウィンドウ設定が画質に重要なのかを、後輩や他職種に論理的に説明できます。
例えば、心筋シンチの画像が不鮮明なとき、単に「患者さんの動きのせい」と片付けるのではなく、「エネルギー設定がズレているのでは?」「検出器の感度補正が不十分かも?」といった、装置側に起因する可能性を疑えるか。その視点を持つことが、放射線技師には求められます。
今日のまとめ
- シンチレータの厚さと性能はトレードオフの関係。厚いほど効率↑・分解能↓、薄いほど効率↓・分解能↑。
- SPECT用NaI(Tl)シンチレータの標準的な厚さは3/8インチ(約1cm)。
- γ線の位置計算には、PMTからの信号を重み付けする抵抗マトリクス方式が用いられる。
- エネルギーの選別は、全PMTの信号を合計したZ信号を波高分析器で分析して行う。
- 光電吸収の効率は、γ線のエネルギーが低いほど高くなる。

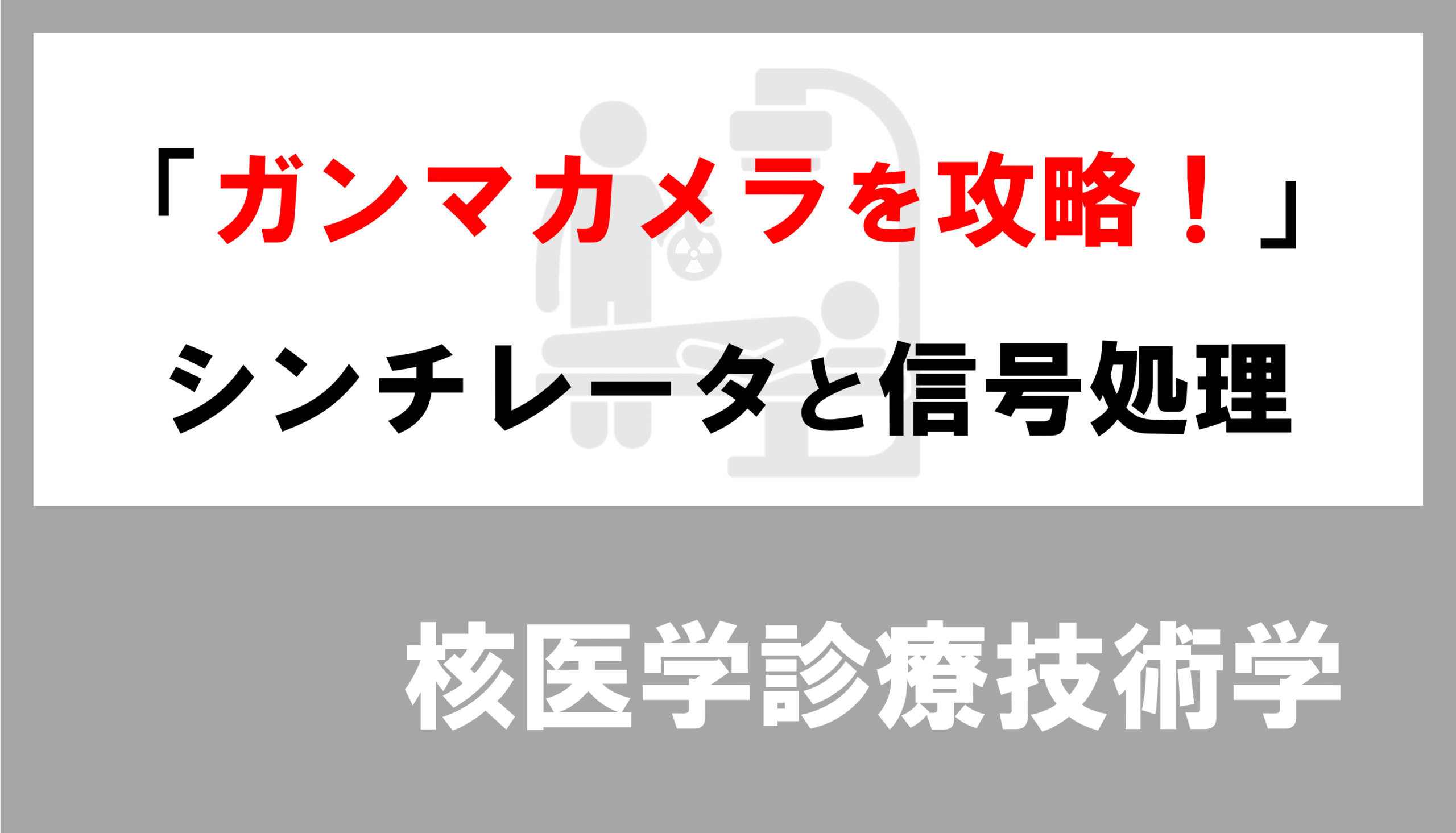

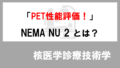
コメント