空間分解能補正を組み込んだPET画像再構成法で、集積部の辺縁を縁取ったような高集積を生じるアーチファクトはどれか。
- アップワードクリープ
- ギブスアーチファクト
- スターアーチファクト
- ストリークアーチファクト
- トランケーションアーチファクト
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
2.ギブスアーチファクト
解説
✔ ギブスアーチファクトとは?:画像再構成における物理的な限界
ギブスアーチファクトは、PETやMRIの画像再構成時に見られる特有の現象です。これは、画像データの処理過程における物理的な限界に起因します。
- シャープな境界と高周波成分
- PET画像において、腫瘍のように集積が急激に変化する部位(シャープな境界)は、画像信号として見ると、非常に高い周波数成分を多く含んでいます。
- 再構成における周波数の限界
- しかし、実際の画像再構成プロセスでは、扱える周波数の範囲に限界があります。そのため、元データに含まれる高すぎる周波数成分は、計算の過程で打ち切られ(トランケーション)てしまいます。
- 「リンギング」の発生
- このように周波数成分を急に打ち切って画像を再構成すると、その副作用として、元のシャープな境界部分で信号が波打つ「リンギング」という現象が発生します。
このリンギングが、画像上では、実際の腫瘍の縁を縁取るように、偽の高集積と偽の低集積として現れます。
これがギブスアーチファクトの正体です。
✔ 空間分解能補正との関係
特に、空間分解能補正(PSF補正など)は、画像のボケを補正して、よりシャープな境界を再現しようとする処理です。
この処理は高周波成分を強調するため、副作用であるギブスアーチファクトも、かえって目立ちやすくなることがあります。
✔ 各選択肢について
1. アップワードクリープ
- ❌ 誤り
- PET特有の現象ですが、これは撮像時間が長くなるにつれてバックグラウンド放射能が減少し、腫瘍の集積が見かけ上上昇していく現象です。
2.ギブスアーチファクト
- ✅ 正解
- 空間分解能補正などを伴う画像再構成時に、高集積の境界部分でリンギングが生じ、縁取り状の偽の高集積を形成します。
3.スターアーチファクト
- ❌ 誤り
- 主にCTで、金属インプラントなどによってX線データが欠損し、金属から放射状に伸びるスジとして現れるアーチファクトです。
4.ストリークアーチファクト
- ❌ 誤り
- これもCTにおける典型的なアーチファクト。高吸収体や動きによって生じる線状のアーチファクトです。
5.トランケーションアーチファクト
- ❌ 誤り
- 撮像範囲(FOV)から体の一部がはみ出してしまった際に生じるアーチファクト。
出題者の“声”

この問題の狙いは、「PETで見られる特有のアーチファクトを、CTなど他のモダリティと区別できるか」を確認することじゃ。
「ストリーク」や「スターアーチファクト」は、放射線画像の授業で耳にタコができるほど聞く言葉じゃから、つい反射的に選んでしまう。しかし、それらはCTの代表選手。
この問題のキーワードは「空間分解能補正を組み込んだPET」。この一文から、「画像をシャープにする処理」→「その副作用で起こるリンギング」→「ギブスアーチファクト!」と連想できるか。
そこが、単なる用語暗記と、原理を理解した知識との違いじゃ。
臨床の“目”で読む

ーなぜギブスアーチファクトを知る必要があるのか?ー
PET/CTの臨床現場でギブスアーチファクトが問題になるのは、腫瘍の評価を誤らせる可能性があるからです。
- SUV値の過大評価
- 腫瘍の縁にできた偽の高集積を拾ってしまい、SUVmax(最大集積値)を実際よりも高く測定してしまう危険があります。
- 治療効果判定の誤り
- 治療によって腫瘍は小さくなったのに、縁取りのアーチファクトが残っていると、「まだ活発な腫瘍が残っている」と誤って判断してしまう可能性があります。
ーPSF補正との関係ー
近年主流となっているPSF(点拡がり関数)補正を組み込んだ再構成法は、画像の分解能を劇的に向上させる一方で、このギブスアーチファクトを増強させることが知られています。
私たちは、新しい技術のメリットだけでなく、その副作用(アーチファクト)も正しく理解し、「これは真の集積か、アーチファクトか」を見極める読影眼を養う必要があるのです。
今日のまとめ
- PET画像で、集積の縁に現れる縁取り状の偽高集積がギブスアーチファクトである。
- 原因は、急峻な信号変化(境界)を有限のデータで表現しようとする際のリンギング(波うち)。
- 空間分解能補正(PSF補正など)を強くかけると、アーチファクトはより顕著になることがある。
- 臨床では、腫瘍の活動性の過大評価や治療効果判定の誤りに繋がるため、このアーチファクトの存在を常に意識する必要がある。

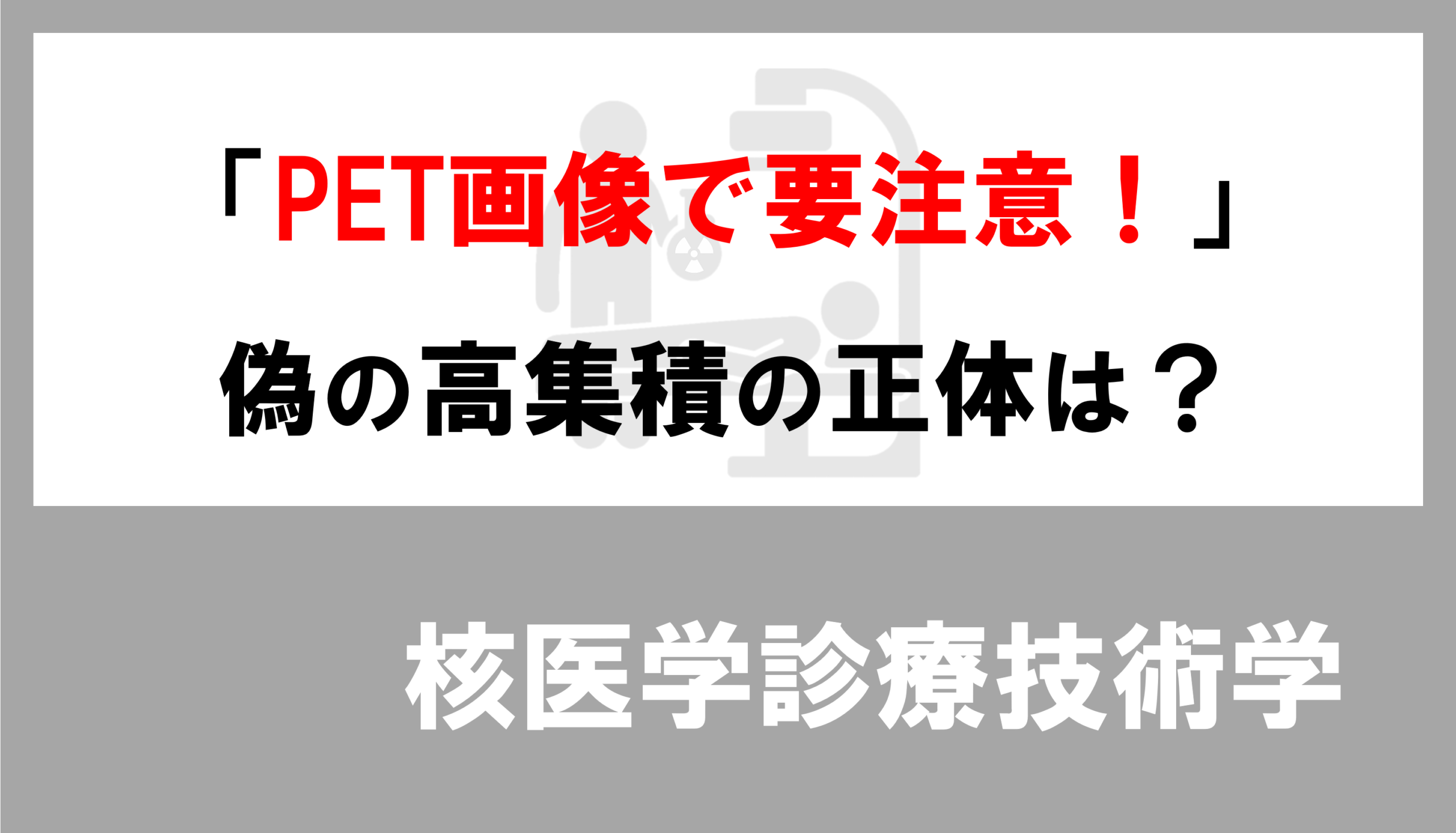
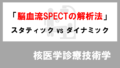

コメント