脳卒中が疑われる場合のMRIの撮影順で適切なのはどれか。
- MRA → 拡散強調像 → FLAIR像 → T₂強調像 → T₁強調像 → T₂*強調像
- T₁強調像 → T₂強調像 → FLAIR像 → T₂*強調像 → MRA → 拡散強調像
- T₁強調像 → T₂強調像 → T₂*強調像 → 拡散強調像 → MRA → FLAIR像
- 拡散強調像 → MRA → FLAIR像 →T₂*強調像 → T₂強調像 → T₁強調像
- 拡散強調像 → T₁強調像 → T₂*強調像 → FLAIR像 → T₂強調像 → MRA
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
4.拡散強調像 → MRA → FLAIR像 → T₂*強調像 → T₂強調像 → T₁強調像
解説
✔ 脳卒中MRIは“時間との勝負”
急性期脳卒中が疑われる場合のMRI撮影は、「Time is Brain(時は脳なり)」が合言葉です。
治療開始までの時間が患者さんの予後を大きく左右するため、撮影順は治療方針の決定に直結する情報から、最も効率的に得るように組まれています。
✔ なぜこの順番なのか?:治療への最短ルートを考える
脳卒中、特に脳梗塞の超急性期では、1分1秒でも早く診断し、治療(血栓溶解療法や血栓回収療法)を開始することが求められます。そのため、MRIの撮像シーケンスは、救命と後遺症の軽減という目的に沿って、以下のような優先順位で組み立てられています。
- 🥇 最優先:拡散強調像 (DWI)
- まず「急性期脳梗塞があるか、ないか?」を判定します。DWIは発症後わずか数分〜数時間で脳梗塞の領域を白く(高信号に)描出できる、最も感度の高い撮像法です。これを最初に撮ることで、脳梗塞の有無を即座に判断できます。
- 🥈 次点:MRA (MR Angiography)
- 次に「どの血管が詰まっているのか?」を評価します。脳の太い血管の閉塞や狭窄の場所を特定することで、血栓溶解療法(t-PA)や、カテーテルで血栓を回収する血管内治療の適応を迅速に判断できます。
- 🥉 時間評価:FLAIR像
- そして「発症から、どれくらい時間が経っているか?」を推定します。DWIで病変が白く見えても、FLAIRではまだ変化が現れていない(白くなっていない)場合、「DWI-FLAIRミスマッチ」と呼ばれ、発症から4.5時間以内の超急性期であることを強く示唆します。これは、t-PA療法の重要な適応基準であり、特に発症時刻が不明な患者さん(Wake-up strokeなど)にとっては、治療方針を決定づける極めて重要な情報となります。
- 📜 安全確認:T₂*強調像
- 最後に「脳内に出血はないか?」を確認します。T₂*強調像は、微小な出血を描出するのに優れています。血をサラサラにする血栓溶解療法の前には、出血がないことを確認するのが絶対条件であり、これは治療開始前の最終的な安全チェックです。
- 📋 詳細評価:T₂/T₁強調像
- 脳梗塞以外の疾患(脳腫瘍など)との鑑別のために、最後に撮像します。
この流れにより、「梗塞の有無 → 原因血管 → 発症時間 → 安全確認」という、治療方針決定に不可欠な情報を、最も効率よく得ることができるのです。
出題者の“声”

この問題は、「急性期脳卒中MRIの優先順位」を、その臨床的な意味まで含めて理解しておるかを試しておる。単にシーケンス名を暗記するのではなく、医師が次に何を知りたいかを考えねばならん。
脳梗塞では、発症からの時間が勝負じゃ。 「DWIで梗塞を見つけ、MRAで血管を特定し、FLAIRで時間を見積もる」 この3点セットが、治療法を決めるための最重要情報じゃ。
特に「DWI-FLAIRミスマッチ」は、t-PAという強力な武器を使えるかどうかを判断する鍵となる。 その上で、最後にT₂*で出血がないかを最終確認し、安全に治療へと進む。
この、臨床の思考の流れそのものが、撮像順に反映されておるのじゃ。
臨床の“目”で読む

急性期脳卒中のMRI検査は、救急外来や当直業務で放射線技師が対応する、最も緊急性の高い検査の一つです。「脳卒中疑い」のオーダーを受けたら、私たちの頭の中では、以下のような思考が瞬時に駆け巡ります。
ー救急現場での思考プロセスー
- まずDWIを撮る!
- 医師が患者さんを診察している間に、脳梗塞の有無という最も重要な情報を得る。
- 続けてMRA!
- 医師がDWIの画像を確認している間に、閉塞血管の情報を追加する。
- 次にFLAIR!
- DWIとの比較で「DWI-FLAIRミスマッチ」の有無を確認。これにより、t-PAの適応時間が判断できる。
- 最後にT₂*で安全確認!
- 血栓溶解療法を行う前に、禁忌となる出血がないか、最終チェックを行う。
ここまでの一連の画像を最短時間で提供することが、患者さんの予後を大きく左右します。限られた時間の中で、最大限の診断的価値を持つ画像をいかに提供するか。そこが、放射線技師の腕の見せ所です。
今日のまとめ
- 急性期脳卒中MRIは「Time is Brain ⏱️」が鉄則。治療方針に直結する情報を最優先で撮像する。
- 撮像順の基本は ①DWI(梗塞の有無) → ②MRA(原因血管) → ③FLAIR(発症時間) → ④T₂(安全確認)
- DWI-FLAIRミスマッチは、発症4.5時間以内の超急性期を示唆し、t-PA療法の適応判断に極めて重要である。
- T₂*強調像は、治療開始前の最終的な出血の有無の確認に不可欠である。

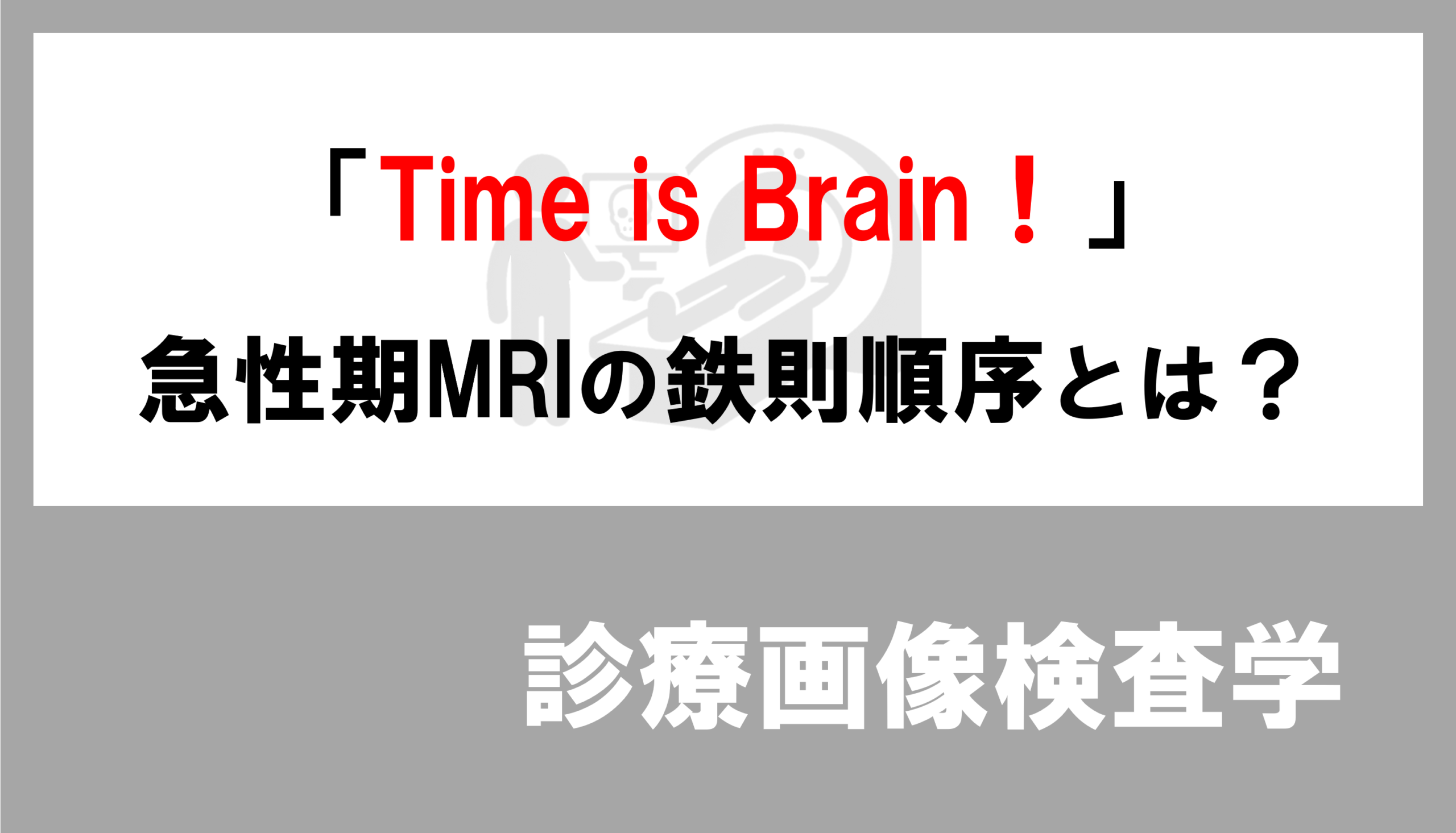
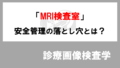
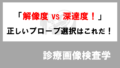
コメント