画像誘導放射線治療として照射位置の照合基準で用いるのはどれか。2つ選べ。
- 血管
- 骨構造
- 体表面
- 体内のガス
- 体内に貯留している液体
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
2.骨構造
3.体表面
解説
✔ IGRTにおける「照合基準」の3原則 🎯
画像誘導放射線治療(IGRT)とは、毎回の照射直前に患者さんの体内の様子を画像で確認し、治療計画時からの位置のズレを補正する技術です。 その際、位置を合わせるための“ものさし”となるのが「照合基準(ランドマーク)」です。良い照合基準には、以下の3つの条件が求められます。
- 視認性が高い: X線やCBCTなどの画像で、はっきりと見えること。
- 再現性が高い: 毎回の治療で、形や大きさがほとんど変わらないこと。
- 位置が安定している: 体内で位置が動きにくいこと。
この問題は、選択肢の中から、この3つの条件を満たすものを正しく選べるかを問うています。
✔ 各選択肢について
1. 血管
- ❌ 誤り
- 造影剤なしでは視認性が低く、拍動や血圧で太さも変わるため、安定性・再現性に欠け、基準には不向きです。
2.骨構造
- ✅ 正解
- X線画像やCBCTで視認性が非常に高く、形も位置も安定・再現しているため、IGRTにおける最も基本的で信頼性の高い照合基準です。
3.体表面
- ✅ 正解
- レーザーや3Dカメラで視認でき、適切な固定具を用いれば再現性も高いです。特に、SGRT(体表面誘導放射線治療)では、体表面そのものを高精度な照合基準としてリアルタイムで用います。
4.体内のガス
- ❌ 誤り
- 腸管内ガスなどは、日によって量も形も位置も大きく変動するため、安定性・再現性が全くなく、基準にはなりません。
5.体内に貯留している液体
- ❌ 誤り
- 膀胱内の尿や胃の内容物なども、量が常に変動するため、安定性・再現性がなく、基準には不向きです。
出題者の“声”

この問題の狙いは、「視認性・再現性・安定性」という、照合基準の三原則を正しく理解しておるか、ただ一点じゃ。 この三原則というフィルターを通して選択肢を見れば、答えは自ずと見えてくる。
ガスや体液は、日ごとに姿を変えるから「安定性」「再現性」でアウト。血管は、造影なしでは「視認性」でアウト。結局、何があっても動じない「骨」と、治療の開始点となる「体表面」が、最も信頼できる基準として残る。
この基本を土台として、さらに精度を高めるために、症例に応じて金マーカーや軟部組織での照合へと応用できるか。そこまで考えが及べば、臨床でも通用する知識となる。
臨床の“目”で読む

IGRTにおける位置照合の標準的なワークフロー
臨床現場での高精度な位置照合は、複数の基準を段階的に用いて行われます。
- 体表面での初期設定
- まず、患者さんの体に記されたマークと室内のレーザーを合わせ、大まかな位置を決めます。SGRTを用いる場合は、この段階で3Dカメラで体表面全体を照合します。
- 骨構造での基本照合
- 次に、kV-X線画像やCBCTを撮影し、治療計画CTから作成したDRR(デジタル再構成画像)と骨の形を一致させ、ミリ単位での精密な補正を行います。
- 標的/マーカーでの精密照合 (必要な場合)
- 前立腺がんにおける金マーカーや、肺がんの定位放射線治療における腫瘍そのものなど、骨とは動きが異なる標的に対しては、最後に標的自身を基準に最終的な微調整を行います。
このように、「体表面 → 骨 → 標的」という階層的な照合を行うことで、迅速かつ高精度な位置合わせを実現しているのです。
今日のまとめ
- IGRTにおける照合基準の3原則は、①視認性、②再現性、③安定性である。
- この3原則を満たす最も基本的な照合基準が、骨構造と体表面である。
- 血管、ガス、体液は、日々の変動が大きいため、照合基準には不向きである。
- 臨床では、「体表面 → 骨 → 標的/マーカー」と、複数の基準を段階的に用いて精度を高めている。

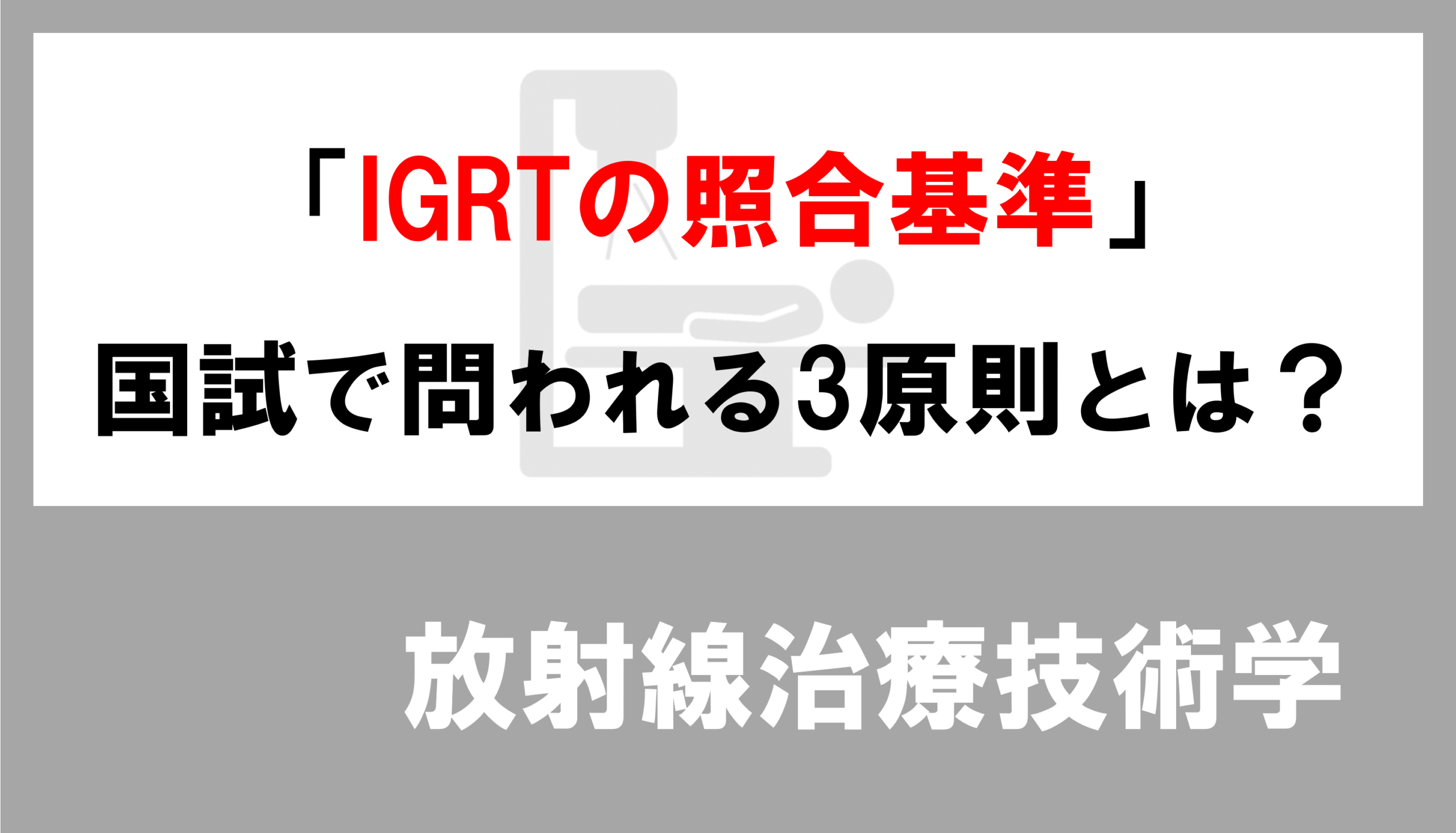


コメント