放射線治療に用いられるX線計測で正しいのはどれか。
- PDDはSSDに依存しない。
- 最大線量深は照射野に依存する。
- kQはエネルギーの大きさに比例する。
- TPR20,10の測定は電離箱線量計の実効中心で行われる。
- TMRの測定は電離箱線量計の幾何学的中心で行われる。
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
2.最大線量深は照射野に依存する。
解説
✔ 治療用X線の線量測定:基本用語と測定のルール 📏
放射線治療で用いられるX線の線量分布を正確に把握するためには、いくつかの重要な物理量と、その測定ルールを理解する必要があります。
- PDD (百分深部率) と TMR/TPR (組織最大線量比/組織ファントム線量比)
- これらは、水中での深さと共に線量がどう変化するかを示す指標です。
- PDD
- 線源-表面間距離(SSD)が一定の条件で測定します。そのため、測定深度が深くなると線源との距離も離れるため、距離の逆二乗則の影響を受けます。つまり、PDDはSSDに依存します。
- TMR/TPR
- 線源-軸間距離(SAD)が一定の条件で測定します。線源と測定点の距離が変わらないため、距離の逆二乗則の影響を受けにくく、より純粋な媒質による減衰を示します。
- dmax (最大線量深)
- X線ビームが入射した後、二次電子のビルドアップにより線量が最大となる深さのことです。 dmaxは、主にビームのエネルギーによって決まりますが、それ以外にも照射野の大きさや、ビーム経路上にウェッジなどの線量修飾具が存在することによっても、散乱線の寄与が変化するため、わずかに変動します。
✔ 測定点:幾何学的中心 vs 実効中心 🎯
電離箱線量計で線量を測定する際、線量計の「どこ」を基準点とするかは、測定の目的によって異なります。
- TPR₂₀, ₁₀ (ビーム品質の指標) の測定
- これは、ビームの硬さ(透過能)を示す「品質指標」を決定するための、特定の深さ(10cmと20cm)での点測定です。この場合、線量勾配の影響を考慮する必要はなく、電離箱の幾何学的中心を規定の深さに設定して測定します。
- TMR/PDD (深部線量分布) の測定
- こちらは、深さと共に線量が連続的に変化する「線量分布」を、線量計をスキャンさせながら測定します。線量が急激に変化する領域(線量勾配が急な領域)では、線量計自体の体積が測定値に影響を与えます。この影響を補正するため、線量計の実効中心(EPOM: Effective Point of Measurement)を基準点として用います。
✔ 各選択肢について
1. PDDはSSDに依存しない。
- ❌ 誤り
- PDDはSSDに依存し、SSDが大きくなるほどPDDの値は増加します。
2.最大線量深は照射野に依存する。
- ✅ 正解
- dmaxは主にエネルギーで決まりますが、照射野の大きさによって散乱線の寄与が変化するため、dmaxもわずかに変動します
3.kQはエネルギーの大きさに比例する。
- ❌ 誤り
- kQは、ビームの品質指標(TPR₂₀,₁₀など)に基づいて決定される水吸収線量校正係数であり、ビームのエネルギー値そのものに単純比例するわけではありません。
4.TPR20,10の測定は電離箱線量計の実効中心で行われる。
- ❌ 誤り
- TPR20,10はSAD=100 cm、10×10 cm²で、電離箱の幾何学的中心(リファレンスポイント)を深さ10 cm/20 cmに置いて測定する扱いが一般的。実効点(EPOM)シフトは用いない。
5.TMRの測定は電離箱線量計の幾何学的中心で行われる。
- ❌ 誤り
- TMRのような線量分布測定では、線量勾配の影響を補正するため、実効中心(EPOM)を基準点とします。
出題者の“声”

この問題は、「どの物理量が、何に依存するか」そして「どの測定で、どの基準点を用いるか」という、線量測定の基本ルールを正確に理解しておるかを問うておる。
最大のワナは、4番と5番の「入れ替え問題」じゃ。
- TPR₂₀,₁₀ → 幾何学的中心 (ビーム品質を決めるための点測定だから)
- TMR/PDD → 実効中心 (線量分布を正確に測るためのスキャン測定だから)
この対応関係を、その理由まで含めて理解していないと、見事にひっかかってしまう。用語の表面的な暗記だけでは通用しない、物理の本質を問う問題じゃ。
臨床の“目”で読む

ー精度管理(QA)における重要性ー
これらの物理測定は、放射線治療の精度と安全性を根幹から支える、極めて重要な品質管理(QA)業務です。
- 実効点補正
- PDDやプロファイルといった線量分布を測定する際の基本操作です。この補正を怠ると、特に線量勾配が急な半影領域などで、TPSとの間に系統的な誤差が生じ、治療計画の検証が不正確になります。
- dmaxの変化
- 照射野や付属物の有無によってdmaxがわずかに変化することは、特に皮膚線量や、ビルドアップ領域にある腫瘍への線量に影響を与えます。治療計画装置(TPS)の計算と、実測値が一致しているかを確認することは重要です。
- TPR₂₀,₁₀の正確な測定
- この値は、線量計の校正係数kQを決定する基礎となります。測定条件(SAD、照射野、深さ、基準点)を一つでも間違えると、その後の全ての線量測定が不正確になり、患者さんへの投与線量に重大な誤差を生じさせる危険があります。
今日のまとめ
- PDDはSSD・照射野・エネルギーに依存する。TMR/TPRはSAD基準のためSSDには依存しない。
- dmaxは主にエネルギーで決まるが、照射野や付属物によっても変化する。
- ビーム品質指標 TPR₂₀,₁₀ の測定では幾何学的中心を基準点とする。
- 線量分布測定 TMR/PDD の測定では実効中心(EPOM)を基準点とする。

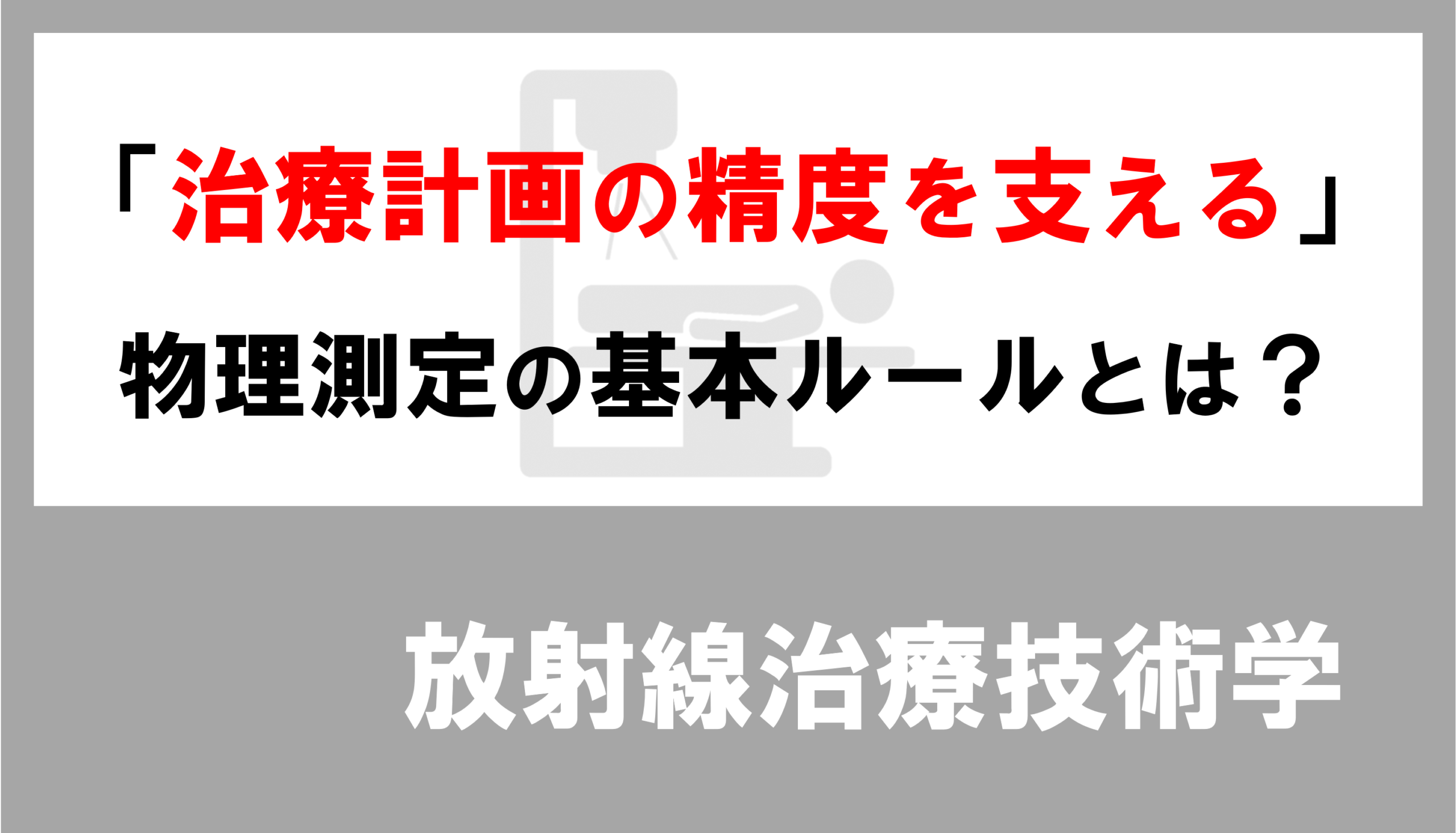
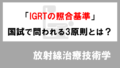
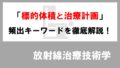
コメント