成人の超音波検査で最も高い周波数のプローブを用いるのが適切なのはどれか。
- 門脈
- 脾静脈
- 総頚動脈
- 上行大動脈
- 腹部大動脈
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
3.総頚動脈
解説
✔ 超音波の基本原則:周波数と「見える深さ・細かさ」の関係
超音波検査で使うプローブの周波数を決めることは、懐中電灯の光の絞り方を選ぶことに似ています。
- 高周波プローブ 🔬 (スポットライト)
- 光を一点に強く絞るイメージです。解像度が非常に高く、近くの物を細部まで鮮明に映し出せますが、光は遠くまで届きません。浅い場所を、詳しく見たいときに使います。
- 低周波プローブ 🔭 (広角ライト)
- 光を広くぼんやりと照らすイメージです。遠くまで光が届き(深達度が高い)、広い範囲を見渡せますが、一つひとつの物の輪郭は不鮮明(解像度が低い)になります。深い場所を、広く見たいときに使います。
したがって、この問題は「最も高い周波数のプローブは?」と問うことで、「選択肢の中で、最も体の表面(皮膚)に近い血管はどれか?」を尋ねているのと同じです。
✔ 各選択肢について
1. 門脈 / 2.脾静脈 / 5.腹部大動脈
- ❌ 誤り
- これらはすべて腹部の深い位置にある血管です。
- 深部まで超音波を到達させる必要があるため、低〜中周波数(2〜5MHz程度)のコンベックスプローブが用いられます。
3.総頚動脈
- ✅ 正解
- 総頚動脈は、首の表面近くにある血管です。
- 動脈硬化の指標となる内膜の肥厚やプラークなど、微細な構造を観察する必要があるため、解像度に優れた高周波数(7〜12MHz程度)のリニアプローブが最適です。
4.上行大動脈
- ❌ 誤り
- 心臓から出てすぐの、胸の奥深くにある血管です。
- 肋骨の間から心臓を描出するのと同様に、低周波数(2〜4MHz程度)のセクタプローブが用いられます。
出題者の“声”

この問題は、超音波の「周波数選択の鉄則」を、解剖学的な知識と結びつけて理解しておるかを試しておる。
「一番周波数が高い=一番皮膚から浅い臓器は?」と読み替えられた者にとっては、サービス問題じゃったじゃろう?
学生は「高周波=きれいに見える」というイメージだけで覚えてしまいがちじゃが、それは「浅い場所なら」という条件付き。深部では、そもそも超音波が届かんから話にならん。
「どこを」「何のために」見るのか? 総頚動脈は「浅い場所」を「細かく見る」必要があるから、高周波の出番。この、目的と手段を正しく結びつける思考が、臨床では不可欠なのじゃ。
臨床の“目”で読む

超音波検査において、プローブと周波数の選択は、検査の質を左右する最も重要なステップです。
- 頚動脈エコー
- 高周波のリニアプローブを用いることで、血管壁の内膜中膜複合体厚(IMT)を0.1mm単位で計測したり、動脈硬化プラークの性状(柔らかいか、硬いか)を評価したりと、極めて詳細な観察が可能です。
- 腹部・心臓エコー
- 腹部大動脈瘤や門脈の血流評価、心臓の動きの評価では、まず低周波のコンベックスプローブやセクタプローブで全体像と血流を把握します。深部まで見通すことが最優先されます。
- 患者に合わせた調整
- もちろん、患者さんの体型も考慮します。例えば、痩せ型の方の腹部検査では、通常より少し高めの周波数を使うことで、解像度を向上させられる場合があります。検査前に対象臓器の深さをイメージし、最適なプローブと周波数を瞬時に選択・調整する能力は、超音波検査技師の腕の見せ所です。
今日のまとめ
- 超音波の基本原則は「高周波=高分解能で浅部向き 🔬」「低周波=低分解能で深部向き 🔭」。
- 総頚動脈は体の表面近くにあり、かつ高分解能が求められるため、高周波プローブが用いられる。
- 門脈や腹部大動脈といった腹腔内の深い血管には、低周波プローブが用いられる。
- 最適な周波数選択は、対象臓器の「深さ」と、診断の「目的(求める解像度)」のバランスで決まる。

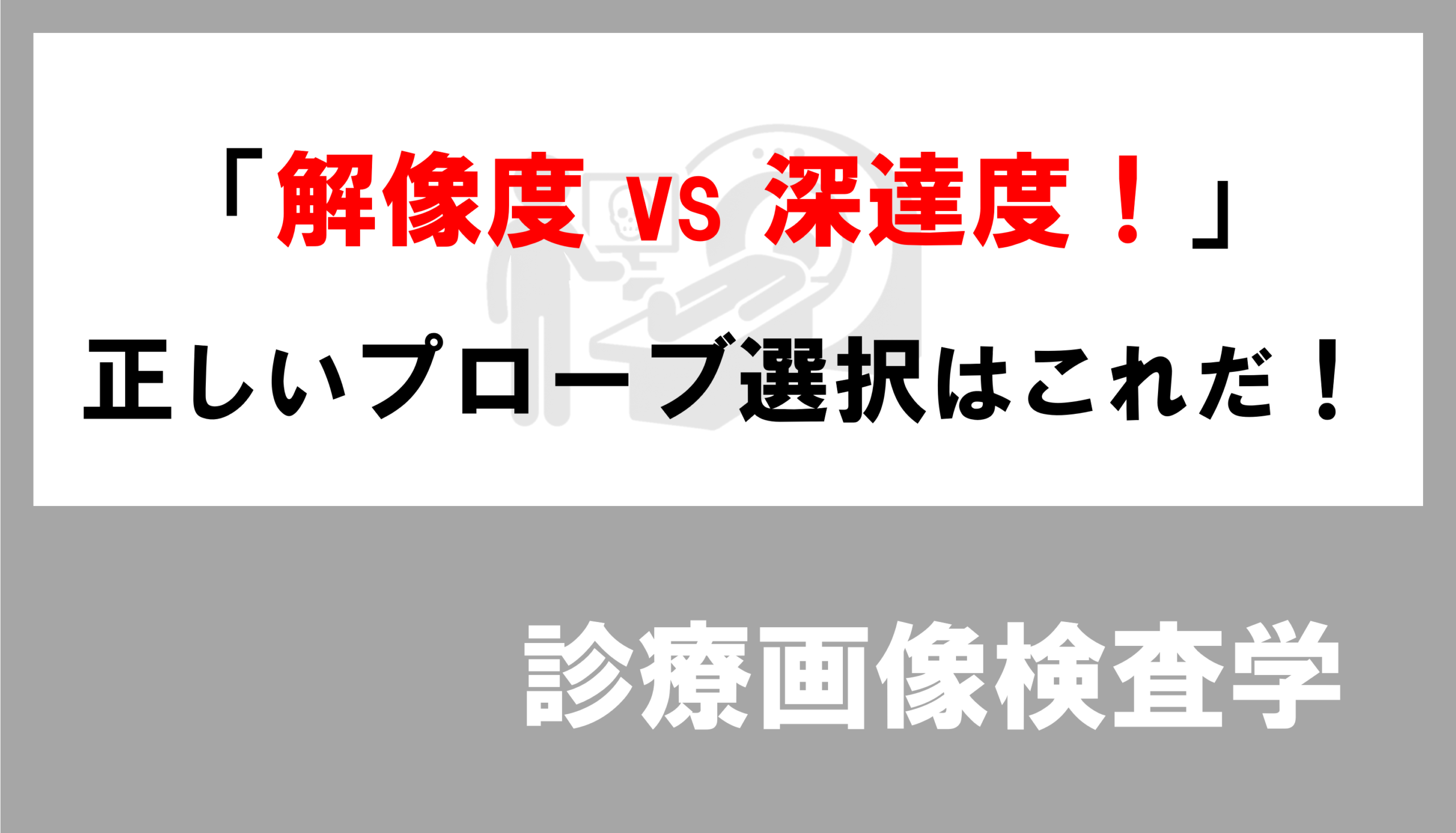
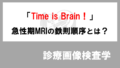

コメント