診療情報の2次利用にあたるのはどれか。
- 患者家族への説明
- 患者本人への診療
- 院内勉強会での利用
- 医療従事者間の情報共有
- 紹介医療機関への情報提供
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
3.院内勉強会での利用
解説
✔ 「一次利用」と「二次利用」の決定的な違い
診療情報の利用は、その「目的」によって「一次利用」と「二次利用」に明確に区別されます。
- 一次利用 👤
- その患者さん自身の診療に直接関わる目的での利用。 (例: 診断、治療、看護、他の医療機関との連携など)
- 二次利用 📚
- その患者さん自身の診療から離れた目的での利用。 (例: 教育、研究、統計、病院経営改善など)
この問題を解く鍵は、「その情報の利用目的が、目の前の患者さんの治療に直結しているか?」という視点で各選択肢を判断することです。
✔ 各選択肢について
1. 患者家族への説明
- ❌ 誤り
- 患者さんの治療方針を決定し、同意を得るための医療行為の一環です。
2.患者本人への診療
- ❌ 誤り
- 診療情報の利用目的として、最も基本的なものです。
3.院内勉強会での利用
- ✅ 正解
- 目的が個別の患者さんの診療ではなく、スタッフの教育であるため、二次利用に該当します。実施には、個人が特定できないよう匿名化するなどの適切な処理が必須です。
4.医療従事者間の情報共有
- ❌ 誤り
- 同じ患者さんの治療を担当するチーム内で、診療方針を共有し連携するための利用です。
5.紹介医療機関への情報提供
- ❌ 誤り
- 治療の継続や、より専門的な医療へ繋ぐための、医療機関同士の連携にあたります。
出題者の“声”

この問題の狙いは、診療情報利用の許可範囲を、「場所」や「関係者」ではなく、「目的」で判断するという、最も重要な原則が身についておるかを試すことじゃ。
ワシは、最大のワナとして5番と3番を並べておいた。 5番の「他院への情報提供」を見て、「院外に情報を持ち出すのだから二次利用だろう」と早合点した者はおらんか?しかし、その目的はあくまで「治療の継続」。患者さん自身の診療に直結しておる。CT画像を共有すれば、転院先での再撮影や余計な被ばくを防げるのじゃから、これは紛れもなく一次利用じゃ。
逆に、3番の「院内勉強会」を見て、「院内だから一次利用だろう」と考えた者。これもワナじゃ。目的はあくまで「教育」。その患者さん自身の治療からは離れておる。だから二次利用なのじゃ。
この「院外でも一次利用」と「院内でも二次利用」の区別が曖昧だと、臨床現場で個人情報保護に関する思わぬトラブルを引き起こしかねん。医療人としての基本のキを問うておるのじゃよ。
臨床の“目”で読む

私たち放射線技師も、学会発表や院内勉強会、卒業研究などで、日常的に診療情報を二次利用する機会があります。その際は、個人情報保護と倫理的配慮を徹底しなければなりません。
ー二次利用を行う際のチェックリストー
- ① 目的の確認
- 目の前の患者さんのため(一次)か、教育・研究のため(二次)かを明確にする。
- ② 手続きの確認
- 院内のルール(個人情報保護規程など)を確認する。研究目的であれば、倫理審査委員会の承認が必須。
- ③ 匿名化の徹底
- 患者氏名、ID、生年月日などの個人情報を完全に削除する。特にDICOM画像では、ヘッダ情報だけでなく、画像に焼き付けられた「burned-in annotation」も見落とさずに消去することが重要。
- ④ 情報の最小化
- 発表や研究に必要な、最小限の情報(画像枚数、項目など)だけを利用する。
- ⑤ セキュリティの遵守
- 私物のUSBメモリは使わない、データを暗号化するなど、所属施設のセキュリティポリシーを厳守する。
これらの手順を遵守することが、医療情報を扱う専門職としての信頼を守ることに繋がります。
今日のまとめ
- 診療情報の利用は「目的」で判断する。患者自身の診療なら一次利用、教育・研究などそれ以外なら二次利用。
- 本問の正解は、教育目的である「院内勉強会での利用」。
- 「院内だから一次利用」という考えは誤り。
- 二次利用を行う際は、院内規程の確認・適切な匿名化・情報セキュリティの遵守が絶対条件である。

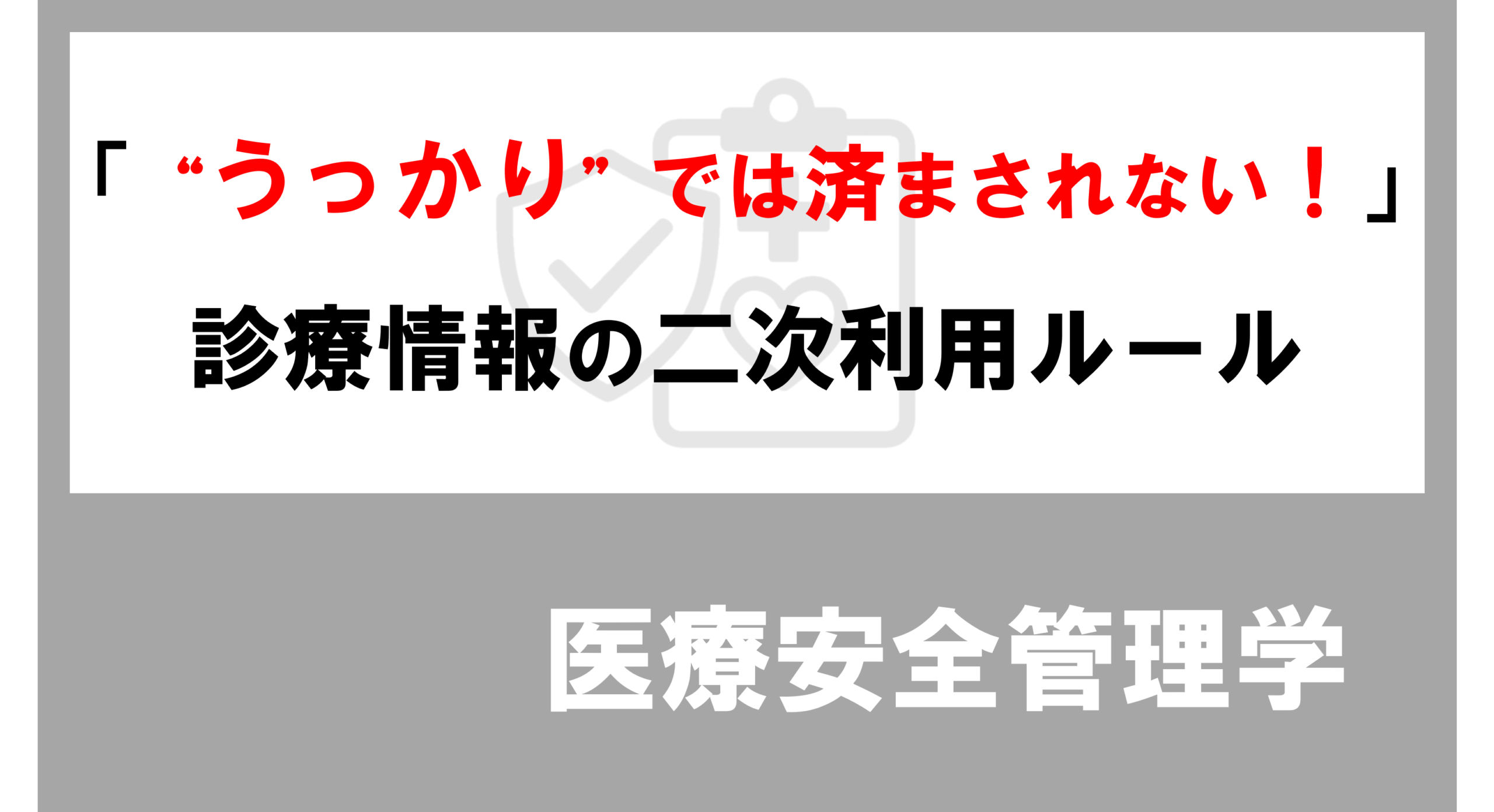
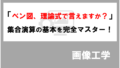

コメント