造影CT施行後に一過性の血圧低下があった。
次にこの患者の造影CT施行が必要になった場合に備えて共有すべき今回のCTの情報はどれか。
- 体重
- 管電圧
- 投与した造影剤の総量
- 投与した造影剤の製品名
- 推算糸球体濾過量(eGFR)
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
4.投与した造影剤の製品名
解説
✔ なぜ造影検査でアレルギー反応が起きるのか?
CT検査で用いられるヨード造影剤は、ごくまれにアレルギーのような副作用(副反応)を引き起こすことがあります。症状は、軽度のじんましんやかゆみから、重篤な場合は血圧低下や呼吸困難といったショック状態に至ることもあります。
このような副反応が一度起きた場合、次回以降の検査を安全に行うために、「何が原因で反応が起きたのか」という情報を正確に記録し、院内で共有することが絶対条件となります。
✔ なぜ「製品名」の共有が最も重要なのか?
副作用の原因は、造影剤の主成分であるヨウ素そのものだけでなく、薬剤に含まれる添加物や、分子構造のわずかな違いである可能性があります。 同じ「ヨード造影剤」というカテゴリーでも、製薬会社や製品(商品名)によって、これらの成分は異なります。
そのため、ある製品で副作用を起こした患者さんでも、別のメーカーや別の製品名の造影剤であれば、安全に使用できる場合があります。逆に、原因となった製品を再度使用してしまうと、症状が再発したり、さらに重症化したりするリスクが非常に高くなります。 したがって、「どの会社の、どの製品名の造影剤を使用して、どのような反応が出たのか」を記録・共有することが、将来の安全対策において最も重要な情報となるのです。
✔ 各選択肢について
1. 体重
- ❌ 誤り
- 体重は、投与する造影剤の量を決定するためには必要ですが、アレルギー様副反応の原因特定や対策とは直接関係ありません。
2.管電圧
- ❌ 誤り
- CTの撮影条件であり、副反応とは無関係です。
3.投与した造影剤の総量
- ❌ 誤り
- もちろん量も記録すべき項目ですが、アレルギー様反応は微量でも発生することがあります。原因となった「物質」を特定することの方が、「量」を記録するよりも優先度が高いです。
4.投与した造影剤の製品名
- ✅ 正解
- 副作用の再発防止や、次回使用する代替薬剤を選定するために、最も重要な情報です。電子カルテの「アレルギー情報」欄などに必ず記載します。
5.推算糸球体濾過量(eGFR)
- ❌ 誤り
- これは腎機能の指標であり、造影剤による腎障害(造影剤腎症)のリスクを評価するために重要です。しかし、今回のような血圧低下といった急性の副反応とは、発生メカニズムが異なります。
出題者の“声”

この問題の狙いは、「造影剤の副反応が起きたとき、医療従事者として、次に何をすべきか」という、臨床現場での思考プロセスを理解しておるかを試すことじゃ。
多くの学生が「総量」や「腎機能」といった、造影検査でよく聞くキーワードに飛びつきがちじゃ。しかし、アレルギー様反応で最も重要なのは「原因物質の特定」。つまり「どの製品か」が全ての始まりなのじゃ。
造影剤には、イオヘキソール(製品名: オムニパーク®)やイオメプロール(製品名: イオメロン®)など、多くの種類がある。現場では、副作用歴のある患者さんに対して「前回はオムニパークで反応が出たから、今回はイオメロンを使い、前投薬も準備しよう」というように、製品名ベースで安全対策を立てる。
この基本を知らぬまま、漫然と同じ造影剤を再使用すれば、患者さんを命の危険に晒すことになりかねん。まさに「記録と共有」が患者安全の要であることを、肝に銘じておくべきじゃ。
臨床の“目”で読む

ー放射線技師が行うべき安全管理と記録ー
造影検査中に副作用が発生した場合、私たち放射線技師は、救急対応の補助と並行して、以下の記録と情報共有を確実に行う責任があります。
ステロイド剤などの前投薬を行ってから、慎重に造影検査を行う といった対策を検討します。
- ① 副反応時の即時対応と観察
- 症状(発疹、嘔吐、血圧低下など)の程度を客観的に評価し、速やかに医師・看護師へ報告。チームで救急対応にあたります。
- ② 正確な記録(電子カルテ・部門システム
- 使用した造影剤の製品名、投与量、投与ルート、副作用の発生時刻、具体的な症状、バイタルサインの変化、実施した処置の内容(薬剤投与、酸素投与など)
- ③ 次回検査への確実な引き継ぎ
- 電子カルテの「アレルギー情報」欄に、「(製品名)で血圧低下あり」など、誰が見ても分かるように明確に記載する。患者さん自身にも、どの薬剤で副作用があったかを説明し、必要であればアレルギーカードなどを渡す。
- ④ 代替策の検討
- 次回の検査が必要になった場合、CTの担当医は、今回の記録を基に、異なる製品のヨード造影剤を使用する。造影MRIなど、別のモダリティの検査を検討する。ステロイド剤などの前投薬を行ってから、慎重に造影検査を行う といった対策を検討します。
今日のまとめ
- 造影剤の副作用が発生した場合、次回検査に備えて共有すべき最も重要な情報は、使用した造影剤の「製品名」である。
- 同じヨード造影剤でも、製品によって成分が異なるため、原因となった製品を特定することが再発防止の鍵となる。
- 腎機能(eGFR)は造影剤腎症、アレルギー様反応は急性の副反応と、リスクの種類を区別して理解することが重要。
- 安全な造影検査の実施は、放射線技師による正確な観察・記録・情報共有の上に成り立っている。


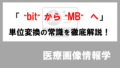

コメント