MRIの拡散強調像で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 真の拡散係数が得られる。
- 組織のT₂値の影響を受ける。
- 急性期脳梗塞で低信号を呈する。
- b値が低いほど拡散が強調される。
- 水分子のブラウン運動を画像化している。
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
2.組織のT₂値の影響を受ける。
5.水分子のブラウン運動を画像化している。
解説
✔ DWI: “水分子の動きやすさ💧”を可視化する技術
MRI拡散強調像(DWI)は、生体組織の中にある水分子が、どれだけ自由に動き回れるか(拡散しているか)を画像化する特殊な撮像法です。 水分子のこのランダムな動きをブラウン運動と呼びます。
水分子の動きを、部屋の中の人に例えてみましょう。
- 正常な脳組織 :🏃♂️ (広い体育館)
- 細胞の外はスペースが広く、水分子(人)は自由に走り回れます(=拡散が速い)。
- 急性期脳梗塞の組織 :🚶♂️ (満員電車)
- 発症直後の脳梗塞では、細胞がパンパンに腫れあがり(細胞性浮腫)、細胞の外のスペースが極端に狭くなります。水分子(人)は身動きが取れず、動きが著しく制限されます(=拡散が制限されている)。
DWIは、この「動きにくい状態(拡散制限)」を鋭敏に捉え、白く明るい信号(高信号)として描き出すことができるのです。
✔ DWI信号の正体:T₂強調画像とのハイブリッド
DWIは、実はT₂強調画像をベースにしたシーケンスに、拡散を検出するための傾斜磁場(MPG)を印加したものです。そのため、最終的に得られるDWIの信号は、「拡散のしにくさ」と「T₂値の長さ」という2つの情報が混ざり合ったものになります。
✔ 各選択肢について
1. 真の拡散係数が得られる。
- ❌ 誤り
- DWIの信号にはT₂値の影響が混ざっているため、そこから算出されるのは「見かけの拡散係数(ADC: Apparent Diffusion Coefficient)」です。T₂値の影響を取り除いた「真の拡散係数」を直接得ることはできません。
2.組織のT₂値の影響を受ける。
- ✅ 正解
- 上記の通り、DWI信号は拡散とT₂値の両方の影響を受けます。このため、古い脳梗塞など、単純にT₂値が長いだけでDWIが高信号に見える「T₂ shine-through」という現象が起こり得ます。
3.急性期脳梗塞で低信号を呈する。
- ❌ 誤り
- 急性期脳梗塞では、拡散制限が起こるためDWIでは高信号を呈します。低信号になるのは、T₂値の影響を除去したADCマップの方です。
4.b値が低いほど拡散が強調される。
- ❌ 誤り
- b値は「拡散をどれだけ強く反映させるか」という感度設定です。b値を高くするほど拡散の動きに敏感になり、拡散が制限されている部分がより白く強調されます。(臨床では通常b=1000 s/mm²程度)
5.水分子のブラウン運動を画像化している。
- ✅ 正解
- DWIは、組織内における水分子のブラウン運動の「動きやすさ」を画像コントラストとして表現する技術です。
出題者の“声”

この問題、狙いは単純そうに見えて実は二段構えじゃ。
まず「DWIは何を映すか」という原理、そして「DWI信号にはT₂成分が混じる」という、知っておくべき落とし穴を知っておるかじゃ。
多くの学生は「DWI=急性期脳梗塞=高信号」と単純な暗記で済ませておる。そこを突くために、「真の拡散係数」や「低信号」といった選択肢を混ぜ、知識が曖昧な者を揺さぶるのじゃ。
特に2番(T₂値の影響)を正解としたのは、DWIとADCマップをセットで評価することがなぜ必須なのか、その理由を理解しているかを試すため。
この問題でまんまと引っかかる者は、原理を分かっているつもりで分かっていないことが露呈するのじゃよ。
臨床の“目”で読む

急性期脳梗塞の診断において、DWIは最前線に立つシーケンスですが、臨床現場では単純に「DWIで白い=新しい脳梗塞」とは判断しません。
ーDWI読影の落とし穴ー
- T₂ shine-through
- DWIで高信号でも、ADCマップが低信号でなければ、それは「見かけ上」白く見えているだけの偽陽性かもしれません。これを脳梗塞と誤診すれば、不要な治療に進んでしまうリスクがあります。
- 鑑別診断
- 脳梗塞以外にも、脳膿瘍や一部の脳腫瘍、急性脱髄疾患なども拡散制限を来たし、DWIで高信号・ADCマップで低信号となることがあります。臨床情報との統合が不可欠です。
ー救急現場でのスピードと正確性ー
救急外来で急性期脳梗塞の診断は、1分1秒を争う状況です。私たちは、迷わず適切な撮像条件で数分以内に画像を提供できなければなりません。 なぜDWIだけでなくADCマップもセットで求められるのか。その理由を深く理解していることが、現場での迅速かつ正確な対応に繋がります。
今日のまとめ
- DWIは、水分子のランダムな動き(ブラウン運動💧)を画像化する技術である。
- 急性期脳梗塞では細胞性浮腫で拡散が制限され、DWIで高信号、ADCマップで低信号となる。
- DWI信号はT₂値の影響を受けるため、「T₂ shine-through」と呼ばれる偽陽性があり得る。
- 「真の拡散制限」の判定には、DWIとADCマップのセットでの評価が絶対条件である。
- b値は拡散の感度。値を高くするほど、拡散の影響が強調される。

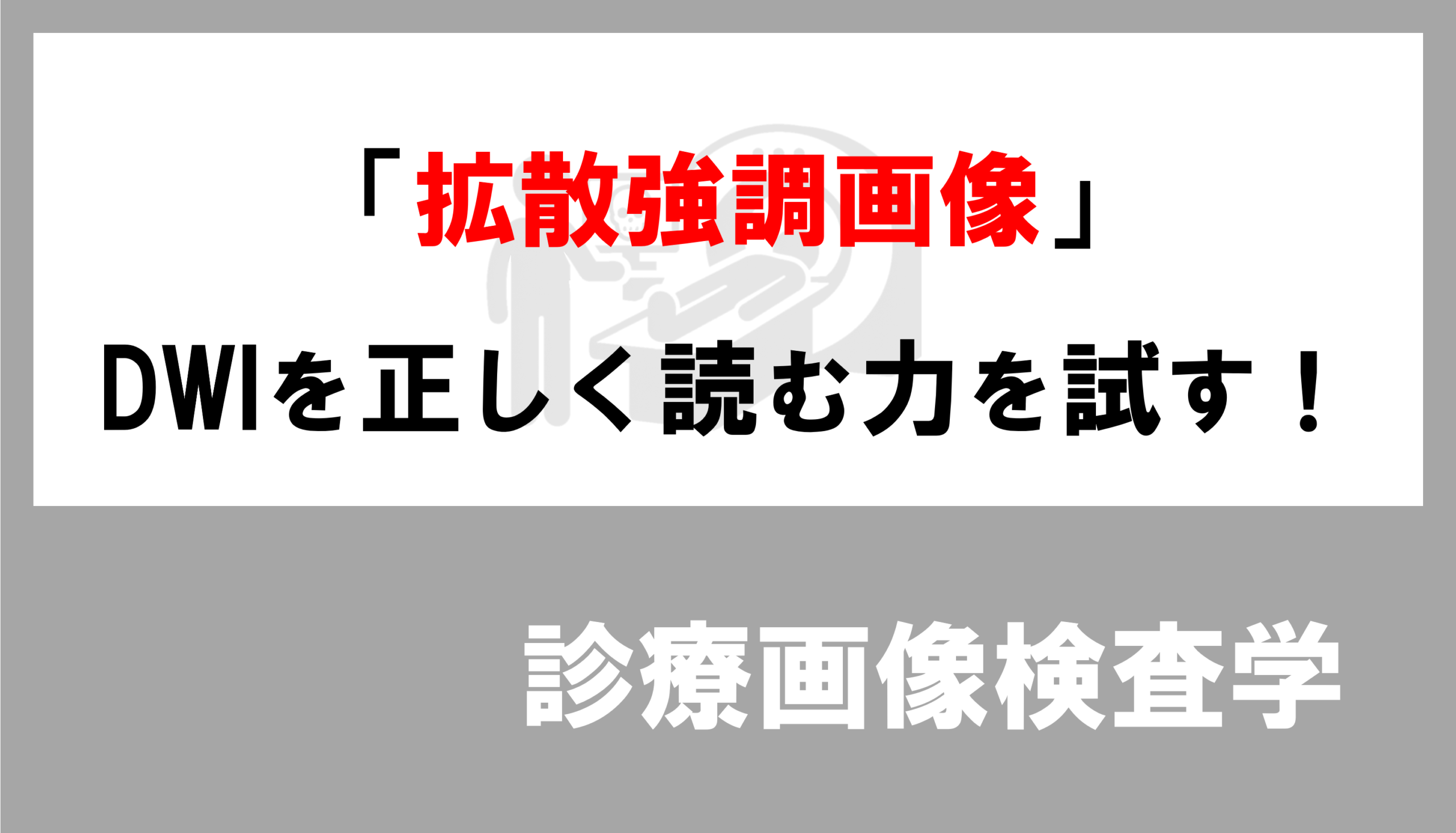
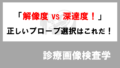

コメント