頭部MRIのFLAIR像で最も高信号を呈するのはどれか。
- 側脳室
- 眼窩脂肪
- 頭蓋骨皮質
- 大脳基底核
- シルビウス裂
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
2.眼窩脂肪
解説
✔ FLAIRとは?:水の信号だけを消す魔法のシーケンス 💧⚫
FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery)は、MRIの撮像法の一つで、一言で言えば「T₂強調画像から、脳脊髄液(CSF)の信号だけを黒く消し去った画像」です。
湖に浮かぶ白いスイレンの花を写真に撮る場面を想像してみてください。
- 通常のT₂強調画像
- 湖の水面が太陽光でキラキラと白く輝いて(脳脊髄液が高信号)、スイレンの花(病変)も白く見えます。これでは、花が水面の輝きに紛れて見えにくいことがあります。
- FLAIR像
- 特殊な偏光フィルターを使って、水面のキラキラ(脳脊髄液の信号)だけをカットした写真です。湖の水は黒く写り、その中に浮かぶスイレンの花(病変)だけがくっきりと浮かび上がって見えます。
この原理により、脳室や脳溝といった脳脊髄液に接する部分に発生した病変を、明瞭に描き出すことができるのです。
✔ FLAIR像における各組織の信号パターン
- 脳脊髄液 (CSF):低信号(信号が抑制され、黒く見える)
- 脂肪 (眼窩脂肪など):高信号(信号は抑制されず、白く明るく見える)
- 脳実質 (脳の組織):中間信号(灰白質は白質よりやや高信号)
- 頭蓋骨皮質:無信号(信号を発しないため、黒く抜けて見える)
したがって、選択肢の中で最も高信号を呈するのは眼窩脂肪となります。
✔ 各選択肢について
1. 側脳室
- ❌ 誤り
- 内部は脳脊髄液で満たされているため、FLAIRの抑制効果により黒く(低信号に)描出されます。
2.眼窩脂肪
- ✅ 正解
- 脂肪は、FLAIRの脳脊髄液抑制の影響を受けません。そのため、ベースとなるT₂強調画像の性質を反映し、白く(高信号に)描出されます。
3.頭蓋骨皮質
- ❌ 誤り
- 骨の硬い部分(皮質骨)は、MRIでは信号をほとんど発しないため、黒く(無信号に)見えます。
4.大脳基底核
- ❌ 誤り
- 脳の実質(灰白質)であり、中間的な信号を示します。脂肪のような強い高信号ではありません。
5.シルビウス裂
- ❌ 誤り
- 脳の深いシワ(脳溝)であり、内部は脳脊髄液で満たされているため、黒く(低信号に)なります。
出題者の“声”

この問題の狙いは、「FLAIRの本質=髄液消去」を理解しているか、ただ一点じゃ。
多くの学生は「FLAIR=脳梗塞や多発性硬化症に使う」という臨床応用だけで覚えておる。そこで、あえて「正常構造で一番明るいものは何か?」と問うことで、信号パターンの基礎を押さえているかを試しておるのじゃ。
最大のワナは「側脳室」と「シルビウス裂」。T₂強調像のイメージが頭にあると、これらが白く見えると錯覚し、つい選んでしまう。しかし、FLAIRでは主役であるはずの髄液は黒く消される。
この「T₂強調像との決定的な違い」に気づけるかが、勝負の分かれ目じゃった。
臨床の“目”で読む

FLAIRは、脳MRIの基本シーケンスの中でも特に病変検出能が高く、日常臨床で欠かせない存在です。
ーFLAIRが得意な疾患ー
- 脳梗塞
- 発症から数時間後(亜急性期)の病変や、脳室周囲の小さなラクナ梗塞の検出に優れます。
- 脱髄疾患(多発性硬化症など)
- 脳室周囲に好発する病変(プラーク)を、髄液に邪魔されずに明瞭に捉えることができます。
- 髄膜炎・くも膜下出血
- 通常は黒い脳溝やくも膜下腔に、異常な高信号が見られることで診断に繋がります。
ー読影の注意点ー
この「髄液が黒くなる」という特徴を理解していないと、「脳室のすぐ隣にある小さな病変を見逃す」「白く見えるものを何でも異常だと誤認する」といった誤読の原因になります。 「FLAIRでは、髄液は真っ黒 ⚫、脂肪は真っ白 ⚪」 この基本パターンを確実に覚えておくことが、国試でも臨床でも、正確な判断を下すための鍵となります。
今日のまとめ
- FLAIRは、水(脳脊髄液)の信号を抑制した T₂強調画像である。
- 脳脊髄液は黒く(低信号)、脂肪は抑制されずに白く(高信号)描出される。
- 骨皮質は信号を持たず黒く、脳実質は中間的な信号を示す。
- FLAIRの主な目的は、脳室や脳溝に接する病変を明瞭に検出することである。
- T₂強調像との信号の違いを理解することが、誤診を防ぎ、病変検出能を向上させる。

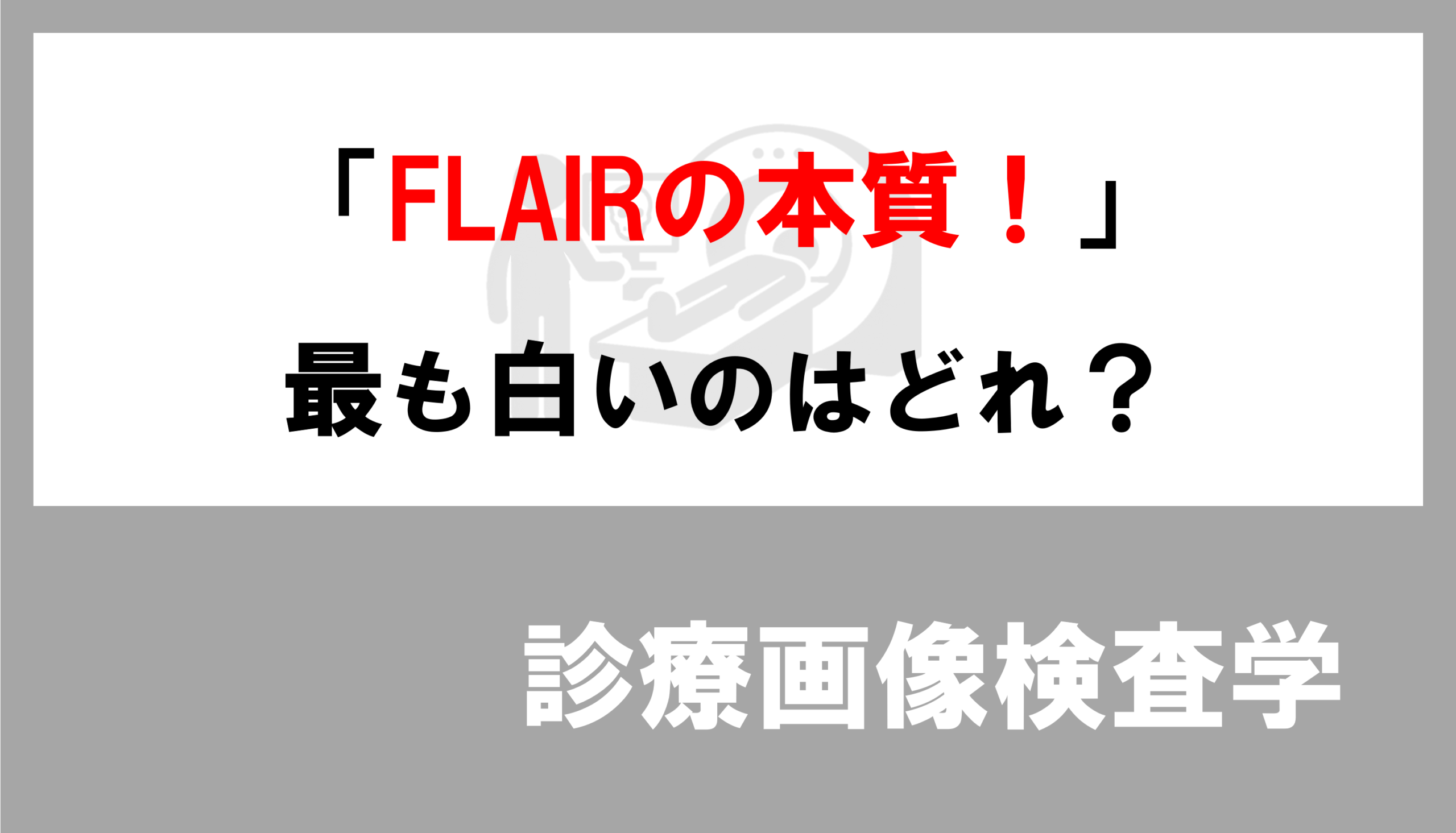


コメント