Silicon photomultiplier〈SiPM〉PET検出器で正しいのはどれか。
- 冷却が不要である。
- 磁場の影響を受ける。
- 光子数を求めることができない。
- 光電子増倍管より時間分解能が高い。
- 物理的サイズは光電子増倍管と同等である。
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
4. 光電子増倍管より時間分解能が高い。
解説
✔ SiPMとは?
- SiPM(Silicon photomultiplier)は、シリコンアバランシェフォトダイオード(APD)を多数並べた構造を持つ、高感度・高速応答の半導体型光検出器です。
- 従来の光電子増倍管(PMT)に代わる新しい検出素子として、PET装置に使われています。
- 特にTOF-PET(Time-of-Flight PET)の時間分解能向上に貢献しており、PET/MRIや小型PETシステムでも活用が進んでいます。
✔ 各選択肢について
1. 冷却が不要である。
- ❌ 誤り
- SiPMは熱雑音(ダークカウント)が比較的多いため、冷却が推奨されることが多い。
- 室温での安定動作は難しい場合もある。
2.磁場の影響を受ける。
- ❌ 誤り
- SiPMは磁場に強く、MRI併用(PET/MRI)にも使用可能。
- 一方、PMTは磁場の影響を強く受ける。
3.光子数を求めることができない。
- ❌ 誤り
- SiPMは光子1個ごとのパルスを検出できるほど高感度。
- 光子数の定量が可能。
4.光電子増倍管より時間分解能が高い。
- ✅ 正解
- SiPMは応答時間が非常に速く、時間分解能に優れる。
- TOF-PETにおける位置精度や画像品質向上に貢献。
5.物理的サイズは光電子増倍管と同等である。
- ❌ 誤り
- SiPMは数mm角の非常に小型で、PMTよりはるかに小さく・軽量。
- コンパクトな装置設計が可能。
出題者の“声”

この問題では、SiPMという新しい検出器が、PETにどんなメリットをもたらしているかをちゃんと理解しておるかを見たかったのじゃ。
特に押さえておきたいのが、SiPMの“三種の神器”とも言える性能:
- 時間分解能の高さ(TOF-PETに直結)
- 磁場への強さ(PET/MRI対応)
- 小型・軽量化(高密度実装・高解像度化)
こうした強みを知らずに、「冷却いらん」「サイズは同じ」など、表面的な言葉に引っかかってしまうようではまだまだ修行が足りんぞい。
TOFの進化、そしてPET-MRIというハイブリッド機器の台頭をイメージして、SiPMの真価をきちんと頭に入れておくのじゃ!
臨床の“目”で読む

SiPM(シリコンフォトマル)は、次世代PET装置の心臓部ともいえる重要な検出器です。
- 小型で並列配置しやすく、検出器を密に配置できる → 空間分解能が向上
- 磁場に強く、MRIとの併用が可能 → PET/MRIハイブリッド装置の実現
- 応答速度が速い → TOF-PETでの時間分解能向上 → より鮮明な画像に
従来のPMT(光電子増倍管)は大きく・磁場に弱いため、設計の制約が多く、特にPET-MRIとの相性が悪かったのですが、SiPMによってその壁が一気に崩されつつあります。
技術的な特徴を理解したうえで、「どのように臨床の画像に貢献しているのか」を説明できる技師になることが、これからますます求められると思います。
キーワード
- SiPM(Silicon Photomultiplier)
- PMT(Photomultiplier Tube)
- 時間分解能
- PET-MRI

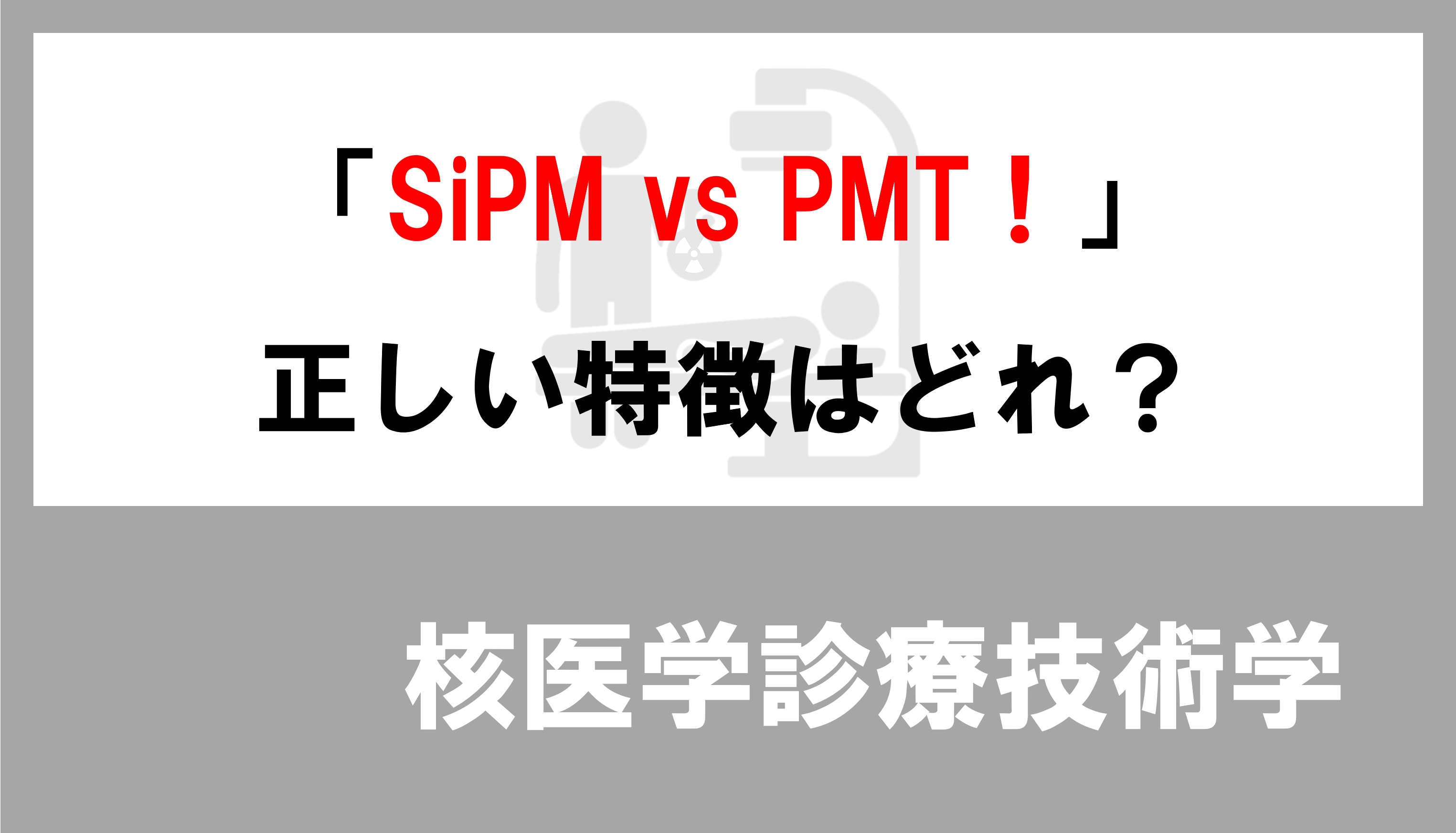
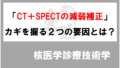
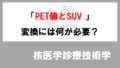
コメント