骨シンチグラフィで正しいのはどれか。
- 骨折では集積が低下する。
- 骨代謝亢進部位に集積する。
- 骨肉腫では集積が欠損する。
- 腸管に生理的集積を認める。
- 多発転移では bone scan index〈BSI〉が低下する。
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
2.骨代謝亢進部位に集積する。
解説
✔ 骨シンチグラフィとは?
- ⁹⁹ᵐTc–MDP(メチレンジホスホネート)などのリン酸塩トレーサーを使って、骨代謝の活発な部位=骨形成が盛んな場所を画像化する検査です。
- 骨代謝が活発な場所では、トレーサーが骨基質(ヒドロキシアパタイト)に取り込まれ、γ線を放出=ホットスポットとして描出されます。
✔ 各選択肢について
1. 骨折では集積が低下する。
- ❌ 誤り
- 骨折部位は修復過程で骨代謝が亢進するため、通常は強い集積(ホットスポット)を示す。
2.骨代謝亢進部位に集積する。
- ✅ 正解
- 骨形成が活発な部位に⁹⁹ᵐTc–MDPが集まり、画像上で強く描出される。骨転移・骨腫瘍・骨折・変形性関節症(OA)などで高集積。
3.骨肉腫では集積が欠損する。
- ❌ 誤り
- 骨肉腫は骨形成が非常に活発で、強い集積像(ホットスポット)を示す。
4.腸管に生理的集積を認める。
- ❌ 誤り
- ⁹⁹ᵐTc–MDP は主に 腎排泄 され、尿として膀胱に集積します。腸管での生理的集積はほとんどありません。
- 一部、胆汁などに代謝物がわずかに分泌される場合は肝・胆汁管から肛門近傍で軽度の排泄描出が見られることがありますが、腸管そのものに意味のある生理的集積は認めません。
5.多発転移では bone scan index〈BSI〉が低下する。
- ❌ 誤り
- BSI は「骨シンチで検出される腫瘍性病変面積の全骨面積に対する割合」を%換算した定量指標であり、骨転移が増えれば増えるほど BSI は増大します。
- 多発転移患者では BSI が大きくなり、治療効果判定や予後予測に活用されます。
出題者の“声”

この問題では、「骨シンチグラフィの基本原理がきちんと頭に入っておるか」を確認したかったのじゃ。
骨シンチの基本はただひとつ、骨代謝(特に骨形成)が活発な部位にトレーサーが集まる=ホットスポットになるということじゃ。
それがわかっておれば、「骨折で集積が低下する」や「骨肉腫で集積が欠損する」なんて選択肢は、直感的におかしいと気づけるはずじゃな。
たとえ原理を忘れていたとしても、選択肢1、2、3を見た時点で、2だけが“増える”という正反対のことを言っておると気づければ、選択肢4・5に何が書いてあったとしても、絞り込みで正解を導き出せるじゃろう。
もちろん、「なぜそれが正しくて、なぜ他が間違いなのか」を説明できることが最も大切なんじゃが、国家試験の五択問題においては、こうした“選択肢の見方・考え方”そのものが得点力につながるのじゃ。
臨床の“目”で読む

骨シンチグラフィは、がんの骨転移評価をはじめ、骨折の治癒過程、炎症性病変、骨腫瘍の活動性評価など、幅広い臨床領域で活用される重要な検査です。
実際の現場では、「ここが光っている=病変」と単純に判断されがちですが、「なぜそこに集積しているのか」という視点、つまり骨代謝の活性をどう読み解くかが大切になります。
たとえば、骨肉腫では骨芽細胞の活性が非常に高いため、強い集積が見られます。
一方、骨折直後の修復期でも炎症や骨形成の反応で集積が強くなることがあります。
こうした腫瘍性と非腫瘍性の集積をどう見分けるかが、読影のカギとなります。
さらに最近では、BSI(Bone Scan Index)という定量的な指標の重要性も高まっています。
BSIは、「骨シンチ画像のうち、どのくらいの面積が病変に占められているか」を数値で表すもので、治療効果の判定や予後予測にも用いられる有用なパラメータです。
経時的に変化を追えるため、客観的な評価ツールとしても信頼されています。
つまり、「ただ撮る」だけではなく、“その画像がどう診断や治療に活かされるか”まで見据えることができるかどうか。それが、一段上の放射線技師の視点につながっていきます。
キーワード
- 骨シンチグラフィ(⁹⁹ᵐTc-MDP / HMDP)
- BSI(Bone Scan Index)

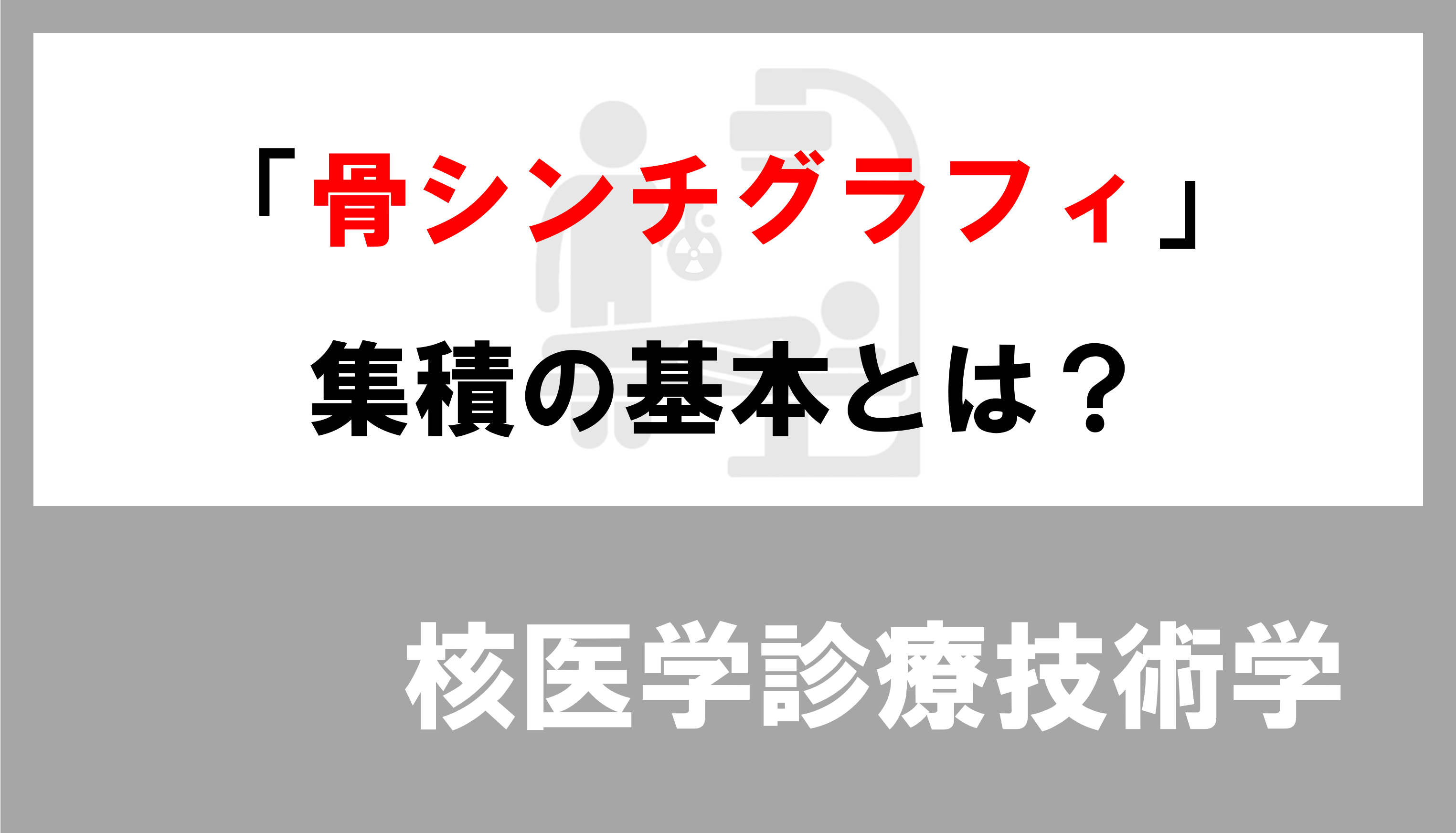
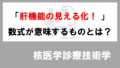

コメント