電離箱線量計の特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。
- アニーリングが必要である。
- 電離空洞内の温度が高いと電離量は増加する。
- 電離空洞内の気圧が低いと電離量は増加する。
- イオン再結合は電離空洞内の電離密度に依存する。
- 水吸収線量校正定数は ⁶⁰Co ガンマ線を用いた校正が可能である。
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
4.イオン再結合は電離空洞内の電離密度に依存する。
5.水吸収線量校正定数は ⁶⁰Co ガンマ線を用いた校正が可能である。
解説
✔ 電離箱線量計とは?
- 電離箱線量計は、放射線治療や診断領域での絶対線量測定に広く用いられる標準的な線量計です。
- 密閉された空洞内に入射した放射線による空気の電離量(イオンペア数)を電流として測定する。
- 高精度・再現性が高く、校正がしやすいことから基準線量測定に広く使用されている。
✔ 各選択肢について
1. アニーリングが必要である。
- ❌ 誤り
- アニーリング(加熱処理による初期化)は、TLD(熱ルミネセンス線量計)など、放射線のエネルギーを素子内に蓄積するタイプの固体線量計に必要な操作。
2.電離空洞内の温度が高いと電離量は増加する。
- ❌ 誤り
- 電離量は、空洞内にある空気の分子数(=密度)に比例。
- 温度が上がると空気は膨張して密度が下がるため、放射線が相互作用する相手が減り、結果として電離量は減少。
3.電離空洞内の気圧が低いと電離量は増加する。
- ❌ 誤り
- 気圧が下がると、同様に空気の密度が下がるため、電離量は減少。
- そのため、正確な測定には温度・気圧補正が不可欠。
4.イオン再結合は電離空洞内の電離密度に依存する。
- ✅ 正解
- イオン再結合とは、生成されたプラスとマイナスのイオンが、電極に集められる前に再び結合して中性の分子に戻ってしまう現象。
- 空洞内のイオンの密度が高い(=高線量率、高線量)ほど、イオン同士が出会う確率が高くなり、再結合が起こりやすい。
5.水吸収線量校正定数は ⁶⁰Co ガンマ線を用いた校正が可能である。
- ✅ 正解
- 日本を含む多くの国で、⁶⁰Co(1.17、1.33 MeVのγ線)を基準線源とし、水中での吸収線量を基準として線量計を校正。
出題者の“声”

この問題では、放射線治療の線量測定で最も基本となる「電離箱線量計」の原理と、その運用上の注意点を正確に理解しているかを確認したかったのじゃ。
「アニーリング」と聞いたらTLD、「温度・気圧」と聞いたら空気密度、というように、キーワードを正しく結びつけられるかが第一歩じゃ。特に、温度や気圧が上がると空気密度が「下がる」という関係は、物理の基本中の基本じゃぞ。
そして、イオン再結合や⁶⁰Coによる校正の話は、絶対線量測定の根幹に関わる重要な知識じゃ。
なぜ補正が必要なのか、なぜ⁶⁰Coが基準なのか。そうした「なぜ?」を説明できてこそ、単なる暗記から一歩進んだ、真の理解と言えるのじゃ!
臨床の“目”で読む

電離箱線量計は、リニアックから照射される放射線の線量を絶対的に保証するための「基準器」であり、その精度管理は放射線治療の安全性の根幹をなします。臨床現場で私たちが特に意識すべきは、「補正」の重要性です。
- 温度・気圧補正:測定時の環境(温度・気圧)は日々変動します。これを標準状態(例: 22℃, 1013.25hPa)に補正しない限り、測定値の信頼性は担保されません。
- イオン再結合補正:IMRTやSBRT(体幹部定位放射線治療)のように、短時間で高い線量を照射する治療法では、イオン再結合の影響が大きくなります。これを補正しないと、実際の線量よりも値を低く見積もってしまう危険性があります。
最近は自動で補正をしてくれる測定器もありますが、「この測定値は、どのような物理現象に基づいており、どんな補正を経て得られた信頼できる値なのか」を理解し、説明できることはとても大切です。
キーワード
- 電離箱線量計(Ionization Chamber)
- 水吸収線量基準/⁶⁰Co校正
- 温度補正
- 気圧補正
- イオン再結合

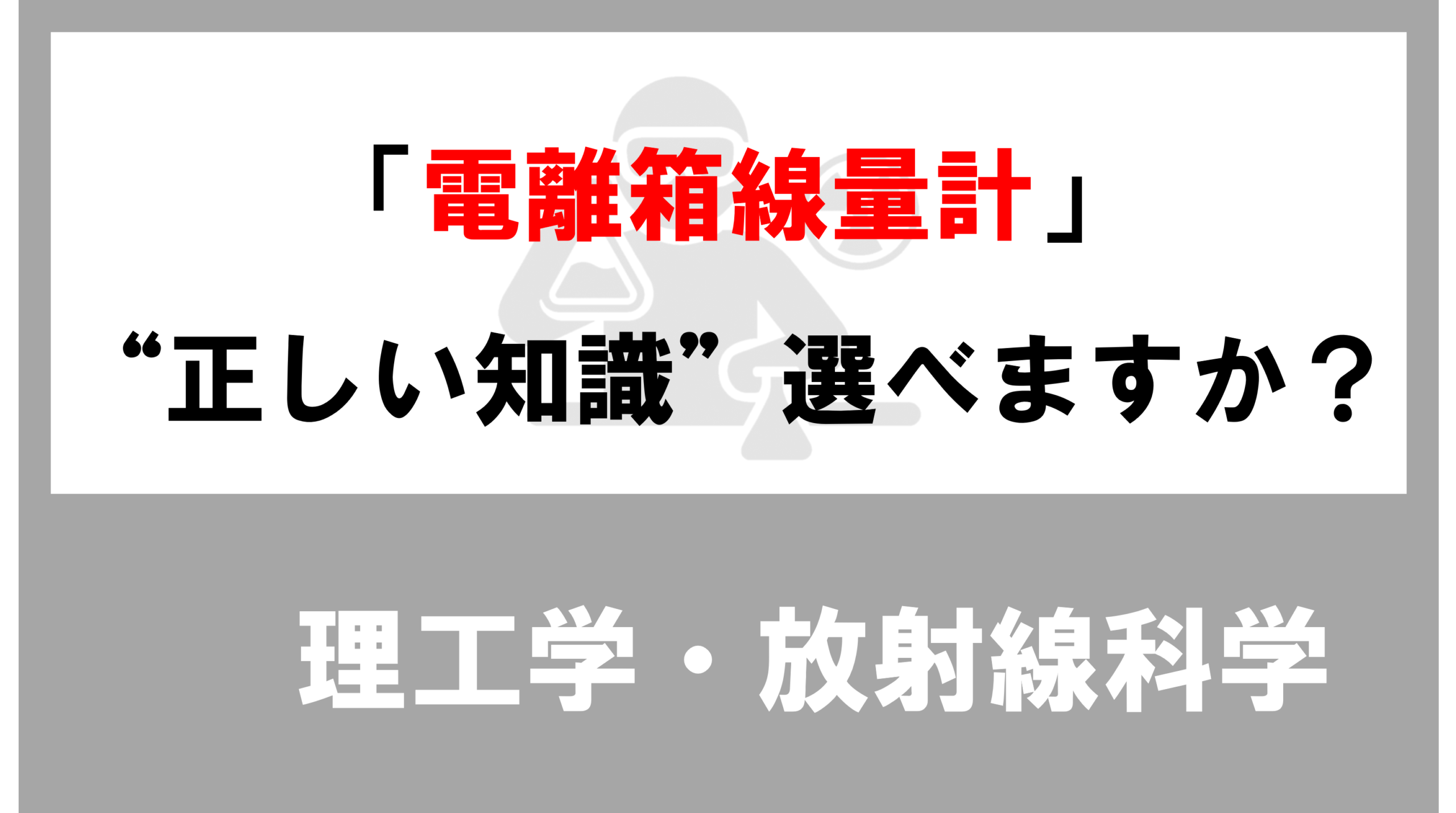


コメント