診療放射線技師による情報の取扱いで正しいのはどれか。
- 守秘義務は診療放射線技師でなくなった後も続く。
- 患者の情報は医療機関内であれば自由に共有してよい。
- 診療放射線技師はカルテの情報を閲覧することができない。
- 個人情報保護法では患者名を画像に載せることは禁止されている。
- 患者本人の了解がなくても家族からの要請があれば情報開示ができる。
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
1.守秘義務は診療放射線技師でなくなった後も続く。
解説
✔ 守秘義務は“辞めたあと”も続く
診療放射線技師法 第29条に明記されています:
- 「診療放射線技師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。診療放射線技師でなくなった後も、同様とする。」
つまり、退職後も職務上知った個人情報は口外禁止。知人や家族へのうっかり発言も違反となり得ます。
✔ 各選択肢について
1. 守秘義務は診療放射線技師でなくなった後も続く。
- ✅ 正解
- 放射線技師法に明記された厳格な守秘義務。
2.患者の情報は医療機関内であれば自由に共有してよい。
- ❌ 誤り
- 情報共有は、その患者の診療に直接関わる医療スタッフ間で、業務上必要な範囲に限定されます。
- 院内であっても、無関係な職員との情報共有はプライバシーの侵害にあたります。
3.診療放射線技師はカルテの情報を閲覧することができない。
- ❌ 誤り
- 安全で質の高い検査を実施するために、業務上必要な範囲で患者の病名、既往歴、アレルギー情報などを確認することは、認められており、むしろ不可欠です。
4.個人情報保護法では患者名を画像に載せることは禁止されている。
- ❌ 誤り
- 院内で患者を取り違えることなく安全に医療を提供するため、画像に患者IDや氏名を表示することは必須です。
- 法律で禁止されているのは、 無断でそれらの情報が外部に漏洩・公開されることです。
5.患者本人の了解がなくても家族からの要請があれば情報開示ができる。
- ❌ 誤り
- 情報開示は、原則として本人の同意が必要です。
- たとえ家族であっても、本人の同意なしに情報を開示することはできません(※意識不明で本人の同意が得られない場合など、一部例外規定はあります)。
出題者の“声”

この問題では、診療放射線技師が扱う情報に対して、どこまで責任があるのか――とくに守秘義務の持続性を正しく理解しておるかを確認したかったのじゃ。
医療情報は、患者のプライバシーそのものであり、取り扱いを誤れば法的責任だけでなく、職業倫理の問題にも発展する重大な領域じゃ。
中でも「守秘義務は技師を辞めた後も続く」という点は、意外と見落とされがちな盲点。
「もう辞めたし関係ない」などとうっかり話してしまえば、それは技師としての倫理の欠如であり、明確な法令違反にもなるのじゃ。
また、「院内だから情報共有してもいい」「家族からの要請だから伝えていい」など、“一見正しそうだが実は誤り”な選択肢に引っかかる者もおるかもしれん。
この問題は、単なる知識だけでなく、専門職としての高い倫理観を試す一問じゃ!
臨床の“目”で読む

診療放射線技師は、日々の業務で膨大な個人情報・診療情報にアクセスします。
CTやMRIのオーダには病名や既往歴が書かれ、過去のレポートを読めば患者さんの詳細な病状もわかります。これらの情報は、より安全で質の高い検査を行うために不可欠なものです。
しかし、その情報を扱う私たちには、「知る権利」と「話さない義務」が常にセットで求められます。
- 「知る権利」:安全な検査実施のため、必要な患者情報を参照する権利と責任。
- 「話さない義務」:職務上知り得た情報を、正当な理由なく決して漏らさない義務。
特に注意すべきは、地元の病院などで友人や知人、その家族の検査を担当するケースです。検査室で知った情報を、たとえ善意からであっても、院外で口にすることは許されません。また、匿名であっても、珍しい症例や特徴的な画像をSNSなどに投稿する行為は、個人が特定されるリスクを伴う極めて危険な行為です。
「知る」ことはプロフェッショナルとして必要不可欠。しかし、「話す」ことには細心の注意を払う。この鉄の規律を守り抜くことこそが、患者さんからの、そして社会からの信頼の礎となるのです。
キーワード
- 守秘義務
- 個人情報保護法
- 診療放射線技師法
- 職業倫理

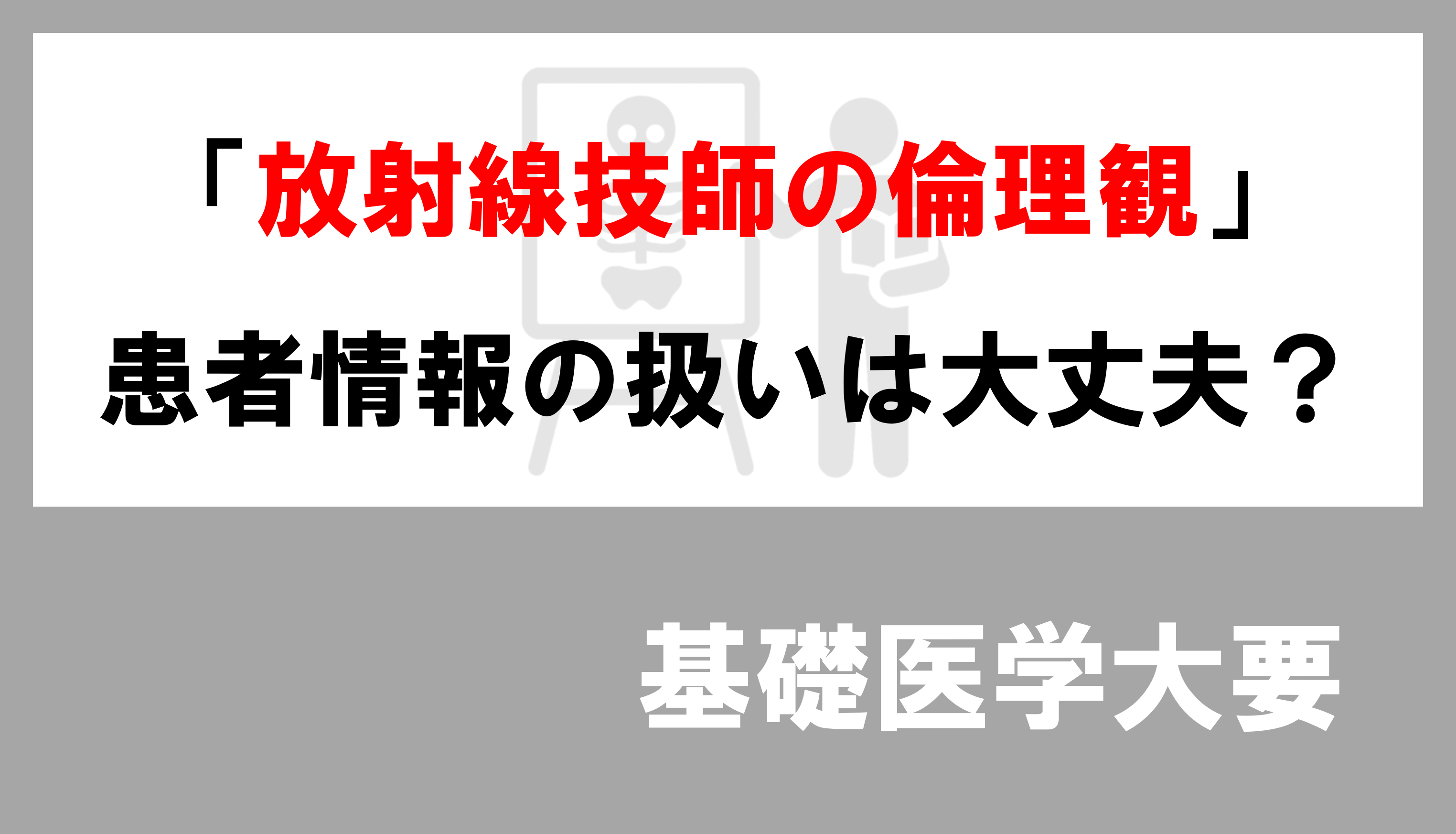
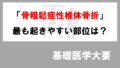

コメント