肺結核の主な感染経路はどれか。
- 空気感染
- 垂直感染
- 接触感染
- 飛沫感染
- 媒介物感染
出典:厚生労働省公開PDF(令和7年版)
1.空気感染
解説
✔ 感染経路の分類とは?
感染症の病原体が「どのように他者へうつるか」を示したものが感染経路です。国試では、まず代表的な3つの経路の違いを明確に区別することが重要です。
- 接触感染: 病原体が付着した手やドアノブ、物品などに直接触れることで感染します。(例: ノロウイルス、MRSA)
- 飛沫感染: 咳やくしゃみで飛び散る、水分を含んだ大きな粒子(5μm以上)のしぶきを吸い込んで感染します。重いので遠くへは飛べません。(例: インフルエンザ、風疹)
- 空気感染: 水分が蒸発した微細な粒子(5μm未満)=「飛沫核」が、長時間ふわふわと空気中を漂い、それを吸い込むことで感染します。広範囲に拡散するのが特徴です。(例: 結核、麻しん、水痘)
✔ 結核菌は「空気感染」の代表格!
肺結核の病原体である結核菌は、感染者の咳やくしゃみで空気中に放出された後、水分が蒸発して「飛沫核」となります。 この飛沫核は非常に軽く、長時間にわたって空気中を浮遊し、気流に乗って遠くまで拡散します。 この目に見えない粒子を他者が吸い込んでしまうことで、感染が成立してしまうのです。
✔ 各選択肢について
1. 空気感染
- ✅ 正解
- 結核菌は飛沫核として空気中を漂い、広範囲に感染を広げます。
2.垂直感染
- ❌ 誤り
- 母体から胎児・新生児へとうつる感染経路です。(例: HIV、B型肝炎)
3.接触感染
- ❌ 誤り
- 病原体に直接触れることでうつります。
4.飛沫感染
- ❌ 誤り
- 咳やくしゃみによる大きな飛沫で感染。
- インフルエンザやコロナなどが典型。
5.媒介物感染
- ❌ 誤り
- 蚊などの昆虫や、汚染された食品・水などを介してうつります。(例: マラリア、デング熱)
出題者の“声”

この問題の核心は、「飛沫感染」と「空気感染」の決定的な違いを理解しているかじゃ。 言葉は似ておるが、その危険性は全くの別物!
ポイントは粒子のサイズと、その滞空時間じゃ。 飛沫感染は、しぶきを直接浴びなければリスクは下がる。しかし、空気感染を引き起こす「飛沫核」は、同じ部屋の空気を吸っているだけで感染しうる。感染者が去った後でも、その空間にはリスクが残り続けるのじゃ。
「咳をしている人から離れればOK」という甘い考えが通用しない、それが空気感染のポイントなのじゃ!
この性質を正しく理解していないと、感染対策において大きな落とし穴となる。
ただ知識として覚えるのではなく、「なぜ飛沫感染では足りないのか」まで考え抜くことが大事じゃ!
臨床の“目”で読む

放射線技師は、結核が疑われる患者さんの撮影を担当する機会も多く、正しい感染対策は自身の責務です。
- 陰圧隔離室の利用
- 結核患者の検査や撮影では、空気感染対策として陰圧隔離室を使用します。部屋の空気が外に漏れない設計になっており、放射線技師はマスク(N95など)を着用して検査を行います。
- 個人防護具の選択
- 普通のサージカルマスクでは飛沫は防げても、飛沫核は通過する可能性があります。結核検査時には必ず N95マスクを装着し、顔とマスクが密着していることを確認します。
- 検査後の換気・清掃
- 撮影後は十分な換気(少なくとも30分以上)と、床・壁面の清掃を実施します。飛沫核がしばらく室内を漂うため、次の患者を安全に検査するためには機材の滅菌だけでなく、室内空気管理が重要です。
特に胸部X線やCT撮影を担当する際、病変の典型的な像(上肺野優位の空洞など)を見逃さないように意識することも求められます。
「この人、結核の可能性は?」と疑う視点は、放射線技師としての感染管理力にもつながります。
今日のまとめ
- 肺結核の主な感染経路は「空気感染」である。
- 原因は5μm未満の「飛沫核」。長時間、空気中を漂うのが特徴。
- 防御の基本はN95マスクの装着と、陰圧室での対応、検査後の十分な換気。
- 放射線技師は、画像所見から感染を疑うという臨床的な視点も極めて重要!

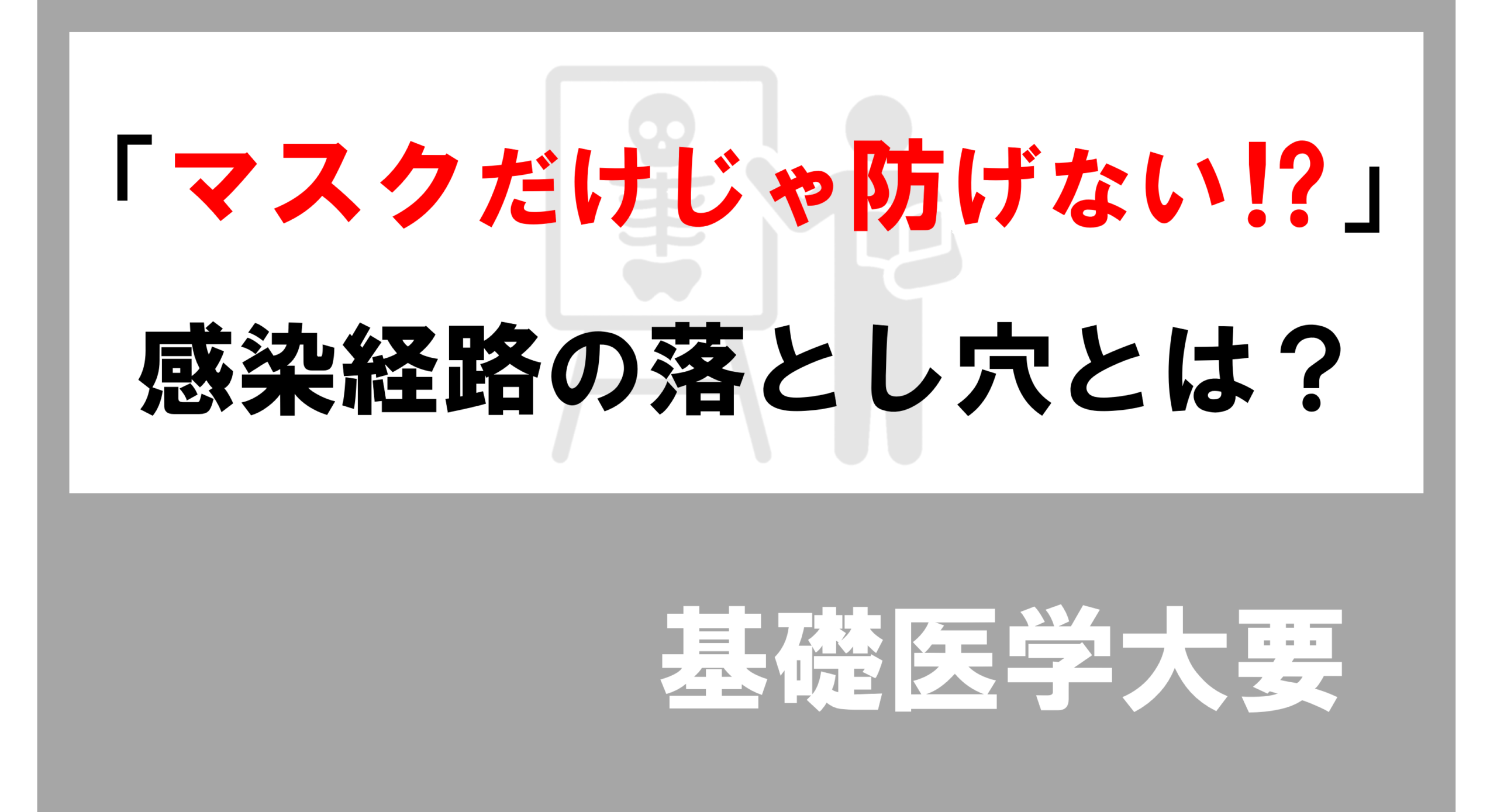


コメント